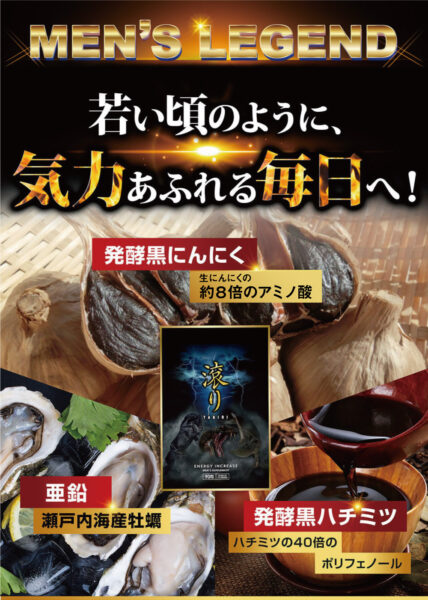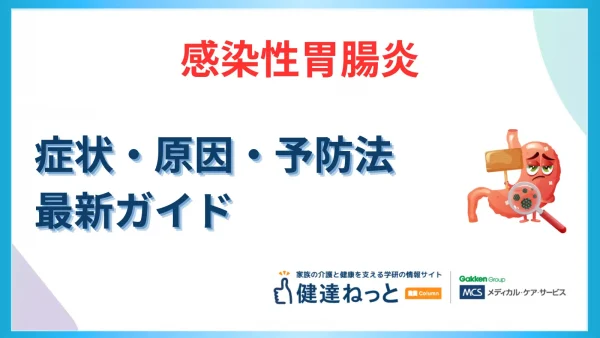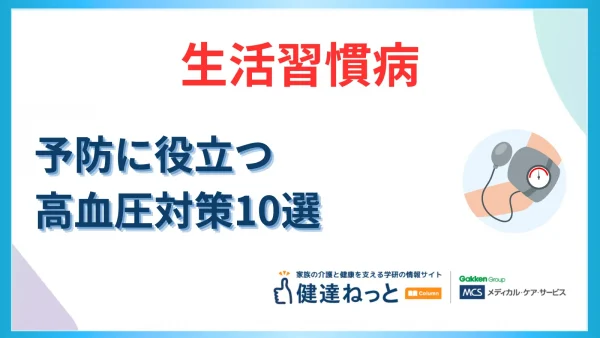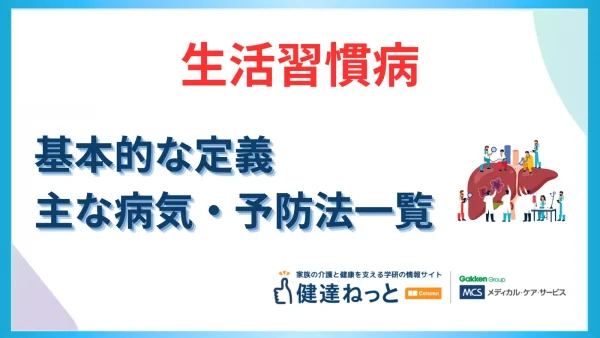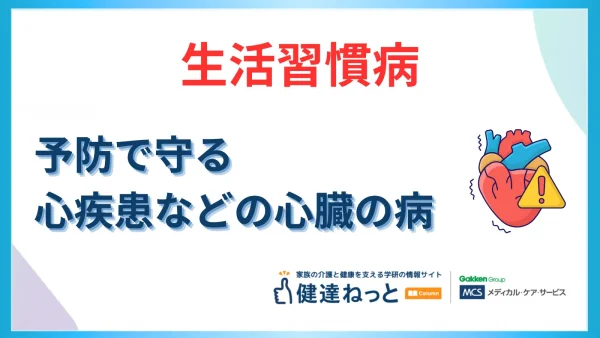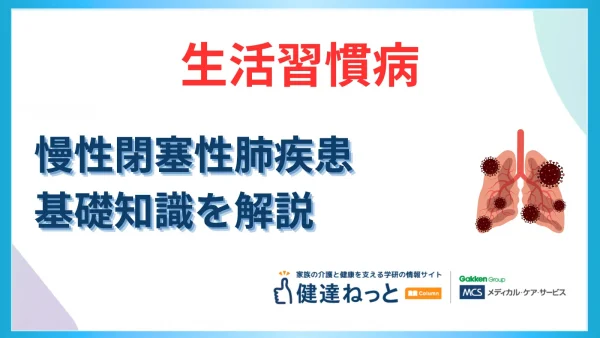亜鉛とは体内に存在する量が最も多いミネラルです。
生命維持に欠かせない役割を担っている栄養素の1つでもあります。
この記事では、亜鉛について解説しながら、亜鉛が多く含まれる食べ物や亜鉛を手軽に効率よく摂る方法などについてご紹介します。
本記事では、以下の内容についてご紹介します。
- 亜鉛の働きと摂取方法
- 亜鉛の1日の必要量
- 亜鉛の身体への影響
ぜひ、最後までご覧いただき、亜鉛不足にならない健康づくりの参考にしてください。
栄養素について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
栄養素は、健康を保つために欠かせない成分です。栄養素には具体的にどのような働きがあるのか御存じですか。本記事では栄養素について、以下の点を中心にご紹介します。 五大栄養素とは 五大栄養素の働き 一日あたりの[…]
スポンサーリンク
亜鉛とはどんな栄養素?

亜鉛は主に骨格筋・皮膚・肝臓・膵臓・前立腺・脳・腎臓などの臓器に存在しています。
約300種類以上の酵素の構成要素として重要な働きを担っている必須ミネラルの1つです。
しかし、人の身体は亜鉛を作り出すことができません。
よって、3食の食事、サプリメントなどから摂取する必要があります。
亜鉛についてより詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
ドラッグストアで亜鉛というサプリメントを見たことがあると思います。亜鉛は、体内では生成されない必須の栄養成分です。ではどのような働きをし、過不足になったときにどのような症状があらわれるのでしょう?本記事では亜鉛について以[…]
スポンサーリンク
亜鉛が豊富な食べ物リスト

亜鉛を多く含む食材は、魚介類、肉類、卵などの動物性食品と、穀類、豆類、ナッツ類などで、特に牡蠣に多く含まれています。
動物性の食品に含まれるタンパク質は、亜鉛の吸収率を高めるため、動物性の食品を多く摂ることが重要です。
逆に、食物繊維やフィチン酸は亜鉛の吸収を妨げるため、注意が必要です。
亜鉛を多く含む食材についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
魚介類
魚介類では生かきに最も多く含まれています。
その他、煮干し、たらこ、しらす干し、かつお節、ほたて、うなぎ蒲焼きなど
肉類
肉類では豚レバーに最も多く含まれています。
その他、牛もも肉、鶏レバー、鶏もも肉など
野菜類
切り干しだいこん、枝豆、しそ、たけのこ、ごぼうなど
豆類・ナッツ類
きな粉、油揚げ、納豆、厚揚げ、あずき、焼き豆腐など
穀類
精白米、そばなど
卵類
全卵、牛乳、プロセスチーズなど
各食材の詳しい含有量を表でまとめました。
| 食品名 | 亜鉛含有量(mg) | 食品名 | 亜鉛含有量(mg) |
| 生かき(養殖) | 13.2 | 鶏レバー | 3.3 |
| 煮干し | 7.2 | 鶏もも肉 | 1.6 |
| たらこ | 3.1 | 切り干しだいこん | 2.1 |
| しらす干し | 3.0 | 枝豆 | 1.4 |
| かつお節 | 2.8 | きな粉 | 4.1 |
| ほたて | 2.7 | 油揚げ | 2.5 |
| うなぎ蒲焼き | 2.7 | 精白米 | 0.6 |
| 豚レバー | 6.9 | そば | 0.4 |
| 牛肩ロース | 5.6 | 全卵 | 1.3 |
| 牛もも肉 | 4.8 | 牛乳 | 0.4 |
注)100gあたりの亜鉛含有量
出典:文部科学省【日本食品標準成分表 2020年版(八訂)】
亜鉛は野菜類や果物類にはあまり含まれていません。
そして、穀類や卵類よりも魚や肉類により多く含まれていることがわかります。
AGAは疾患であるため、必要な治療を施さなければ治すことはできません。さらに、AGAは進行性の脱毛症のため、できるだけ早く治療を始めないと手遅れになってしまいます。AGA治療を検討している方にとって、どのクリニックを選ぶかは非常に重[…]
手軽に亜鉛を摂る方法

亜鉛の腸管での吸収率は約30%といわれています。
食べ物から十分な亜鉛の摂取が難しいという方はサプリメントで補うのも良いでしょう。
亜鉛は単独で市販されている他、ビタミン系やミネラル系のサプリメントにも含まれている場合があります。
また、亜鉛は食べ物からの摂取が理想的です。
しかし、他の食品成分との作用で吸収率が低下してしまうこともあります。
サプリメントについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
亜鉛の吸収を助ける栄養も一緒に摂る
一緒に摂ると亜鉛の吸収率を上げる食材があります。
吸収率を上げるものとして
- クエン酸
- ビタミンC
- 動物性タンパク質
などがあります。
それでは、亜鉛の吸収率をあげる食べ物について詳しく見てみましょう。
タンパク質
動物性タンパク質は亜鉛の吸収率をあげる作用があります。
肉類、魚類、牛乳、チーズ、卵など
タンパク質について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]
ビタミンC+クエン酸
ビタミンCやクエン酸にも亜鉛の吸収率をあげる作用があります。
レモンやかぼす、柚子などの柑橘類など
ナッツで手軽に亜鉛補給!
亜鉛はアーモンドや落花生、くるみなどにも多く含まれています。
間食として摂取してみるのも良いでしょう。
汁物はお汁まで飲む
亜鉛は水に溶けやすい性質があります。
亜鉛を効率的に摂取するための調理の工夫として
- 短時間で加熱する
- 茹で汁を捨てる調理法は避け、煮汁ごと食べられる汁物やスープ料理にする
- 電子レンジで加熱、蒸す
などがあげられます。
亜鉛を効率よく摂取する際の注意点
亜鉛と一緒に摂取することで吸収率を下げてしまう食材があります。
注意するべき栄養素として
- 植物性食品に含まれている食物繊維やフィチン酸
- 加工食品に多く含まれているポリリン酸
などがあります。
これらの栄養素の摂りすぎには注意しましょう。
また、アルコール摂取は亜鉛の排泄量を増加させてしまうため、飲酒は控えめにしましょう。
亜鉛の1日の摂取量

亜鉛は、皮膚や肝臓、脳、腎臓などの細胞に含まれる必須ミネラルの1つです。
亜鉛は野菜類や果物類ではなく、穀類や卵類、特に魚や肉類に多く含まれています。
亜鉛が豊富な食べ物は、含有量の多い順に、牡蠣、煮干し、たらこ、しらす干し、かつお節、ほたて、豚レバー、牛肩ロース、牛もも肉、鶏レバー、鶏もも肉です。
以上を踏まえて、亜鉛の食事摂取基準について詳しく見てみましょう。
1日に必要な亜鉛の摂取量は、年齢や性別で異なっています。
| 年齢 | 男性の推奨量(mg) | 女性の推奨量(mg) |
| 18~29歳 | 11 | 8 |
| 30~49歳 | 11 | 8 |
| 50~64歳 | 11 | 8 |
| 65~74歳 | 11 | 8 |
| 75歳以上 | 10 | 8 |
*推奨量:ほとんどの人が必要量を満たす量(97.5%の人が充足)のこと。
出典:厚生労働省【日本人の食事摂取基準(2020 年版)】
18歳以上の亜鉛の推奨量は男性では10〜11mg、女性では8mgほどといわれています。
厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によると、亜鉛の平均摂取量は20歳以上の男性で9.2mg、女性で7.7mgです。
男女共に推奨量よりも下回っていることがわかります。
亜鉛が不足するとどうなるの?

亜鉛が不足すると、以下のような様々な症状が現れることがあります。
| 皮膚炎 | 脱毛 | 骨粗鬆症 |
| 味覚異常 | 貧血 | 食欲不振 |
| 下痢 | 成長障害 | 生殖機能の低下 |
| 免疫力の低下 | 低アルブミン血症 | 舌がヒリヒリする |
出典:日本臨床栄養学会【亜鉛欠乏症の診療指針2018】
特に以下のの症状が代表されます。
- 皮膚炎
- 味覚異常
- 免疫力の低下
- 成長障害
- 生殖機能の低下
それぞれの症状についてご紹介します。
皮膚炎
亜鉛が不足すると皮膚のターンオーバーが乱れ皮膚炎を発症します。
皮膚のターンオーバーが乱れるのは亜鉛が皮膚のタンパク質の合成に関与してるからです。
亜鉛不足による皮膚症状の1つとして、爪の変形にも影響を及ぼします。
味覚異常
味覚異常も亜鉛不足が原因で起こる症状です。
味覚を感じる舌の上皮細胞には亜鉛が豊富に含まれています。
亜鉛が不足すると、舌の味覚を感じる機能が低下して味覚異常が起こるのです。
舌のターンオーバーは短いので、亜鉛不足の影響が出やすいこともあります。
免疫力の低下
亜鉛不足は免疫力の低下につながるとされています。
亜鉛の働きには以下のようなものがあります。
- 生まれつき備わっている細胞の免疫機能を活性化させる自然免疫機能
- 病原体を不活性化したり、攻撃したり排除する獲得免疫機能
亜鉛不足はウイルスや細菌に対する免疫機能を低下させるのです。
成長障害
子供が亜鉛不足になると成長障害を引き起こすことがあります。
成長の為に必要な「成長ホルモン」や「テストステロン」の分泌が悪くなるからです。
また、亜鉛不足はALP酵素の低下をもたらし低身長の原因となります。
ALPはアルカリフォスファターゼという骨の成長にかかわる酵素だからです。
生殖機能の低下
大人の亜鉛不足は男性の場合、生殖機能の低下をもたらします。
亜鉛は精子やテストステロンの生成に関わっているためです。
亜鉛が不足するとテストステロンが減少して
- 男性更年期障害
- 精力減退
- ED(勃起不全)
など男性機能の低下につながるのです。
亜鉛不足の方におすすめしたいサプリ!
ここまで、亜鉛の摂取方法や摂取できる食品などについて説明しました。
ですが、亜鉛を多く含む食品を食べることができない場合や料理をする時間がない!という方もいるはずです。
そんな方々におすすめのサプリメント3選を紹介します!
滾り 滋養強壮
「滾り 滋養強壮」になります。
「滾り 滋養強壮」は生にんにくの約8倍のアミノ酸、瀬戸内海産牡蠣の亜鉛、ハチミツの40倍のポリフェノールが配合されています。
多くの滋養素材がしっかり配合されているうえに、馬の心臓、すっぽん、マカなどが成分を後押ししています!
そして、今回こちらから購入していただくと、送料無料・初回限定1,058円で購入できます!
通常価格が13,824円のため、かなりお得な価格になっています。
是非、この機会にお試しコースをはじめてみることをおすすめします!!
滾り 滋養強壮の基本情報
| 商品名 | 滾り 滋養強壮 |
| 内容量 | 90粒(1ヶ月分) |
| 定期初回価格(税込) | 1,058円 |
| 定期価格(税込) | 8,618円 |
ミナルギンDX
大正製薬の「ミナルギンDX」になります。
「ミナルギンDX」は、1日4袋(8粒)の摂取で1日分に必要な亜鉛10mgを摂取できます。
他にも、亜鉛と同じような効果を持つ成分が配合されているため、摂取前と摂取後の違いが期待できます。
そして、今回こちらから購入して頂くと、送料無料・50%OFFで購入できます!
気になる方はお試し感覚で購入することをおすすめします!
ミナルギンDXの基本情報
| 商品名 | ミナルギンDX |
| 内容量 | 60粒(1ヶ月分) |
| 定期初回価格(税込) | 3,240円 |
| 定期価格(税込) | 5,832円 |
新時代の亜鉛サプリ「海宝の力」
新時代の亜鉛サプリ「海宝の力」になります。
新時代の亜鉛サプリ「海宝の力」は、瀬戸内海産牡蠣190個分もの亜鉛を凝縮!!
3粒で亜鉛17mgを摂取できます。
そのため、満足度は驚異の92.4%!!
今回こちらから購入していただくと、送料無料・初回限定500円で購入できます!
通常価格4,980円から約90%オフ!
さらに、20日間の返金保証サポートもあるため、安心してお試しできます!
海宝の力の基本情報
| 商品名 | 海宝の力 |
| 内容量 | 90粒(1ヶ月分) |
| 定期初回価格(税込) | 500円 |
| 定期価格(税込) | 5,480円(2袋) |
ベルタ葉酸サプリ

ベルタ葉酸サプリは、葉酸480㎍をはじめ、合計83種類の栄養素を配合しているマルチビタミン葉酸サプリです。
この多種多様な栄養素の中に亜鉛は含まれています。
このサプリは健康を保つために必要な栄養素をバランス良く配合しており、過剰摂取を心配することなく服用できるでしょう。
これらは無添加13種で開発されており、放射能濃度検査や残留農薬試験も実施されています。
さらに、国内GMP認定工場での製造により、品質と安全性が確保されています。
ベルタ葉酸サプリの基本情報
| 商品名 | ベルタ葉酸サプリ |
| 内容量 | 120粒(1ヶ月分) |
| 定期初回価格(税込) | 1,980円 |
| 定期価格(税込) | 3,980円 |
mitas for men

Mitas for Menは、マカや亜鉛、セレンなどの栄養素を配合しています。
これらの成分は、男性の妊活をサポートするために重要な成分です。
また、ビタミンC、ビタミンE、コエンザイムQ10などの成分も配合されています。
医師の監修のもとに製造されており、製品の品質と効果が保証されています。
これらの要素が組み合わさって、Mitas for Menは男性の健康を全面的にサポートする強力なツールとなるでしょう。
mitas for menの基本情報
| 商品名 | mitas for men |
| 内容量 | 60粒(1ヶ月分) |
| 定期初回価格(税込) | 4,298円 |
| 定期価格(税込) | 5,478円 |
vitas

マカや亜鉛、ビタミンC、葉酸など、11種類のビタミンと必要な栄養素を配合しています。
これらの成分は、日々の生活だけでなく、トレーニング時のような多様な場面での栄養補給に最適です。
Vitasは、成分配合量と美味しさを追求しています。
プロテインの味は、キウイ、バナナ、イチゴ、マンゴー、チョコがあり、好みのフレーバーを選べます。
厚生労働大臣が定めた基準値をクリアした、安心安全な栄養機能食品です。
これにより、製品の品質と効果が保証されています。
健康とフィットネスを全面的にサポートする多方面に有用なサプリメントです。
vitasの基本情報
| 商品名 | vitas |
| 内容量 | 120粒(1ヶ月分) |
| 定期初回価格(税込) | 1,984円 |
| 定期価格(税込) | 1,984円 |
亜鉛不足になる原因とその解消法

亜鉛は私たちの体にとって重要なミネラルであり、300以上の酵素反応に関与しています。
しかし、亜鉛不足になると、健康に様々な影響を及ぼします。
この章では、亜鉛不足になる原因とその解消法について詳しく解説します。
亜鉛不足の原因
亜鉛不足の原因は大きく分けて4つあります。
それは、亜鉛の摂取不足、亜鉛の需要増大、亜鉛の吸収不全、亜鉛の過剰排泄です。
特に、亜鉛の需要と供給のバランスがとれていないことが一番多い原因とされています。
成人男性の場合、日本の厚生労働省では1日に11mgの亜鉛を摂取することが推奨されています。
しかし実際の摂取量は平均で9.2mgとなっており、亜鉛不足に陥りやすい状態です。
また、妊婦や授乳中の女性、慢性的に炎症を持つ人、スポーツを行っている人などは通常以上に亜鉛が必要となります。
亜鉛不足の解消法
亜鉛不足を解消するためには、まず亜鉛が豊富に含まれている食べ物を摂取することが重要です。
しかし、亜鉛を過剰に摂取することは避けるべきであり、上限量が決められています。
亜鉛をサプリメントなどで補う場合は、定期的なモニタリングが必要です。
また、亜鉛が吸収されにくくなる疾患や亜鉛が排泄されやすくなる疾患を持つ人は、医療機関に相談することが推奨されています。
スポンサーリンク
亜鉛の食べ物を多く含むメニュー

亜鉛の食べ物を多く含む以下のメニューをご紹介します。
- かきを使ったメニュー
- 煮干しを使ったメニュー
- 豚レバーを使ったメニュー
- 牛肩ロースを使ったメニュー
- 牛もも肉を使ったメニュー
それぞれ3つずつのメニューと簡単な説明を加えました。
かきを使ったメニュー
かきを使ったメニューを以下に3つご紹介します。
【かきのバターホイル焼き】
かき、新玉ねぎ、ほうれん草、パプリカをアルミホイルに包みバターをのせてオーブンで焼けば出来上がりです。
【かきとニンニクの芽のオイスターソース炒め】
かきとニンニクの芽、玉ねぎ、白ネギのオイスター炒めで簡単に料理できます。
【かきと春キャベツの炒めもの】
旬の春キャベツを使って、かきを美味しく頂ける炒めものの料理です。
煮干しを使ったメニュー
煮干しを使ったメニューを以下に3つご紹介します。
【ふきといりこの煮物】
ふきをいりこで煮出した春らしい煮物です。
【いりことじゃがいもの味噌汁】
いりことじゃがいも、玉ねぎ、いんげんを入れた味噌汁です。
【辛子といりこ出汁で野菜炒め】
炒めた野菜に辛子といりこ出汁を加えたピリ辛炒め料理です。
豚レバーを使ったメニュー
豚レバーを使ったメニューを以下に3つご紹介します。
【豚レバーのバター炒め】
バター風味に炒めた豚レバーにキャベツやピーマンなど炒め野菜を合わせた料理です。
【豚レバー唐揚げ 辛味和え】
山椒風味のたれが効いた豚レバーの唐揚げのおつまみです。
【豚レバーとピーマンの甘辛炒め】
簡単焼き肉のタレを使った豚レバーとピーマンの甘辛炒め料理です。
牛肩ロースを使ったメニュー
牛肩ロースを使ったメニューを以下に3つご紹介します。
【レタスとキャベツのすき焼き】
採れたてレタス、キャベツ、春菊と牛肩ロースで新鮮抜群のすき焼きです。
【牛肩ロースステーキ】
ポイントはミートハンマーの叩き過ぎに注意です。
【牛肩ロースと夏野菜のスタミナ炒め】
焼き肉のタレに漬けた牛肩ロースとナスを炒め合わせた夏向けのスタミナ料理です。
牛もも肉を使ったメニュー
牛もも肉を使ったメニューを以下に3つご紹介します。
【牛もも肉の網焼き】
上質の牛もも肉を使って塩コショウしただけの網焼きの簡単料理です。
【牛もも肉の赤ワイントマト煮込み】
トマトの酸味と赤ワインの風味がよく合った味わい深い牛もも肉の煮込み料理です。
【牛もも肉とピーマンで簡単チンジャオロース】
具材は牛もも肉とピーマンだけのシンプル食材で手軽に作れるチンジャオロースです。
スポンサーリンク
亜鉛の食べ物による過剰摂取に注意

日常的な食事からの亜鉛が過剰摂取になることはほとんどありません。
ただし、亜鉛サプリメントの不適切利用や高濃度の亜鉛摂取は健康障害の原因になります。
亜鉛の過剰摂取による健康障害で知られているのは銅欠乏症です。
銅欠乏症の症状には
| 貧血 | 骨異常 |
| 毛髪異常 | 白血球減少 |
| 好中球減少 | 心血管異常 |
| 神経系異常 | 成長障害 |
などがあります。
亜鉛の食事摂取基準量の1日の耐用上限量は以下のように定められています。
- 18歳以上の男性:40~45mg
- 18歳以上の女性:30~35mg
健康障害を生じないようサプリメントなどによる過剰摂取には十分気をつけましょう。
出典:厚生労働省【日本人の食事摂取基準(2020 年版)】
スポンサーリンク
運動する人への亜鉛の推奨摂取量

亜鉛は汗の中に多く含まれています。
また、筋力トレーニングなど身体への負担が大きい運動ほど、亜鉛の消費量は増加します。
- トレーニングやスポーツなどを頻繁に行っている方
- 日常的に発汗量が多い方
上記に該当する方は、亜鉛不足にならないように積極的に摂取するように心がけましょう。
認知症とリハビリの関係について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
認知症のリハビリと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。一般的に知られているのは、手を動かす作業や軽い運動だと思います。ですが他にも刺激法や回想法など多くの種類のリハビリがあります。数多くあるリハビリから効果的なものを見つけるには、[…]
高齢者は亜鉛が不足しがち

65歳以上の亜鉛の摂取推奨量は
- 男性:10~11mg
- 女性:8mg
となっています。
2019年の国立健康・栄養研究所の国民健康・栄養調査データによる高齢者の亜鉛の平均摂取量を見てみましょう。
| 年齢 | 男性の平均摂取量(mg) | 女性の平均摂取量(mg) |
| 60~69歳 | 9.3 | 8.0 |
| 70~79歳 | 9.1 | 8.0 |
| 80歳以上 | 8.3 | 7.2 |
出典:国立健康・栄養研究所【栄養素等摂取量】
60歳以上の平均亜鉛摂取量は
- 男性:8.3~9.3mg
- 女性:7.2~8.0mg
と、高齢者の亜鉛の平均摂取量は推奨量よりも下回っていることがわかります。
女性よりも、特に男性が推奨量よりも大幅に下回っています。
そのため、特に男性は亜鉛を多く含む食べ物を意識した食生活を心がけることが大切です。
スポンサーリンク
亜鉛の食べ物に関するよくある質問

亜鉛の食べ物に関するよくある質問を以下に2つ挙げました。
- 亜鉛の吸収率はビタミンと一緒に摂ると上がりますか?
- 妊娠中・授乳中の亜鉛の推奨摂取量はどのくらいですか?
それぞれの回答をご紹介します。
亜鉛の吸収率はビタミンと一緒に摂ると上がりますか?
亜鉛の吸収率はビタミンCやクエン酸、動物性タンパク質と一緒に摂ることで上がります。
亜鉛の腸管での吸収率は約30%と言われています。
しかも吸収率は年齢とともに下がるといわれているので、吸収率をあげる工夫が必要です。
亜鉛を多く含む肉類や魚介類とビタミンCを多く含む野菜を一緒に摂ることです。
例えば豚レバーの野菜炒めなど亜鉛の吸収を意識したメニューなどがよいでしょう。
妊娠中・授乳中の亜鉛の推奨摂取量はどのくらいですか?
妊娠中・授乳中の亜鉛の1日の推奨摂取量は以下の通りです。
- 18~49歳の推奨摂取量 :8mg
- 妊娠中の亜鉛の推奨付加量 :2mg(合計推奨摂取量:10mg)
- 授乳中の亜鉛の推奨付加量 :4mg(合計推奨摂取量:12mg)
妊娠中・授乳中の方にとって亜鉛は胎児や乳児の発育や成長に欠かせません。
亜鉛が不足すると成長障害を引き起こす原因にもなります。
通常時よりもより意識して亜鉛を摂取する必要があります。
出典:厚生労働省【日本人の食事摂取基準(2020 年版)】
スポンサーリンク
亜鉛が豊富な食べ物まとめ
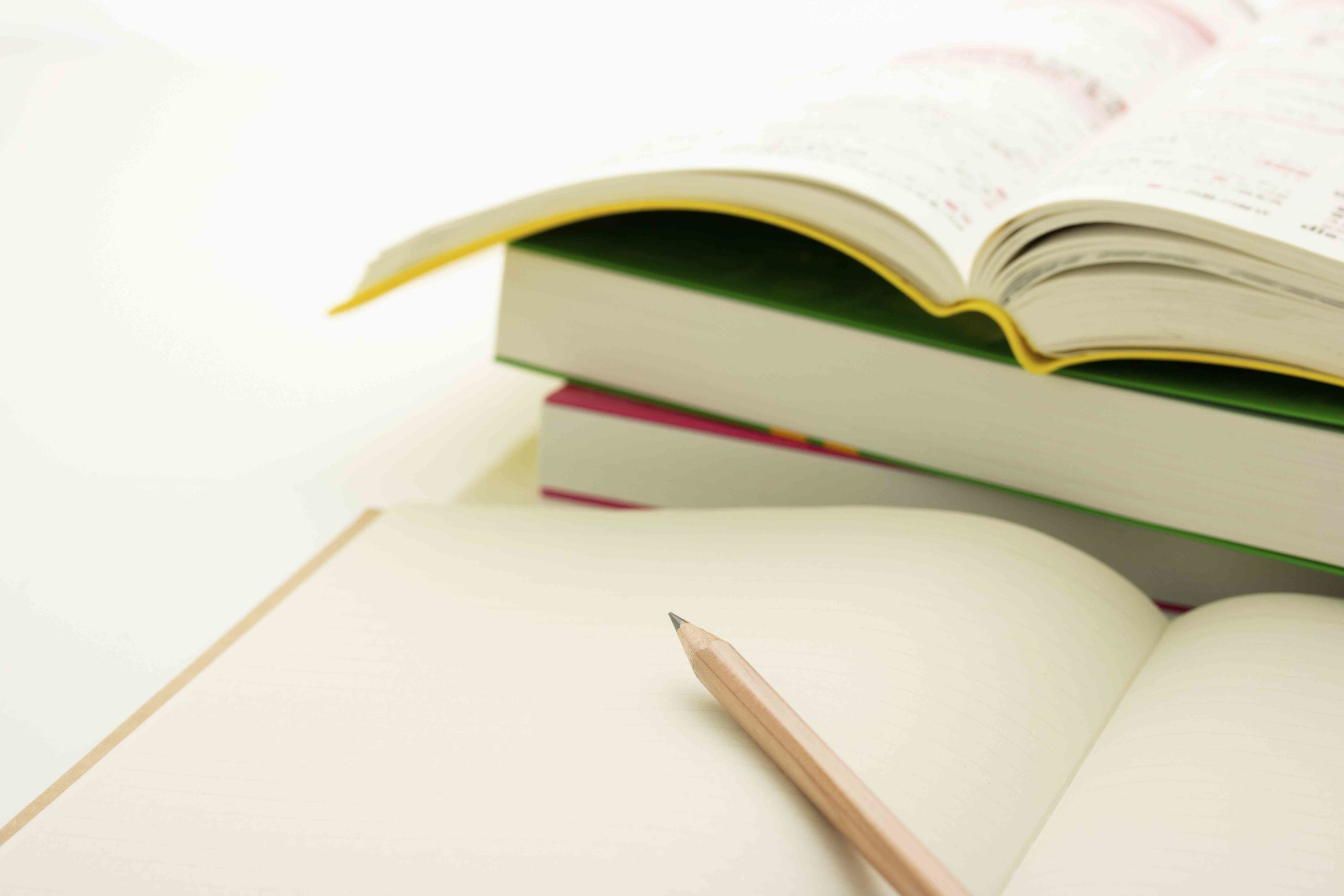
ここまで、亜鉛の働き、亜鉛が多く含まれる食べ物、亜鉛の身体への影響などを中心にお伝えしてきました。
亜鉛の必要性をまとめると以下の通りです。
- 亜鉛は約300種類以上の酵素の構成要素として重要な働きを担っている栄養素である
- 亜鉛を手軽に効率よくとるにはサプリメントなどを活用する
- 亜鉛の1日の摂取量は男性:10~11mg、女性:8mgほどといわれている
- 亜鉛不足による症状には皮膚炎、味覚異常、貧血、免疫力の低下などがある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります