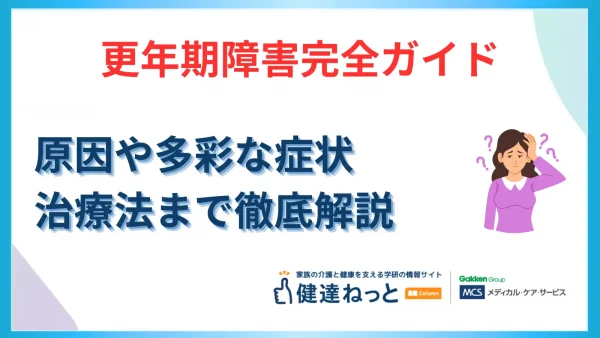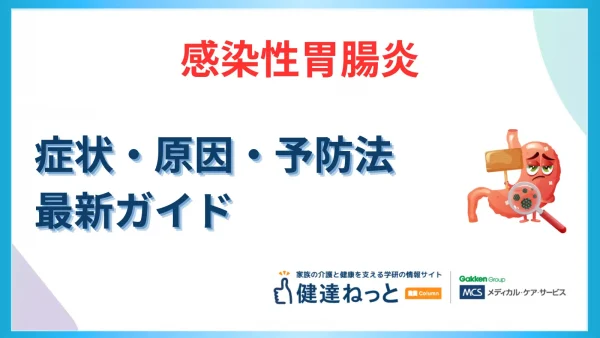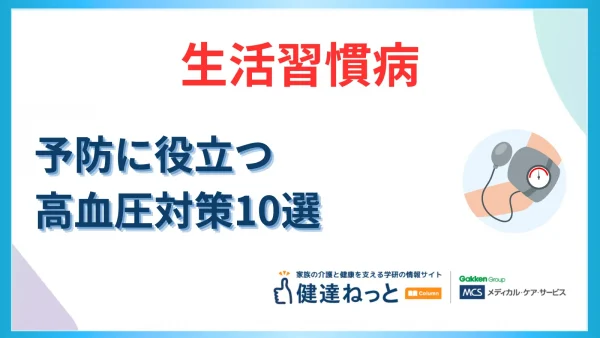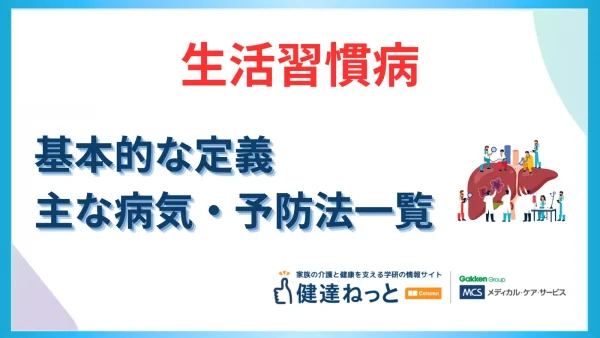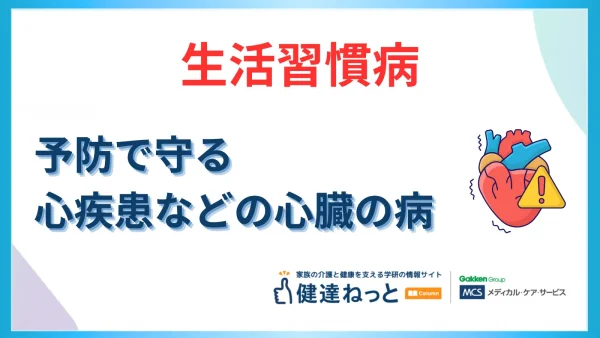急に動悸がすると「心臓病なのでは?」と心配になるものです。
しかし実は、動悸は更年期が原因で起こることもあります。
更年期の動悸とはどのようなものなのでしょうか。
本記事では、更年期の動悸について以下の点を中心にご紹介します。
- 更年期の動悸の特徴
- 更年期の動悸の原因
- 更年期の動悸の対処法
更年期の動悸について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
更年期で起こる動悸とは

更年期にはさまざまな症状が出やすくなります。
代表的なのが動悸です。
ちなみに更年期とは、閉経を挟んで前後10年の期間を指します。
更年期が原因であらわれる症状は、まとめて更年期障害と呼ばれています。
ここでは、
- 更年期の動悸の特徴
- 動悸を引き起こすホルモンの変動
その生理的な背景とともに解説します。
更年期の動悸がどのようなものか、その具体的な特徴を理解することから始めましょう。
更年期の動悸の特徴
更年期の動悸は突然に感じる心拍の速さや不規則さが特徴です。
これは、閉経に向かう過程でエストロゲンとプロゲステロンのレベルが不安定になるため生じます。
具体的には、心臓が一時的に速く打つことで不安やパニックを感じることがあります。
また、これらの症状は安静時にも、活動中にも現れることがあり、日常生活に影響を与えることも少なくありません。
動悸を引き起こすホルモンの変動
更年期に入ると、女性ホルモンであるエストロゲンの減少が主な原因となって自律神経のバランスが崩れ、これが心拍数の増加に直接的に影響を与えます。
エストロゲンは心血管系の機能を正常に保つ役割も担っており、その減少により心臓の働きに変化が生じるのです。
これによって、普段とは異なる心拍感を体験することになります。
自律神経と動悸の関係について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
自律神経失調症の症状の1つに、動悸があります。誰でも緊張したり走ったりすると心臓がドキドキします。しかし激しい運動をしたり、興奮したりしたわけでもないのに動悸が起こると不安になりますよね。そこで本記事では自律神経失調症の[…]
スポンサーリンク
更年期の動悸の症状

更年期には動悸などの症状があらわれやすくなります。
更年期の動悸の特徴をご紹介します。
更年期の方で「最近胸がドキドキする…」という方は、ぜひ次のような事柄に心当たりがないかぜひ確かめてみてください。
動悸の起こり方
更年期の動悸は突然始まるのが特徴的です。
たとえば次のような心当たりがある場合、動悸の原因として更年期が考えられます。
- 激しい運動をしていないのに胸がドキドキする
- じっとしているときに胸がドキドキする
- 夜、寝ているときに胸がドキドキする
- 突然脈が速く・大きくなる
更年期の動悸のあらわれ方は個人差があります。
たとえば、緊張したときやストレスを感じたときに動悸が始まるケースもみられます。
動悸の持続時間
更年期の動悸の持続時間は個人差があるため、一概にはいえません。
たとえば1~2回で治まる場合もあれば、30分以上続く場合もあります。
もし動悸が30分~1時間以上続く場合は、更年期障害以外の病気の可能性があります。
あるいは、安静にしても治まらない場合も更年期障害以外の原因が疑われます。
代表的なのは心筋梗塞です。
動悸の症状だけでは、原因が更年期なのか心臓の病気なのか判断できないのが実情です。
少しでも体調に不安がある場合は、すぐに病院を受診しましょう。
脈の状態
更年期が原因の動悸は、脈に異常がないことが多いです。
しかし個人差があるため、一概にはいえません。
動悸と一緒に起こりやすい脈の異常には次があります。
- 脈が速い(100回以上/1分)
- 脈が遅い(50回以下/1分)
- 脈が乱れる
- 脈が1拍飛ぶ
動悸とあわせて脈に異常がある場合は、心疾患や甲状腺の病気が疑われます。
もし動悸以外に気になる症状がある場合は、病院を受診してください。
更年期の動悸が起こる原因

更年期の動悸の原因は、閉経による女性ホルモン(エストロゲン)の減少です。
より具体的にいえば、女性ホルモンの減少によって自律神経が乱れることで動悸が起こりやすくなります。
自律神経とは内蔵の働き・心拍・血圧・ホルモン分泌などをコントロールする器官です。
自律神経は、女性ホルモンの分泌の指令を出す器官と同じ脳分野に存在します。
卵巣が寿命を迎えて閉経すると、卵巣からはエストロゲンが分泌されなくなります。
しかし閉経直後は、脳は卵巣が寿命を迎えたことを認識できません。
そのため、脳は卵巣に「もっとエストロゲンを出せ」と命令します。
いわば脳が混乱してしまうのです。
すると、女性ホルモンの分泌元と同じ分野にある自律神経も混乱しやすくなります。
自律神経が乱れると、心拍や血圧の調節がうまくいかなくなります、
結果として、心臓が異常にドキドキする症状があらわれやすくなるのです。
ちなみに、更年期には動悸以外の症状が複数あらわれることも多いです。
動悸以外の更年期の症状も、閉経による自律神経の乱れが原因とされています。
更年期障害の原因について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
ホットフラッシュの対策について更年期に多い症状の1つがホットフラッシュです。顔が火照ったり、汗が止まらなくなったりします。ホットフラッシュを止めるには、どのような対策をしたらよいのでしょうか?また、ホットフラッシュの予防対策に[…]
更年期の動悸の対処方法

更年期の動悸がひどい場合は、病院で検査・治療を受けるのがおすすめです。
主な診療科・検査方法・治療方法をご紹介します。
受診科
更年期の動悸で受診する場合、診療科は婦人科が適当です。
最寄りにあるのであれば、更年期外来を訪ねてもよいでしょう。
あるいは、呼吸器内科・循環器内科を受診してもかまいません。
検査方法
更年期の動悸の主な検査方法は次の通りです。
具体的な検査項目は病院によって異なります。
- 問診
- 血液検査
- 心電図
- 心エコー
- 甲状腺ホルモン検査
- 胸部レントゲン検査
検査の主な目的は、更年期以外の病気をみつけることです。
たとえばレントゲンで心臓の異常がみつかった場合、動悸の原因として心疾患が疑われます。
各種検査で特に異常がない場合は、更年期障害の可能性が高まります。
薬物療法
動悸の原因が更年期と診断された場合は、治療に移行することが一般的です。
更年期障害の代表的な治療法は薬物療法です。
具体的には次のような治療方法・薬剤が検討されます。
- ホルモン補充療法(HRT)
- 抗うつ剤
- 抗不安薬
- 睡眠導入剤
ホルモン補充療法は、減少した女性ホルモンを薬で補給する方法です。
抗うつ剤・抗不安薬は、イライラ・不安などの精神症状が強い場合に用いられることが一般的です。
不眠症状がある場合は、睡眠導入剤が出されることもあります。
実際にどの治療法が選択されるかは、個人の状態や医師の判断によって異なります。
漢方薬
更年期障害の治療では漢方薬が処方されることもあります。
代表的な種類をご紹介します。
桂枝茯苓丸
桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)は女性特有の不調に効果があるとされる漢方薬です。
血の巡りをよくして、動悸・冷え・生理痛などの症状を軽減する効果が期待できます。
当帰芍薬散
当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)も更年期障害の治療によく用いられます。
卵巣機能を高める効果があり、女性特有の不調の軽減を期待できます。
加味逍遥散
加味逍遙散(カミショウヨウサン)は、身体の巡りを整える漢方薬です。
いわゆる「血の道症」の治療薬としても有名です。
期待できる効果は、イライラや不安を鎮めて精神を安定させることです。
柴胡加竜骨牡蛎湯
柴胡加竜骨牡蛎湯(サイコカリュウコツボレイトウ)は、更年期のイライラ・不安などの症状に有効とされます。
更年期による動悸のほか、のぼせ・疲労感の改善効果も期待できます。
黄連解毒湯
黄連解毒湯(オウレンゲドクトウ)は自律神経を整えて心身をリラックスさせる効果があるとされます。
動悸のほか、更年期が原因のイライラ・のぼせの改善も期待できます。
更年期の検査方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
更年期にさしかかると、さまざまな体調不良に悩まされます。更年期の体調不良は放置すると症状がひどくなる可能性があります。更年期における体調不良の症状や原因は何でしょうか?更年期の検査にはどのようなものがあるのでしょうか?[…]
更年期の動悸に効くツボ

更年期における動悸は多くの方が経験する症状の一つです。
ここでは、更年期の動悸を和らげるとされる、
- 心経ツボ
- 神門ツボ
- 内関ツボ
の位置と効果について表で解説します。
| ツボの名称 | 位置 | 効果 |
| 心経ツボ | 腕の内側、肘のくぼみから指三本分下の部分 | 動悸の緩和、心臓の健康に効果的 |
| 神門ツボ | 手首の内側、小指の骨の端のすぐ下 | 心の安定、緊張緩和、不安やストレスによる動悸の改善に効果 |
| 内関ツボ | 手首の内側、腕の中央から指三本分上 | 精神的ストレスによる動悸の改善、心身のリラックス促進 |
ツボを押す時の注意点
更年期の動悸に対するツボ押しは非常に効果的とされる手法ですが、安全かつ効果的に行うためにはいくつかの注意点を守る必要があります。
以下は、ツボを押す際の主な注意点です。
適切な圧力を使用する
ツボを押すときは、強すぎず、しかし十分な圧力をかけることが大切です。
痛みを感じるほど強く押すと逆効果になることがあります。
心地よい圧力を心がけ、痛みがある場合は圧力を少し緩めてください。
正しい位置を把握する
ツボの位置が正確でないと、期待する効果が得られないことがあります。
ツボの位置を事前によく確認し、必要であれば専門の指導を受けることも検討しましょう。
リラックスした状態で行う
ツボ押しはリラックスした状態で行うことが最も効果的とされます。
緊張していると筋肉が硬くなり、ツボ押しの効果が得にくくなります。
深呼吸をしながら、落ち着いて行うようにしましょう。
自律神経を整えるツボに興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
私たちが生きていく中で自律神経は重要な役割を果たしています。しかし、ストレスや生活習慣の乱れなどにより自律神経が乱れると、体調が悪くなることがあります。自律神経が乱れた際に、多くの人はストレッチやマッサージで血行を促し乱れを整えたり、[…]
動悸が起こる病気との見極め方

動悸は更年期以外の病気でも広くみられる症状です。
もし更年期の動悸を「更年期障害だろう…」と自己判断すると、重大な病気を見逃すおそれもあります。
ここからは、動悸が起こりやすい病気と特徴をご紹介します。
もし動悸が起こった場合は、今回ご紹介するような症状・特徴を伴っていないかチェックしてみてください。
動悸の他に気になる症状がある場合は、すぐに病院を受診しましょう。
心臓疾患
動悸が起こりやすい病気の1つが心臓疾患です。
代表的な心疾患は次の通りです。
| 心不全 | 心臓弁膜症 |
| 不整脈 | 大動脈弁狭窄症 |
| 心筋症 | 狭心症 |
| 虚血性心疾患 | 心房細動 |
| 僧帽弁閉鎖不全症 | 心筋梗塞 |
心疾患の場合、動悸とあわせて次のような症状が出ることが多いです。
- 激しい胸・背中の痛み
- めまい
- 冷や汗
- 脈の乱れ(早い・遅い・飛ぶ)
- 呼吸困難
- 失神
もし心当たりの症状がある場合は心疾患を疑い、すぐに救急外科や循環器内科を受診してください。
起立性調節障害
起立性調節障害では、立ち上がったときに動悸・めまいなどの症状があらわれます。
主な症状は次の通りです。
| 立っていると気分が悪くなり、ひどい場合は倒れる |
| 立ちくらみ・めまい |
| 朝、なかなか起き上がれない |
| 頭痛 |
| 体がだるい・全身倦怠感 |
| 入浴時・いやなことを見聞きすると気持ちが悪くなる |
| 食欲不振・腹痛 |
| 少し動くと動悸・息切れがする |
| 乗り物に酔いやすい |
起立性調節障害の原因は、自律神経の乱れによって上半身に血液が届かなくなることです。
一時的にですが心臓や脳が酸欠になるため、動悸・めまいなどの症状があらわれやすくなります。
鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は、鉄分不足によって起こる貧血です。
具体的には、鉄分不足によって赤血球が減った状態を指します。
赤血球は血液に乗って全身に酸素を届ける細胞です。
赤血球が少なくなると酸素の運搬が滞るため、全身が酸欠になります。
貧血の主な症状は次の通りです。
- 動悸
- 息切れ
- 疲労感、倦怠感
- 顔面蒼白
- つめが反る・割れやすい
- 味覚障害
症状だけでは更年期と鉄欠乏性貧血を見極めるのは困難です。
診断には血液検査が必要です。
高血圧症
高血圧症とは、高い血圧が維持される状態です。
具体的には、血圧が140mmHg/90mmHg以上の状態が続くと高血圧症と診断されます。
高血圧状態が続くと、心臓が血液を送り出す力が強まります。
いつもより心拍が大きくなりやすいため、「動悸がしている」と感じることがあります。
高血圧症の動悸以外の主な症状は次の通りです。
- 胸痛
- 息切れ
- 不整脈
高血圧症は自覚症状があらわれないことも多いです。
そのため、動悸がしても高血圧と気づけないこともあります。
更年期には高血圧を合併しやすくなります。
更年期高血圧は、些細なことで血圧が変動しやすいのが特徴です。
また、更年期高血圧は不安感・めまい・頭痛を伴うことが多いです。
動悸のほかに血圧の変動・なんらかの不調を感じる場合は、一度病院で検査するのがおすすめです。
バセドウ病
バセドウ病は甲状腺機能亢進症の原因となる疾病の1つです。
甲状腺機能亢進症を発症すると、甲状腺ホルモンの分泌量が増加します。
甲状腺ホルモンには、新陳代謝を盛んにする作用があります。
心拍数も増えるため、心臓がドキドキするのを感じたり、動悸が起こったりしやすくなります。
バセドウ病では動悸以外にも次のような症状があらわれます。
- 異常な食欲がある
- 体重が減る
- 疲れやすい
- 精神的に不安定になりやすい
- 眼球突出
バセドウ病の症状は更年期障害や自律神経失調症とよく似ています。
そのため、症状だけでは見分けがつきにくいのが実情です。
もしバセドウ病を疑う症状がある場合は、病院で検査を受けましょう。
バセドウ病は心疾患に発展するおそれがあるため、放置するのはやめましょう。
不安障害
不安障害とは、不安が原因で心身にさまざまな症状が出る状態です。
不安障害には次のような種類があります。
- 全般性不安障害
- 社会不安障害
- パニック障害
- 過換気症候群
- 限局性恐怖症
不安を感じることは誰にでもあるものです。
たとえば大事な会議の前に心臓がドキドキしたり、お腹が痛くなったりする経験をお持ちの方は多いでしょう。
一方、不安障害では些細なこと・根拠のないことに過度の不安・緊張を感じます。
通常であれば、不安の種が解消されれば不安・緊張はほぐれるものです。
しかし不安障害では、根拠のない不安・緊張が長期間続くこともあります。
不安・緊張は自律神経のリズムを乱す原因です。
自律神経が大きく乱れると、動悸・息切れ・吐き気などの症状があらわれやすくなります。
(出典:厚生労働省【不安障害|こころの病気について知る】)
(出典:厚生労働省【パニック障害・不安障害|こころの病気を知る|メンタルヘルス|厚生労働省】)
更年期の動悸に関する意識調査
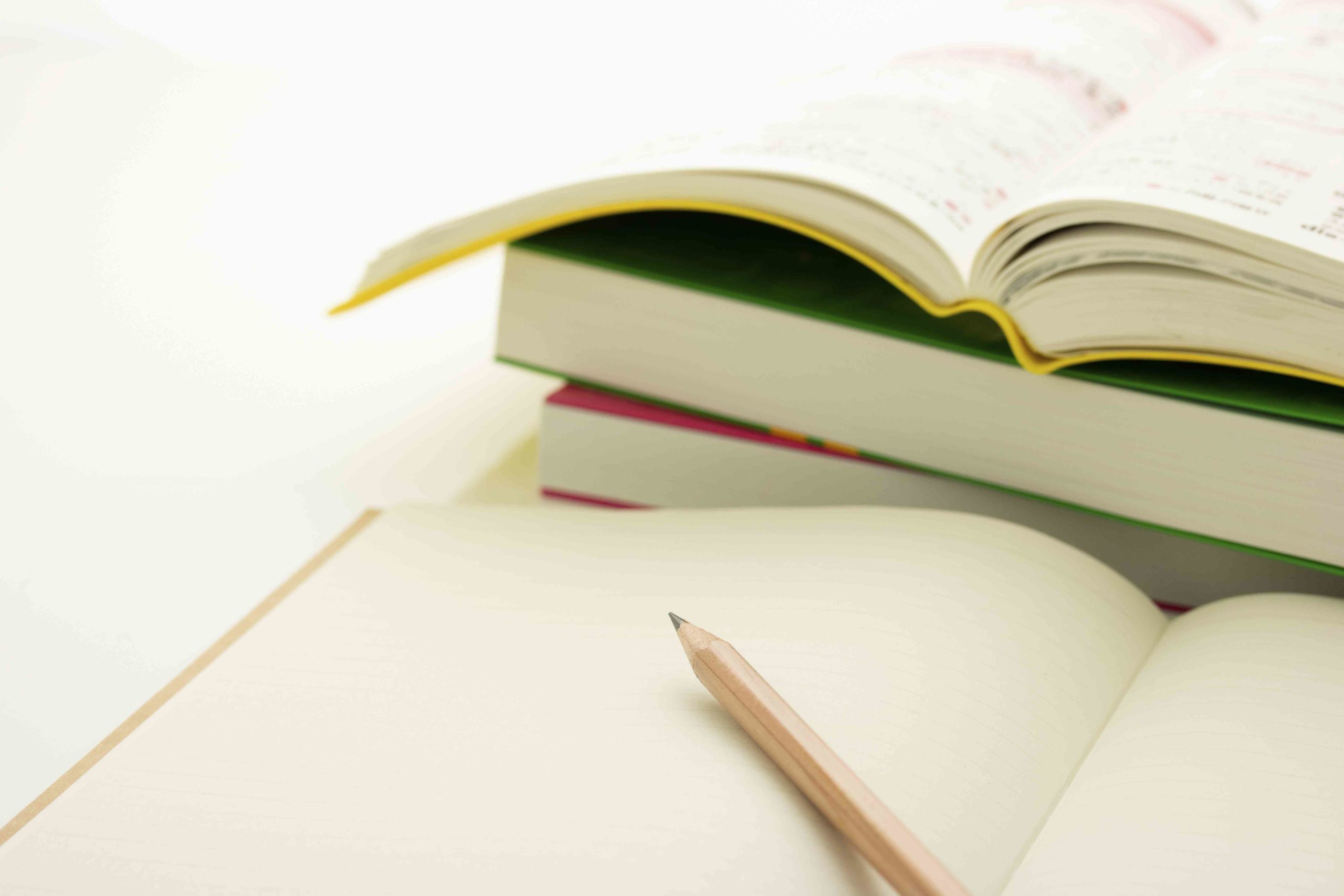
厚生労働省の調査結果を参照します。
20代~60代の女性のうち、更年期による動悸がある方の各年代の割合は次の通りになりました。
【女性の年代別 更年期症状(息切れ、動悸がする):単数回答】
| 症状が強い | 症状の程度は中くらい | 症状の程度は弱い | 症状が無い | |
| 20~29歳 | 3.4% | 13.1% | 18.2% | 65.4% |
| 30~39歳 | 5.5% | 12.2% | 17.7% | 64.7% |
| 40~49歳 | 3.5% | 10.8% | 20.7% | 65.0% |
| 50~59歳 | 3.8% | 12.6% | 25.6% | 58.1% |
| 60~69歳 | 4.6% | 5.1% | 23.5% | 66.8% |
症状が無いと答えた方の割合が最も少ないのは、50代の方です。
つまり、動悸の症状が最も出やすいのは50代であることが分かります。
50代の動悸の程度を強い・中くらい・弱いで分けると、最も割合が大きいのは弱でした。
50代では動悸を感じる方の割合は多いものの、症状自体はさほど深刻でないことが分かります。
急に動悸を感じると心臓病を疑いがちです。
更年期には動悸が起こりやすいことを認識し、過度な心配は抱かないようにしましょう。
「心臓病かも」という過度な不安はストレスの原因となります。
ストレスは自律神経を乱しやすいため、動悸症状がかえって悪化するおそれがあります。
ただし、中には本当に心疾患が原因で動悸がしている場合もあります。
頻繁に動悸がする場合・症状の持続時間が長い場合は、一度病院を受診しましょう。
動悸以外に胸痛・冷や汗・失神などの症状がある場合も、病院で検査を受けてください。
(出典:厚生労働省【「更年期症状・障害に関する意識調査」 基本集計結果 (2022 年7月 26 日)】)
ストレスが原因の動悸の対処法に興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
動悸とは、心臓の拍動を感じる状態のことです。ストレスが動悸の原因になることもあります。そもそも動悸を感じたときはどのように対処すればよいのでしょうか?本記事ではストレスによる動悸と対処法について以下の点を中心にご紹介しま[…]
スポンサーリンク
更年期の動悸まとめ

ここまで更年期の動悸についてお伝えしてきました。
更年期の動悸の要点を以下にまとめます。
- 更年期の動悸の特徴は突然始まり、脈の乱れはないことが多い
- 更年期の動悸の原因は、女性ホルモンの減少によって自律神経が乱れること
- 更年期の動悸の対処法は、病院での治療・深呼吸・リラックスなど
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。