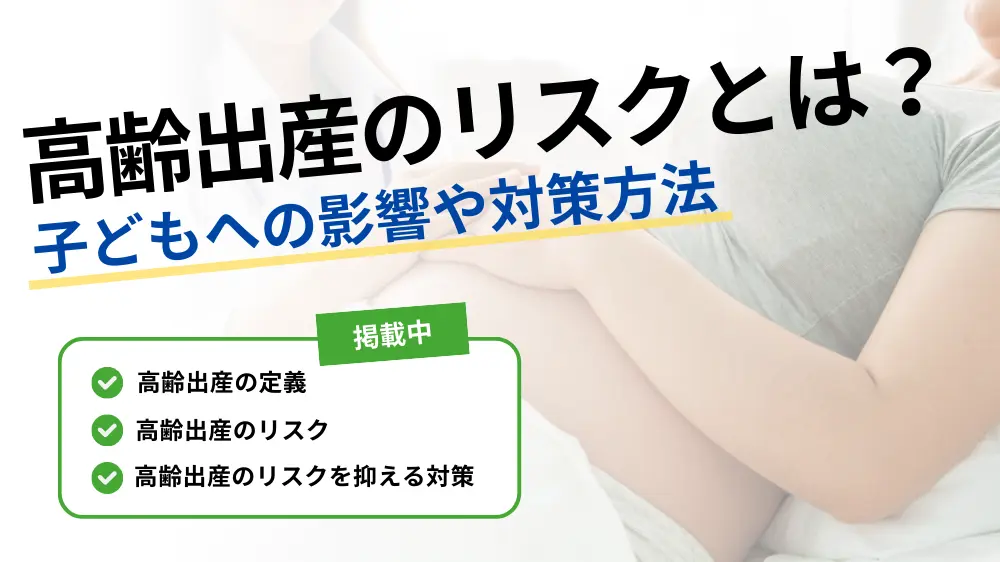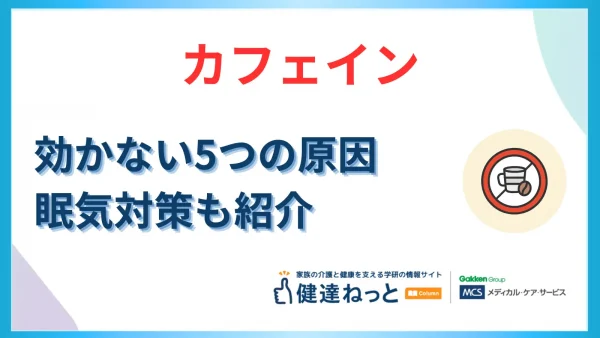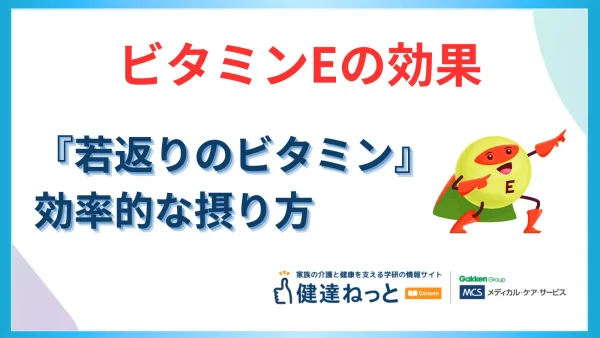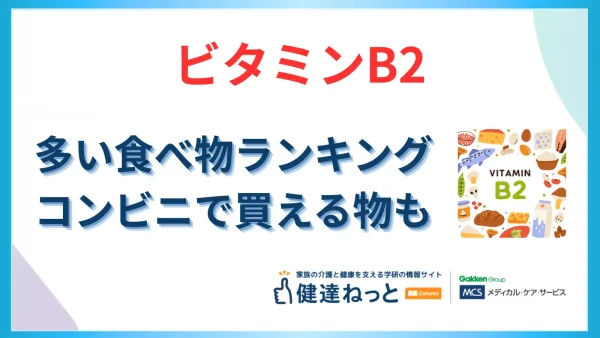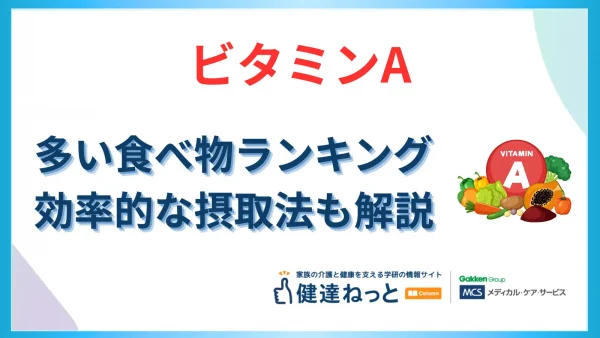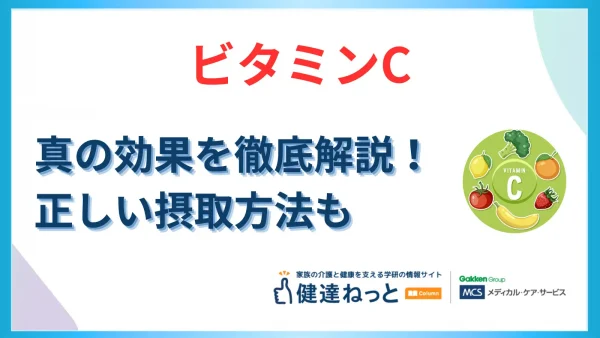「高齢出産は子どもに障害が起こりやすいって本当?」
「子どもに障害が起こらないよう対策できないかな」
高齢出産で悩む人の中には、このように考える人もいるのではないでしょうか。
高齢出産では子どもに障害が起こりやすく、健康な赤ちゃんを生むためには生活習慣などの見直しが大切になります。
本記事では、高齢出産と子どもの障害について以下の点を中心に解説します。
- 高齢出産で子どもに障害が起こりやすい理由
- 高齢出産で健康な子どもを生むための予防策
- 子どもに疾患・障害の有無を調べる方法
高齢出産と子どもの障害の関係性などにご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
高齢出産の定義と子どもが障害を持つ確率

まずはじめに、高齢出産の定義と子どもが障害を持つ確率についてご紹介します。
一般的に、高齢出産とは35歳以上の女性が初めて出産することを指します。
35歳以上での出産は20代での出産と比べて、子どもが障害を持つ確率が上がることがわかっています。
知的障害や精神障害などの症状が見られるダウン症候群の発症率は、母親が20歳のときの出産では約1/1667、40歳のときの出産では約1/106の確率とされています。
その他にも、発達障害の一種である自閉症スペクトラム障害(ASD)は、父母の年齢が上がるにつれ、発症のリスクが高まります。
様々な発症率のデータから、母親の出産年齢が子どもの障害の発症に影響を及ぼすことがわかります。
高齢出産の傾向やリスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
「高齢出産って何歳から?」「高齢出産による子どもの体への影響が心配」30代で子どもを産もうと考えている、あるいは出産を控えている30代〜40代の方の中には、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。国内[…]
スポンサーリンク
高齢出産で子どもに障害が起こりやすい原因

ここでは、高齢出産で子どもに障害が起こりやすい原因をご紹介します。
高齢出産で子どもに障害が起こりやすい原因は、加齢に伴い、卵子の質が低下するからです。
卵子の質の低下は以下のような影響を及ぼすため、子どもに障害が起こりやすいとされています。
- 卵子がダメージを受ける
- 卵子の染色体異常が増える
また、卵子が老化することによって、妊娠率の低下を招き、流産率も上がるため、高齢出産は母子ともに影響があることは知っておきましょう。
子どもにあらわれる障害と種類

ここでは、子どもにあらわれる障害と種類について、以下の3つに分けてご紹介します。
- 先天性の疾患
- 発達障害
- 知的障害
先天性の疾患
子どもにあらわれる障害と種類の1つ目は「先天性の疾患」です。
先天性の疾患とは、生まれつき身体の形や臓器などの機能に異常がある状態を指します。
症状の度合いは、生活に支障がない軽度のものから生まれてすぐに医療が必要な重度のものまで人によって様々です。
また、先天性の疾患の原因は、染色体や遺伝子の異常の他、感染症やタバコ、アルコールの影響など多岐にわたります。
先天性の主な疾患には、以下の3つがあります。
- ダウン症候群(染色体異常の疾患)
- フェニルケトン尿症(単一遺伝子異常の疾患)
- 先天性風疹症候群(感染症によって引き起こされる疾患)
発達障害
2つ目は「発達障害」です。
発達障害とは、生まれつき脳機能の発達に偏りがあることで、言語や行動に特性が見られる障害のことです。
主なものとしては、以下の5つの障害があります。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
- チック症
- 吃音
特性があらわれる年齢は子どもによって様々で、2歳で特性があらわれるケースもあれば、就学して集団生活に馴染めないことで気づかれるケースもあります。
発達障害は特性のため完治は難しいですが、特性の度合いなどによって、薬物療法による対処療法や生活療法を通じて特性を和らげる方法など、子どもに応じた治療を行います。
知的障害
3つ目は「知的障害」です。
知的障害とは、おおむね18歳未満の発達期に知的機能の障害があらわれ、日常生活や社会生活を送る中で不自由が生じることを指します。
知的障害の症状や特徴は、例えば以下の3つが挙げられます。
- おつりのやりとりなど日常生活で計算が苦手
- 計画立てや、優先順位をつけられない
- 会話の中で相手の意図を理解することが難しい
知的障害の重要度は軽度/中度/重度/最重度の4つに分けられ、治療には療育と環境の調整が行われます。
高齢出産で健康な子どもを生むための予防策

ここでは、高齢出産で健康な子どもを生むための予防策を8つご紹介します。
- 葉酸を積極的に摂取する
- 食事改善を行う
- ストレス管理を行う
- 十分な休息をとる
- 適度な運動で体力をつける
- 肥満にならないよう体重管理を行う
- 妊婦健診で母子の健康状態をチェックする
- 出生前検査で子どもの病気の可能性を知る
葉酸を積極的に摂取する
高齢出産で健康な子どもを生むための予防策の1つ目は「葉酸を積極的に摂取すること」です。
葉酸とは赤ちゃんの脳や神経が形成されていくときに必要な栄養素で、妊娠初期は特に不足しがちです。
妊娠中に葉酸が不足すると、赤ちゃんに神経管閉鎖障害や無脳症を引き起こすリスクが高まるため、日頃から葉酸を含む食材を献立に取り入れるようにしましょう。
葉酸を多く含む食材は、以下の5つです。
- ブロッコリー
- アボカド
- さつまいも
- いちご
- 納豆
また、食事だけでは赤ちゃんに必要な量の葉酸を摂取することは難しいため、不足分はサプリメントで補うなどの対策も必要です。
妊娠前や妊娠初期に摂取すべきサプリについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
妊娠は女性の体に大きな変化をもたらし、その期間中に適切な栄養素を摂取することが非常に重要です。サプリメントは、必要な栄養素を効率的に摂取する手段として、多くの妊婦にとって欠かせない存在となっています。しかし、どのサプリメントを選[…]
食事改善を行う
2つ目は「食事改善を行うこと」です。
赤ちゃんに必要な栄養が不足すると、低出生体重児になる恐れがあります。
低出生体重児は成人後に、肥満などの生活習慣病のリスクが高まるとされており、赤ちゃんの将来にまで影響を及ぼします。
そのため、コンビニ弁当などの出来合いの食事はなるべく避け、自炊による栄養バランスの整った3度の食事を心掛けるようにしましょう。
また、塩分の摂り過ぎにも注意してください。
塩分の取りすぎは、妊婦の体重増加や妊娠高血圧症候群を引き起こし、赤ちゃんに発育不全などの悪影響を及ぼします。
栄養バランスの取れた食事について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
栄養バランスは健康のためには欠かせません。偏ることで重大な病気につながることもある栄養バランスですが、何をどれくらい摂取すればよいのでしょうか?今回、栄養バランスについてご紹介した上で、その必要栄養素や摂取目安についてもご紹介し[…]
ストレス管理を行う
3つ目は「ストレス管理を行うこと」です。
妊娠中にストレスを感じると、赤ちゃんに様々な影響を及ぼすとされています。
- 赤ちゃんの発育不全や低出生体重児のリスクが高まる
- 赤ちゃんに神経機能の障害を引き起こす可能性がある
- 交感神経が活発になると切迫早産につながる
これらのリスクを抑えるためにも、妊娠中は職場や仕事などのストレス要因を遠ざけたり、リラックスして映画鑑賞を楽しんだりするなど、ストレス管理を徹底しましょう。
ストレス解消に役立つおすすめグッズに興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
十分な休息をとる
4つ目は「十分な休息をとること」です。
妊娠中は免疫力が低下する時期のため、この時期に感染症にかかるとお腹の赤ちゃんにまで感染する可能性があります。
疲労が溜まるとさらなる免疫力低下を招くため、仕事や家事は無理をせず、疲労を感じたら休むようにしましょう。
また、妊娠中に休息を取るポイントは以下の3つです。
- 8時間程度の睡眠を心がける
- つわりで寝つきが悪いときは、日中に睡眠をとる
- 楽な姿勢で何度も休憩をとる
休息をとるには、同僚や家族の配慮・サポートも必要なため、周りに協力を仰ぐようにしてください。
適度な運動で体力をつける
5つ目は「適度な運動で体力をつけること」です。
高齢での出産は、若いときの出産と比べて体力がないため、出産時にいきむ力が弱くなり、分娩時間が長引く恐れがあります。
また、出産後は出産の疲れを残したまま育児を行うことになるため、相当の体力を使います。
出産や育児に備えるためにも、適度な運動で体力をつけておくことが大切です。
妊娠初期は母子ともに不安定な時期のため、運動は避けた方が良いですが、安定期(妊娠中期)以降は激しい運動でなければ問題ありません。
妊娠中のウォーキングは、1日30分を週5回行うことが推奨されています。
運動の習慣がない人は、まずは週1回から始めてみましょう。
肥満にならないよう体重管理を行う
6つ目は「肥満にならないよう体重管理を行うこと」です。
母親が肥満になることで、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症のリスクが高まります。
これらの合併症は、お腹の赤ちゃんにも影響があり、発育不全や形態異常を引き起こします。
このような事態を避けるためにも、肥満にならないよう体重管理はしっかり行うべきでしょう。
体重管理としてアプリやノートに体重の記録をつけ、急激な増減がないか確認してください。
一週間に300~500gほどの増加が目安ですが、つわりなどの健康状態によって個人差があるので、不安な人は医師に相談しましょう。
妊婦健診で母子の健康状態をチェックする
7つ目は「妊婦健診で母子の健康状態をチェックすること」です。
妊婦検査では、母親と赤ちゃんの健康状態を定期的にチェックします。
妊婦検査では主に以下の検査が行われ、赤ちゃんの発育に問題ないかわかります。
- 尿検査
- 血液検査
- 腹囲や子宮底の測定
- 体重測定
- 超音波(エコー)検査
- 性器クラミジア検査
- 子宮頸がん検診
もし、妊婦健診で赤ちゃんに異常が見られたときは、より精度の高い出生前検査を行い、診断を受けることも視野に入れましょう。
より精度の高い診断結果を得ることで、分娩の準備や出生後の治療について専門医と相談することが可能になります。
出生前検査で子どもの病気の可能性を知る
8つ目は「出生前検査で子どもの病気の可能性を知ること」です。
出生前検査では、妊婦健診よりも精密な検査を行えるため、障害や疾患の可能性をくわしく調べることが可能です。
出生前検査は、すべての障害や疾患を把握できるわけではありませんが、ダウン症候群など特定の疾患に対しては精度が高く、事前に把握することで以下のメリットが得られます。
- 子どもを受け入れる準備を整えられる
- 出生後の療養計画を立てられる
- 子どもに必要な支援を事前に把握できる
検査費用が高いことはデメリットですが、赤ちゃんの状態がくわしく分かるので、興味のある人は医師やパートナーに相談してみましょう。
子どもの疾患・障害の有無を調べる方法

最後に、子どもの疾患・障害の有無を調べる方法について、以下の3つをご紹介します。
- 出生前検査
- 発達検査
- 知能検査
出生前検査
子どもに疾患・障害の有無を調べる方法の1つ目は「出生前検査」です。
出生前検査の種類には主に以下の5つがあり、調べ方や診断可能な疾患も様々です。
- 超音波(エコー)検査
- NIPT(新型出生前診断)
- 母体血清マーカー検査
- 絨毛検査
- 羊水検査
検査を受けられる施設は限られており、検査を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。
希望者全員が受けられる検査ではないため、詳細は検査を実施している専門機関に相談した方が良いでしょう。
発達検査
2つ目は「発達検査」です。
発達検査とは、子どもの心身の発達状態を調べる検査のことで、運動や言語など、領域別に状態を測定します。
発達検査単体では、発達障害の診断をすることはなく、問診や行動観察などの様々な要素から総合的に判断します。
子どもに発達検査を受けさせたい場合は、小児精神科や発達外来などの医療機関を受診しますが、自治体によっては、発達障害者支援センターなどの専用窓口を設けていることもあります。
お近くの専門機関がわからない場合は、自治体に相談してみましょう。
高齢出産と発達障害の関わりについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
「高齢出産による発達障害のリスクが気になる」「高齢出産による発達障害のリスクを軽減するために、どのような対策を取ればいいのか知りたい」高齢出産を検討されている方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。本記事[…]
知能検査
3つ目は「知能検査」です。
知能検査では、物事の理解や知識、課題解決能力などの認知能力を測定するための検査です。
知能検査を行うことによって、知的障害や発達障害の有無を判断できます。
検査自体は2歳から受けられるものや、5歳から受けられるものまで様々で、対象年齢によって受けられる検査が異なります。
自治体の発達障害者支援センターや小児科などの医療機関で検査を受けられるので、子どもに発達障害や知的障害の傾向が見られるときは検査について問い合わせてみましょう。
高齢出産と障害に関するまとめ

ここまで、高齢出産と子どもの障害との関係についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 高齢出産によって子どもに障害が起こりやすい原因は、加齢に伴い、卵子の質が低下するから
- 高齢出産で健康な子どもを生むためには、食生活やストレス管理などの生活習慣の見直しが大切
- 障害には様々な種類があり、検査方法によって診断可能な障害・疾患が異なるので、気になる人は専門機関に相談しよう
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。