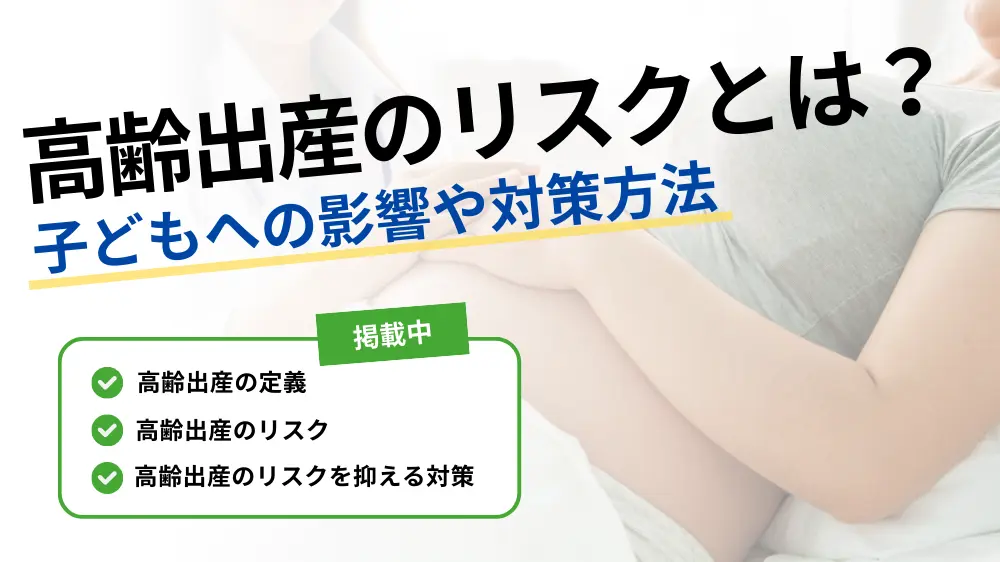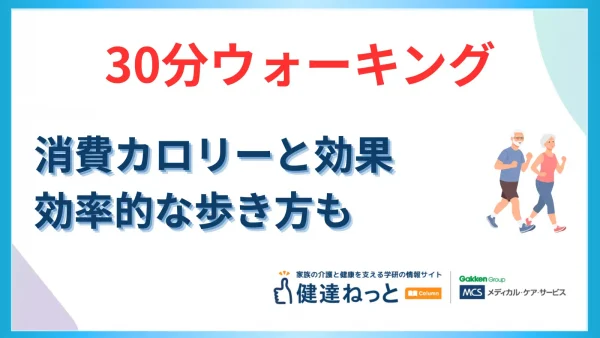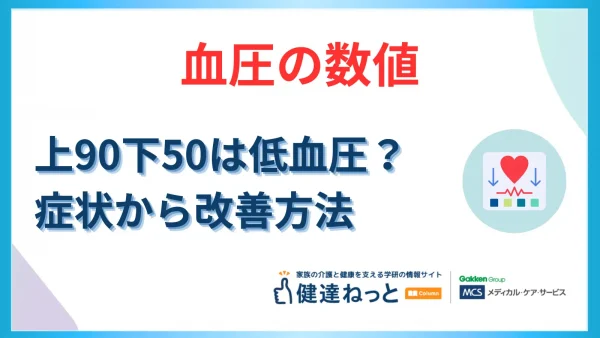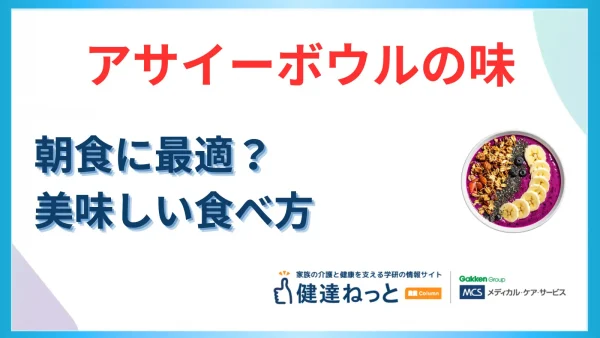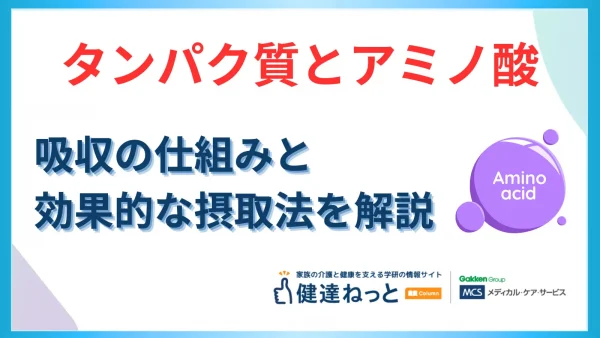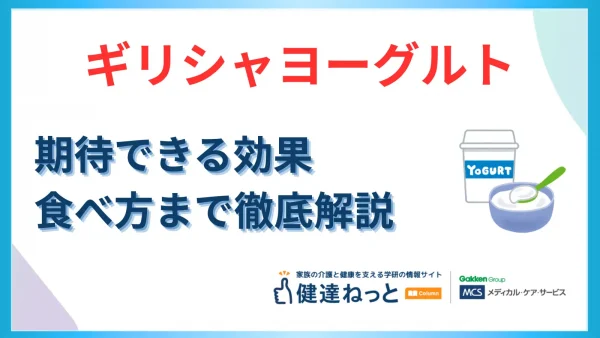「高齢出産は子どもに障害があらわれやすいのかな」
「高齢出産が原因で障害児だったらどうしよう」
出産を控えている人や、出産を検討している人の中には、このように考えている人も多いのではないでしょうか。
高齢での出産は35歳までの出産よりも子どもに障害があらわれやすいため、生活習慣などに注意を払う必要があります。
本記事では、子どもの障害について以下の点を中心に解説します。
- 高齢出産で子どもに障害があらわれやすい理由
- 出生前に障害の有無を調べる方法
- 子どもに障害を引き起こさないための予防策
子どもが障害を持つリスクを減らす方法にご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
高齢出産で子どもに障害があらわれやすい理由

まずはじめに、高齢出産で子どもに障害があらわれやすい理由をご紹介します。
高齢出産で子どもに障害があらわれやすい理由は、女性の加齢に伴い、卵子の質が低下するためです。
女性の身体は35歳を過ぎると閉経の準備に入り、卵巣機能が低下していきます。
卵巣の機能低下が起こると、卵子がダメージを受けたり、染色体異常が増えたりするため、子どもが障害を持つリスクが高くなります。
また、卵子の質の低下は加齢による原因の他、タバコやアルコールの摂取、不規則な生活やストレスなども関係してくるため、日頃の生活習慣を見直すなどの対策も必要です。
高齢出産の傾向やリスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
「高齢出産って何歳から?」「高齢出産による子どもの体への影響が心配」30代で子どもを産もうと考えている、あるいは出産を控えている30代〜40代の方の中には、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。国内[…]
スポンサーリンク
高齢出産で子どもに起こりやすい障害

ここでは、高齢出産で子どもに起こりやすい障害を3つご紹介します。
- 染色体異常
- 遺伝子異常
- 発達障害
染色体異常
高齢出産で子どもに起こりやすい障害の1つ目は「染色体異常」です。
細胞の核の中には複数の遺伝子情報を持つ構造体(染色体)があり、受精卵が細胞分裂するときに染色体の本数に異常があると、子どもに先天性の疾患が起こりやすくなります。
染色体異常によって引き起こされる先天性の疾患には、主に次の5つが挙げられます。
- ダウン症候群(21トリソミー)
- パトウ症候群(13トリソミー)
- エドワーズ症候群(18トリソミー)
- ターナー症候群
- クラインフェルター症候群
これらの中でも発生する頻度の多い疾患がダウン症候群です。
ダウン症候群を発症すると筋肉の緊張が低下したり、知的障害や発達が遅れたりなどの症状があらわれます。
遺伝子異常
2つ目は「遺伝子異常」です。
遺伝子異常は、母親と父親から受け継ぐ遺伝要因と、たばこなどの環境要因の2つが主な原因となりますが、加齢に伴い遺伝子異常を持つ細胞が増加することも知られています。
遺伝子異常によって引き起こされる疾患の総数は7,000を超え、代表例としては筋ジストロフィーやパーキンソン病などが挙げられます。
これらの先天的な疾患は完治が難しく、生涯にわたり医療が必要です。
発達障害
3つ目は「発達障害」です。
発達障害とは、生まれつきの脳機能の障害で主に次の3つが挙げられます。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
生まれてすぐに発達障害の有無を判断することは難しく、年齢を重ねていく中で発達が気になれば検査を受けて診断します。
症状の強さには個人差があるため、2~3歳の頃に発達の遅れなどに気づいて検査を行うケースや、就学してから発達障害の特性が強くあらわれて検査を受けるケースなど、子どもによって様々です。
高齢出産と発達障害の関わりについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
「高齢出産による発達障害のリスクが気になる」「高齢出産による発達障害のリスクを軽減するために、どのような対策を取ればいいのか知りたい」高齢出産を検討されている方の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。本記事[…]
子どもに障害が発生する確率

ここでは、子どもに障害が発生する確率をご紹介します。
子どもに障害が発生する確率は、母親の年齢が上がるにつれ高くなります。
高齢出産でよく見られる子どものダウン症候群の確率は、母親が20歳のときの出産では1/1667、40歳のときの出産では1/106の確率です。
また、発達障害は母親の年齢だけでなく、父親の年齢も関係していることがわかっています。
発達障害の一種である自閉症スペクトラム障害は、父親の年齢が10歳上がるたびにリスクが2倍以上になるという研究結果があります。
父母ともに加齢によるリスクは避けられないため、出産を望む場合は、早めに妊活に取組むべきといえます。
出生前に障害の有無を調べる方法

ここでは、出生前に障害の有無を調べる方法を5つご紹介します。
- 超音波(エコー)検査
- NIPT(新型出生前診断)
- 母体血清マーカー検査
- 絨毛検査
- 羊水検査
1~3の検査は非確定検査と呼ばれ、4と5の確定検査を行うための事前検査です。
非確定検査では子どもが染色体異常を持つ可能性がわかり、確定検査では病気や障害の有無を確認できるといった違いがあります。
超音波(エコー)検査
出生前に障害の有無を調べる方法の1つ目は「超音波(エコー)検査」です。
腹部に超音波を当てて赤ちゃんの脳や臓器、顔や身体の特徴を調べて異常がないかを判断します。
検査は15~30分ほどの短時間で終わり、子宮を傷つける心配もないため、流産や死産のリスクが少ないことがメリットです。
ただし、絨毛検査や羊水検査と比べて精度は低いので、あくまで障害や病気の可能性を探るための手段といえます。
NIPT(新型出生前診断)
2つ目は「NIPT(新型出生前診断)」です。
検査では、妊婦の血液中に含まれる赤ちゃんのDNAの断片を解析して、染色体疾患を調べます。
NIPTは他の非確定検査と比べても精度が高いといった特徴があり、ダウン症候群(21ソリトミー)の検査精度は99%以上を誇ります。
ただし、基本的に調べられる疾患は以下の3つです。
- ダウン症候群(21トリソミー)
- パトウ症候群(13トリソミー)
- エドワーズ症候群(18トリソミー)
費用相場は20万円前後と高額で、日本医学連合会が認証した医療機関でのみ検査が可能です。
母体血清マーカー検査
3つ目は「母体血清マーカー検査」です。
NIPTと同様に、妊婦から血液を採取して血液中の物質を調べて病気の可能性を判断します。
費用は2~3万程度と安いですが、検査精度は約80%とNIPTと比べて劣ります。
偽陽性が出る確率が5%もあり、的中率が高いとはいい難い検査です。
調べられる疾患や障害は以下の3つで、全ての疾患や障害に対応しているわけではありません。
- ダウン症候群(21トリソミー)
- エドワーズ症候群(18トリソミー)
- 開放性神経管奇形
絨毛検査
4つ目は「絨毛検査」です。
妊娠11~14週の早い時期に、妊婦の腹部に注射針を刺して絨毛組織を採取します。
採取した絨毛組織から、赤ちゃんに染色体異常症や先天的な病気がないかをほぼ100%の確率で発見できます。
ただし、絨毛検査でわかるのは、染色体や遺伝子の異常を原因とした疾患や病気の有無だけで、知能や能力に関連する発達障害の有無はわかりません。
また、母子ともに不安定な時期に行う検査のため、流産や死産が約1%の割合で発生するといわれています。
その他、出血や破水、子宮内膜症など様々なリスクがあるため、非確定検査で陽性反応が出た場合や高齢出産などの特定の条件に当てはまる妊婦に限り検査可能です。
羊水検査
5つ目は「羊水検査」です。
妊娠15週以降の妊婦の腹部に注射針を刺して羊水を採取し、羊水に含まれる赤ちゃんの細胞を調べて検査します。
絨毛検査と同様に染色体異常があるかを確認し、疾患などの有無を判断する検査方法です。
しかし、検査を受けられる時期が絨毛検査よりも遅い点には注意が必要です。
羊水検査の結果には2~4週間程度の時間を要しますが、人工中絶が可能な時期は、母体保護法により22週未満と決められています。
そのため、検査を受けて人工中絶を検討する場合は、遅くとも17週目までには検査を受けておく必要があります。
また、非確定検査で陽性反応があったときや高齢出産などの特定の条件に限り検査ができるため、全ての妊婦が受けられるわけではありません。
子どもに障害を引き起こさないための予防策

ここでは、子どもに障害を引き起こさないための予防策を4つご紹介します。
- 葉酸を積極的に摂取する
- 妊婦健診を欠かさず受ける
- 感染症予防を行う
- 禁煙する
葉酸を積極的に摂取する
子どもに障害を引き起こさないための予防策の1つ目は「葉酸を積極的に摂取すること」です。
葉酸は赤ちゃんの脳や神経が形成されていく妊娠初期では、通常の食事に加えて1日400μg(マイクログラム)の葉酸を摂取することが推奨されています。
葉酸が不足すると神経管閉鎖障害の発症のリスクが高まるため、以下の食材を中心とした食事を意識し、不足分はサプリメントで補うようにしましょう。
- ブロッコリー
- アボカド
- さつまいも
- いちご
- 納豆
ただし、妊娠中に1日1000μg以上の葉酸を摂取した場合、小児ぜんそくを引き起こすリスクが高まります。
葉酸の過剰摂取には注意してください。
妊娠前や妊娠初期に摂取すべきサプリについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
妊娠は女性の体に大きな変化をもたらし、その期間中に適切な栄養素を摂取することが非常に重要です。サプリメントは、必要な栄養素を効率的に摂取する手段として、多くの妊婦にとって欠かせない存在となっています。しかし、どのサプリメントを選[…]
妊婦健診を欠かさず受ける
2つ目は「妊婦健診を欠かさず受けること」です。
妊婦健診は定期的に行われ、採血や超音波検査、体重測定などから母子の健康状態と赤ちゃんの発育状況をチェックします。
妊婦健診では専門家から状況に応じて生活・食事の指導を受けられるうえ、元気な赤ちゃんを生むために注意すべきこともわかります。
特に母親の肥満は、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病といった合併症を引き起こす可能性があり、赤ちゃんに発育不全や形態異常があらわれるリスクが高まります。
このようなリスクを下げるためにも、妊婦健診は欠かさず受け、専門家へ指導を仰ぎましょう。
感染症予防を行う
3つ目は「感染症予防を行うこと」です。
妊婦が細菌やウイルスに感染すると赤ちゃんにも感染する、母子感染の可能性があります。
母子感染では、先天的な障害や重篤な病気を持つリスクだけでなく、流産や死産のリスクも高まるため非常に危険です。
このような事態を避けるためにも、妊娠中は以下の感染症予防を行うことが大切です。
- 人混みを避ける
- マスクの着用する
- 手洗いやうがいの徹底
禁煙する
4つ目は「禁煙すること」です。
たばこに含まれるニコチンには血管を収縮させる働きがあり、子宮や胎盤への血液量減少を招きます。
血液量が減少してしまうと、赤ちゃんに必要な酸素や栄養素が供給されなくなるため、以下のような悪影響が出るとされています。
- 赤ちゃんの発育遅延や低出生体重での出産
- 流産/死産/早産のリスクが高まる
- 赤ちゃんの身体が奇形になるリスクが高まる
また、ニコチンの神経毒性が、発達障害との関連があることも報告されています。
妊婦の禁煙はもちろんですが、副流煙にも注意が必要です。
家族や知人の中に喫煙者がいるなら、禁煙してもらったり、離れた場所で喫煙してもらったりなどの配慮をお願いしましょう。
中絶手術のリスクについて

最後に、中絶手術のリスクについて2つご紹介します。
- 身体面でのリスク
- 精神面でのリスク
身体面でのリスク
中絶手術のリスクの1つ目は「身体面でのリスク」です。
中絶手術を行うことで、母体には次のようなリスクが伴います。
- 感染症
- 出血
- 子宮に穴が開く
- 月経不順
手術後に起こる痛みや出血によって、めまいや頭痛などの症状があらわれることもあり、母体への負担が大きいことがわかります。
また、中絶手術が原因で不妊症になる可能性は低いですが、その後に引き起こされる感染症の影響で不妊症のリスクが高まるケースもあります。
中絶手術の後に、感染症の疑いがある場合は早急に婦人科への受診が必要です。
精神面でのリスク
2つ目は「精神面でのリスク」です。
中絶手術による精神的なストレスが原因で、中絶後遺症候群(PAS)を発症する可能性があります。
中絶後遺症候群(PAS)には次のような症状が挙げられます。
治療には婦人科や心療内科への受診・通院が必要です。
- 中絶手術の記憶がフラッシュバックされ、強い恐怖心に襲われる
- 眠りが浅い/寝つきが悪いなどの不眠症状
- 気分が落ち込むなどのうつ症状
症状が重度の場合、自傷行為などの願望が出る恐れもあるため、精神面への影響は軽視できない問題です。
ストレス解消に役立つおすすめグッズに興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
高齢出産で障害児だった場合まとめ

ここまで高齢出産と子どもの障害との関係についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 加齢に伴う卵子の質の低下により、子どもに障害や疾患があらわれる確率は上がる
- 出生前の検査では、赤ちゃんに障害がある可能性や障害の有無を調べられる
- 中絶手術は母親の身体や精神に大きな負担となるため、元気な赤ちゃんを生むためにも、生活習慣や定期健診が大切
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。