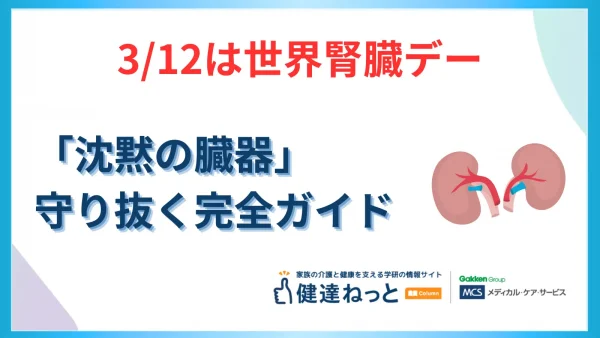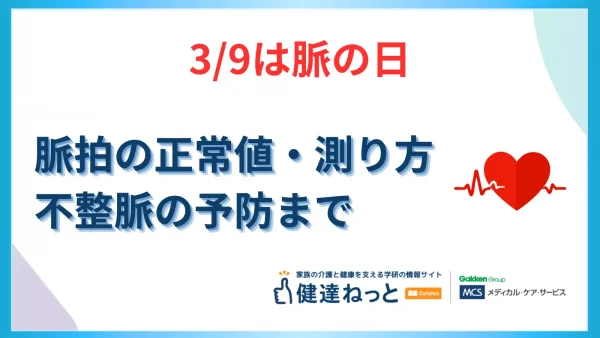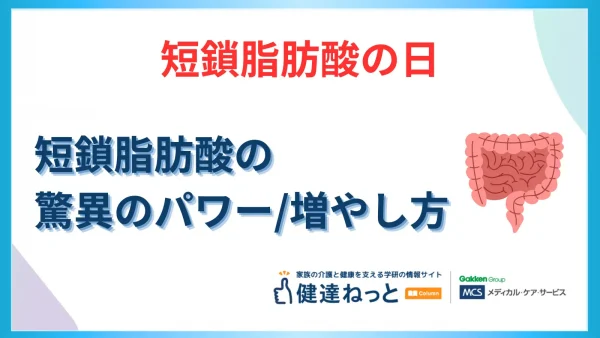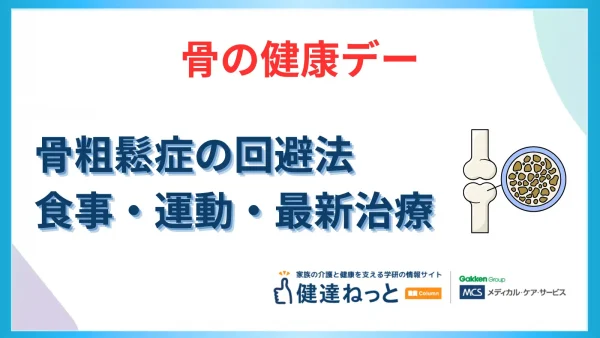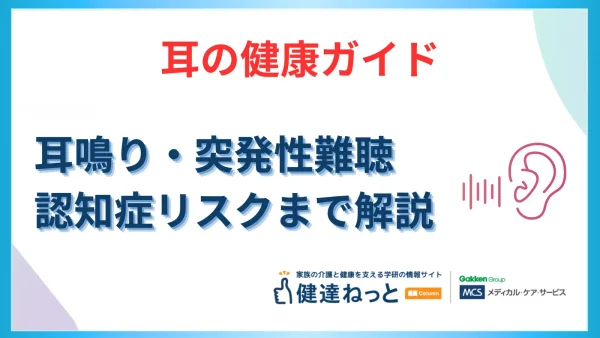食物繊維は便通改善の効果がある栄養素です。
水溶性食物繊維は栄養素の吸収に、不溶性栄養素は便の嵩に関係しています。
食物繊維の水溶性・不溶性はそれぞれどのような効果があるのでしょうか。
本記事では水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違いや食物繊維とダイエットの関係についてご紹介していきます
- 水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違いについて
- 1日にどのくらい食物繊維を摂取すると良いのか
- 食物繊維とダイエットについて
今回の食物繊維に関する情報が、皆さまの健康増進やダイエットについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ、最後までお読みください。
スポンサーリンク
食物繊維とは

食物繊維とは、私たちの体内にある消化酵素では消化することができない栄養素のことです。
食物繊維にはお腹の調子を整えたり、便通を良くするイメージがある方が多いです。
しかし、他にも身体に良い作用が秘められています。
- 便の嵩(かさ)を増やして便通を良くしてくれる
- 食後の血糖値の急上昇を緩やかにして体重増加や糖尿病を防ぐ
- 腸内細菌を活発にして免疫や消化を助ける
上記のように、食物繊維には便通改善以外にも多くの健康効果を期待できます。
食物繊維は、炭水化物やタンパク質などの五大栄養素に次いで「第六の栄養素」といわれています。食物繊維はおなかの調子を整え、便秘の解消に効果的です。では、食物繊維とは具体的にどのような栄養素なのでしょうか。本記事では食物繊維につ[…]
スポンサーリンク
水溶性食物繊維・不溶性食物繊維の特徴

食物繊維には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のそれぞれの特徴を把握して、自分に身体に必要な食物繊維を摂取してみてください。
水溶性食物繊維
水溶性食物繊維は、水に溶けることでドロドロのジェル状に変化します。
ドロドロのジェル状になった食物繊維は小腸、大腸内に張りついて糖質やコレステロールなどの栄養素の吸収をゆっくりにする作用があります。
また、体外に排出する作用もあるため、高血圧、糖尿病や脂質異常症の予防に効果があります。
水溶性食物繊維を多く含む食品の例は以下の通りです。
- ワカメや昆布、めかぶなどの海藻類
- 切り干し大根やゴボウなどの野菜類
水溶性食物繊維を効率的に取るには、お味噌汁に入っているだし昆布を一緒に食べたり、わかめ味噌汁がオススメです。
不溶性食物繊維
不溶性食物繊維は、水に溶けずに、水分を吸収して便の嵩を増やす作用があります。
不溶性食物繊維の摂取によって便の嵩が増えます。
すると大腸を内部から圧迫され、蠕動運動(ぜんどううんどう)と呼ばれる腸の動きが活発になり排便が促されます。
また、不溶性食物繊維が腸内の毒素など様々な物質を吸収して、便と一緒に体外へ排出する作用もあります。
不溶性食物繊維を多く含む食品の例は以下の通りです。
- ライ麦や玄米などの穀類
- 小豆や大豆などの豆類
普段の食事を少し工夫するだけで不溶性食物繊維を多くとることができます。
主食の白米を精製度の低い玄米に変えてみましょう。
もしくは、毎日の食事に納豆を1パック追加することで手軽に不溶性食物繊維の摂取量を増やすことができます。
タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]
水溶性食物繊維の多い食品ランキング|ベスト10

水溶性食物繊維の豊富な食品ベスト10をランキング形式でまとめました。
含有量(g/100g) | |
| らっきょう | 18.6 |
| スーパー大麦 | 8.3 |
| 押し麦 | 4.3 |
| えんばく/オートミール | 3.2 |
| ごぼう | 2.3 |
| 豆みそ | 2.2 |
| レモン | 2 |
| アボカド | 1.7 |
| ごま | 1.6 |
| 大豆 | 1.5 |
出典:文部科学省【日本食品標準成分表2020年版(八訂)】
出典:【栄養成分表示 | (一財)日本食品分析センター】
食物繊維のサプリの効果とメリット

食物繊維は、消化されない食品成分の総称で、水溶性と不溶性の2種類があります。
食物繊維は、便秘や糖尿病、高血圧などの予防や改善に役立つと言われていますが、日本人の食物繊維摂取量は、推奨量の約半分しかありません。
そこで、食物繊維のサプリメントが注目されていますが、本当に効果があるのでしょうか?また、どんなメリットがあるのでしょうか?
食物繊維のサプリも効果がある?
食物繊維のサプリメントは、食物繊維を含む植物由来の粉末や錠剤などの形で販売されています。
食物繊維のサプリメントは、食事から摂取するのと同じように、腸内環境の改善や血糖値のコントロールなどの効果が期待できます。
ただし、食物繊維のサプリメントは、食事から摂取する食物繊維とは異なり、他の栄養素や食品成分との相互作用がありません。
そのため、食物繊維のサプリメントの効果は、個人差や摂取量、摂取タイミングなどによって変わる可能性があります。
また、食物繊維のサプリメントは、水分と一緒に摂取しないと、腸内で固まって便秘を悪化させることもあります。
したがって、食物繊維のサプリメントは、食事から十分に摂取できない場合や、医師の指示に従って、適切な量と方法で摂取することが重要です。
食物繊維のサプリのメリット
食物繊維のサプリメントのメリットは、食事から摂取するのと比べて、以下のような点が挙げられます。
食物繊維のサプリのメリット|摂取量を調節しやすい
食物繊維のサプリメントは、1回分の摂取量が明確に表示されているので、自分の目標や体調に合わせて摂取量を調節しやすいです。
また、水溶性と不溶性のバランスも調整できます。
食物繊維のサプリのメリット|摂取しやすい
食物繊維のサプリメントは、味やにおいが気にならないものも多く、飲みやすいです。
また、持ち運びやすく、外出先や職場でも摂取できます。
食物繊維のサプリのメリット|食物アレルギーの心配がない
食物繊維のサプリメントは、原料となる植物の種類や成分が明記されているので、食物アレルギーのある人でも安心して摂取できます。
食物繊維のサプリメントは、食物繊維の摂取量を補う手段として有効ですが、食事から摂取する食物繊維に代わるものではありません。
食物繊維は、野菜や果物、穀物などの食品に含まれる他の栄養素や食品成分と一緒に摂取することで、より効果的に働きます。
そのため、食物繊維のサプリメントは、バランスの良い食事と併用することがおすすめです。
以下の記事では、食物繊維のサプリについてさらに詳しく解説しています。 近年、健康志向の高まりとともに、食物繊維サプリの需要が増えています。食物繊維は、私たちの健康にとって非常に重要な要素です。便秘解消やダイエット効果など、その効果は多岐にわたります。しかし、食物繊維サプリには様々な種類があり、[…]
食物繊維を摂るなら青汁がおすすめ!【青汁ランキング15選】
食物繊維は不足すると、体にさまざまな異変をきたします。
そのため、食物繊維の不足を改善することは健康的に生活するために非常に大切なことです。
食物繊維を手軽に補いたい方にお勧めしたいのが「青汁」です。
実は、青汁には食物繊維を含め、さまざまな栄養素が豊富に含まれています。
食物繊維不足の改善におすすめの青汁を15商品紹介しているので、自分の目的や希望に合った青汁をぜひ検討してみてください!
 | .jpg) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 商品名 | (FABIUS) すっきりフルーツ青汁 | (美的ラボ) まんぷく美人青汁 | (Vivid Healthcare) GREEN MILK | (ナチュレライフ) 美長命青汁 | (SENOBIRU) こどもバナナ青汁 | (ナチュレライフ) ドクターベジフル | (KENPRIA) RICH GREEN | (ナチュラルファーム) スカルプ青汁 | (マイケア) ふるさと青汁 |
| 価格・内容量 | 90g(3g×30包) 4,298円〜 | 90g(3g×30包) 6,458円〜 | 150g(5g×30包) 1,000円〜 | 1箱(1.5g×30包) 5,100円〜 | 1箱(30包) 1,058円〜 | 90g(3g×30包) 2,894円〜 | 3g×12スティック 500円〜 | 2.5g×30日分 980円〜 | 3g×30包 3,693円〜 |
| 定期購入価格 | 初回:680円 2回目以降:3,758円 ※4ヶ月以上縛りあり | 初回:680円 2回目以降:4,298円 ※4ヶ月以上縛りあり | 初回:1,000円 2回目以降:4,536円 定期縛りなし! | 初回:2,106円 2回目以降:3,564円 定期縛りなし! | 初回:1,058円 2回目以降:3,996円 ※2ヶ月以上縛りあり | 初回:2,894円 2回目以降:3,402円 定期縛りなし! | 3,694円 定期縛りなし! | 初回:980円 2回目以降:4,000円 ※定期縛りあり | 3,693円 定期縛りなし! |
| 特徴 | ・81種類の酵素配合 ・美容成分配合 ・アレンジレシピが豊富 | ・こんにゃくマンナンによる満腹感 ・脂肪燃焼効果 ・高級美容成分 配合 ・112種類の酵素配合 | ・DHA・EPA配合 ・成長期の子ども用の青汁 | ・長命草による血糖値の改善 ・ケールを超える濃密な栄養バランス | ・こどもに必要な50種類の栄養素 ・美味しく飲めるバナナ味 | ・生産者の顔がわかる九州産野菜使用 ・良質なタンパク質も摂取できる | ・独自の活性保存製法で酵素が生きている ・生搾りで特別なエキス抽出 | ・育毛メーカーと共同開発 ・スカルプケア成分のヒハツエキス配合 | ・スパーフード「明日葉」を豊富に配合 |
| おすすめな人 | 青汁の 味・匂いが苦手 な人! | 美容効果・ ダイエット効果 を求めている人! | 子どもの成長・学力の向上 を支える青汁を探している方! | 血糖値や野菜不足が気になる方! | 子どもも美味しく飲める栄養満点な青汁を探している方! | 安心・安全な 国産素材の青汁 を探している方! | 健康・美容両方に力を入れたい方! | 薄毛予防 をしたい方! | いつまでも 若々しく いたい方! |
| 特典情報 | ・初回限定キャンペーン ・全国どこでも送料無料 ・お届け周期の変更可能 | ・90日間全額返金保証 ・初回実質無料(送料以外) | ・初回限定割引あり ・全額返金保証あり | ・安心の30日間全額返金保証 ・初回価格62%OFF | ・60日間全額返金保証 ・初回限定キャンペーンあり ・豪華賞品が当たるキャンペーンあり | ・定期割引あり ・全額返金保証あり | ・初回限定キャンペーンあり | ・初回限定キャンペーンあり | 5,832円以上で送料無料 |
| 支払い方法 | ・クレジットカード ・NP後払い | ・クレジットカード ・後払い | ・クレジットカード ・代金引換 ・NP後払い | ・クレジットカード ・デビットカード ・後払い ・Amazon pay ・楽天ペイ | ・クレジットカード ・代金引換 ・後払い | ・クレジットカード ・後払い | ・クレジットカード ・代金引換 ・後払い | ・クレジットカード ・Amazon Pay ・後払い | ・クレジットカード ・代金引換 ・後払い |
| 商品の詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
1位【FABIUS すっきりフルーツ青汁】
FABIUS「すっきりフルーツ青汁」は青汁に苦手意識がある方におすすめです。
青汁特有の青臭さがなく、過去に青汁が続かなかった方でも飲みやすくなっています。
また、「すっきりフルーツ青汁」を使用したさまざまなアレンジレシピがあります。
青汁に飽きた経験のある方や青汁が苦手な方におすすめの青汁です。
| 商品名 | FABIUS「すっきりフルーツ青汁」 |
| 価格・内容量 | 90g(3g×30包):4,298円〜 |
| 定期購入価格 | 初回 680円 2回目以降 3,758円 ※定期縛りあり:初回含め4ヶ月以上 |
| 特徴 | ・81種類の酵素配合 ・3種類の美容成分配合 ・飽きないアレンジレシピが豊富 |
| 成分・原材料 | 還元麦芽糖水飴、大麦若葉粉末、熊笹粉末、乳頭、デキストリン、明日葉粉末、マンゴー果汁パウダー、抹茶、植物発酵物乾燥粉末、いちご果汁パウダー、アカシア食物繊維、アセロラパウダー、グァガム、イナゴ豆抽出物、藍藻抽出物、アカメガシワエキス末、有胞子性乳酸菌、メロンプラセンタ抽出物、フルーツ野菜エキス、茶抽出物、豆乳末、ざくろ抽出物、パイナップル果汁抽出物、香料、βカロテン、シクロデキストリン |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 11.8Kcal |
| 特典情報 | ・初回限定キャンペーンあり ・全国どこでも送料無料 ・お届け周期の変更可能 |
| 支払い方法 | クレジットカード、NP後払い |
2位【美的ラボ まんぷく美人青汁】
美容やダイエットのために青汁を飲もうと考えている方も多いのではないでしょうか?
そのような方におすすめの青汁が美人ラボの「まんぷく美人青汁」です。
この青汁には、美容成分や脂肪燃焼効果のある成分が含まれています。
また、満腹感があるこんにゃくマンナンも含まれているため、1食と置き換えやすいです。
美容やダイエットしたい方はぜひ「まんぷく美人青汁」を試してみてはいかがでしょうか?
| 商品名 | 美的ラボ「まんぷく美人青汁」 |
| 価格・内容量 | 3g×30包:6,458円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 680円 2回目以降 4,298円 ※定期縛りあり:4回受け取り必要 |
| 特徴 | ・こんにゃくマンナンによる満腹感 ・L-カルニチンによる脂肪燃焼サポート ・高級美容成分配合 ・112種類の酵素配合 |
| 成分・原材料 | 乾燥おからパウダー、グルコマンナン、クロレラ原末、大麦若葉末、難消化デキストリン、酵母エキス、野草発酵エキス末、ヘンププロテイン、ココナッツオイル、穀物発酵エキス、コラーゲンペプチド、乾燥酵母粉末、L-カルニチンフマル酸塩、緑茶、豚プラセンタエキス、クコの実末、マキベリー果汁パウダー、鉄含有酵母、モリンガ粉末、乳酸菌末、ソルビトール、増粘菌多糖類、香料、クエン酸、甘味料、ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、抽出ビタミンE、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 6.95Kcal |
| 特典情報 | ・90日間全額返金保証 ・初回実質無料(送料のみ) |
| 支払い方法 | クレジットカード、後払い |
3位【ファンケル 野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁】
最近野菜不足が気になる方や腸の調子を整えたい方におすすめの青汁です。
この「野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁」には不足しがちな緑黄色野菜のケールが35gと豊富に含まれています。
また、機能性関与成分であるビフィズス菌BB536と有胞子性乳酸菌も含まれています。
腸内細菌のバランスを整える効果や腸に届いて善玉菌を増やす効果があります。
美味しく手軽に野菜を摂りたい方や腸内環境を整えたい方におすすめです。
| 商品名 | ファンケル「野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁」 |
| 価格・内容量 | 30本入り:3,600円〜 90本入り:10,260円〜 |
| 定期購入価格 | 30本入り:3,240円 90本入り:9,234円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・ケール青汁として日本初の機能性表示食品 ・腸の調子を整えるビフィズス菌入り ・すっきり飲みやすい宇治抹茶入り |
| 成分・原材料 | ケール粉末(ケール国内産、でんぷん分解物)還元麦芽糖、難消化性デキストリン、スダチ粉末、ビフィズス菌末、有胞子性乳酸菌末、抹茶、植物性乳酸菌殺菌末、保存料香料無添加 |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 11Kcal |
| 特典情報 | 初めての方限定!特別価格980円(14本入り) |
| 支払い方法 | クレジットカード、振込用紙、代金引換、口座自動引落し、PayPay |
4位【Vivid Healthcare GREEN MILK(グリーンミルク)】
Vivid Healthcareの「GREEN MILK」は、お子様の成長を応援する青汁です。
お子様の勉強のことで、暗記や計算が苦手、集中力がないなどの悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?
「GREEN MILK」は、子どもの成長や学力の向上に必要と言われているDHAやEPAが配合されています。
「GREEN MILK」を飲むことで、子どもの一番伸びる時期のサポートになるのです。
上のような悩みがある方は、ぜひ試してみてください。
| 商品名 | Vivid Healthcare「GREEN MILK(グリーンミルク)」 |
| 価格・内容量 | 5g×30包:1,000円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 1,000円 2回目以降 4,536円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・DHAとEPAを配合 ・成長期の子ども用の青汁 |
| 成分・原材料 | 還元麦芽糖、有機大麦若葉末、クリーミングパウダー、DHA・EPA含有精製魚油、ミルクカルシウム、抹茶粉末、難消化デキストリン、植物発酵エキス末、卵殻カルシウム、ステビア(甘味料)、ビタミンC |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 14.65Kcal(1包5gあたり) |
| 特典情報 | ・初回限定割引あり ・全額返金保証あり |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、NP後払い |
5位【ナチュレライフ 美長命青汁】
ナチュレライフの「美長命青汁」は食後の血糖値が高い方や野菜不足の方におすすめの青汁です。
長命草(ボタンボウフウ)という野菜を使用しており、ポリフェノールの一種である、クロロゲン酸の働きにより血糖値を抑える働きがあります。
さらに、従来の青汁の原料と使用されるケールをはるかに超える濃密な栄養素が豊富に含まれています。
食後の血糖値が気になる方や野菜不足の方はぜひ「美長命青汁」試してみてはいかがでしょうか?
| 商品名 | ナチュレライフ「美長命青汁」 |
| 価格・内容量 | 1箱(1.5g×30包):5,100円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 2,106円 2回目以降 3,564円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・長命草による血糖値の改善 ・ケールを超える濃密な栄養バランス |
| 成分・原材料 | ボタンボウフウ若葉末(鹿児島県産) |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 4.01Kcal |
| 特典情報 | ・安心の30日間全額返金保証 ・初回価格約62%OFF |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、後払い(コンビニ、郵便局、銀行、LINE Pay)、Amazon pay、楽天ペイ |
6位【SENOBIRU(こどもバナナ青汁)】
SENOBIRUの「こどもバナナ青汁」はお子様におすすめな青汁です。
子どもの成長に必要な栄養素が50種類以上含まれています。
さらに、WHO(世界保健機関)も推奨しているスーパーフードのスピルリナも配合されています。
「こどもバナナ青汁」は美味しく飲めるバナナ味のため、家族みんなで飲むことができます。
子どもの栄養不足が心配な方や家族で一緒に飲みたい方におすすめです。
| 商品名 | SENOBIRU「こどもバナナ青汁」 |
| 価格・内容量 | 1箱(30包):1,058円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 1,058円 2回目以降 3,996円 ※定期縛りあり:2ヶ月以上継続 |
| 特徴 | ・こどもに必要な50種類の栄養素 ・美味しく飲めるバナナ味 ・こどもの成長や健康に役立つ情報提供あり |
| 成分・原材料 | デキストリン、大麦若葉末、還元麦芽糖水飴、乾燥バナナパウダー、甘味料、香料、酸味料 |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 11.6Kcal |
| 特典情報 | ・60日間全額返金保証 ・初回限定キャンペーンあり ・電話1本で解約可能 ・豪華賞品が当たるキャンペーンあり |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、後払い |
7位【ナチュレライフ ドクターベジフル】
ナチュレライフの「ドクターベジフル」は、野菜のプロである髙上青果の髙上実さんがプロデュースした青汁です。
21種類の豊富な野菜の栄養成分がたっぷり入っており、野菜不足に悩んでいる方におすすめな商品です。
「ドクターベジフル」に使用されている野菜は、全て顔のわかる契約農家さんが作った野菜を使用しています。
使用している野菜は全て九州産であり、公式サイトで農家の方1人1人を確認することができます。
野菜不足に悩んでいる方や安心安全な産地にこだわりたい方におすすめな青汁です。
| 商品名 | ナチュレライフ「ドクターベジフル」 |
| 価格・内容量 | 90g(3g×30包):2,894円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 2,894円 2回目以降 3,402円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・生産者の顔がわかる九州産野菜使用 ・良質なタンパク質も摂取できる |
| 成分・原材料 | 大麦若葉末、きなこ、黒糖、かぼちゃパウダー、おから末、さつまいもパウダー、紫いもパウダー、野菜ミックスパウダー、小松菜、人参、サニーレタス、グリーンリーフ、チンゲン菜、春菊、レタス、パセリ、ごぼう、ピーマン、アスパラガス、大葉 |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 10.41Kcal |
| 特典情報 | ・定期割引あり ・1回でも休止、中止可能 ・全額返金保証あり |
| 支払い方法 | クレジットカード、後払い(コンビニ、郵便局、銀行、LINE Pay) |
8位【KENPRIA RICH GREEN(リッチグリーン)】

KENPRIAの「RICH GREEN(リッチグリーン)」は健康と美容に力を入れたい方におすすめの青汁です。
「RICH GREEN(リッチグリーン)」は、青汁では珍しい生搾りで作られています。
生搾りで作っているおかげで、女性の美容に必要なコラーゲンを補う酵素が失われることなく豊富に含まれています。
健康と美容に力を入れたい方におすすめな青汁といえます。
| 商品名 | KENPRIA「RICH GREEN(リッチグリーン)」 |
| 価格・内容量 | 3g×12スティック:500円〜 |
| 定期購入価格 | 定期便価格 3,694円 定期縛りなし! |
| 特徴 | ・独自の活性保存製法で酵素が生きている ・生搾りで特別なエキス抽出 |
| 成分・原材料 | 大麦若葉(九州産)、でんぷん分解物 |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 9.5〜12.2Kcal |
| 特典情報 | ・初回限定割引キャンペーンあり |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、後払い |
9位【ナチュラルファーム スカルプ青汁】
ナチュラルファームの「スカルプ青汁」は男性におすすめな青汁です。
育毛剤メーカーと共同開発された栄養機能食品で、脱毛を防いだり、頭皮をはじめとする髪の健康に必要な栄養成分が含まれています。
近年、身体の内側からスカルプケアをサポートする成分として注目されているヒハツエキが配合されています。
薄毛や育毛に興味がある方は、ぜひ試してみてください。
| 商品名 | ナチュラルファーム「スカルプ青汁」 |
| 価格・内容量 | 2.5g×30日分:980円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 980円 2回目以降 4,000円(1個あたり) 定期縛りあり:2ヶ月に1回、2個ずつお届け |
| 特徴 | ・育毛メーカーと共同開発 ・栄養機能食品ビオチン配合 ・スカルプケア成分のヒハツエキス配合 |
| 成分・原材料 | 大麦若葉、麦芽糖、ぶどう糖、マルトデキストリン、桑葉、フラクトオリゴ糖、クマザサ粉末、抹茶、大豆抽出物、加熱乳酸混合末、乳酸菌凍結乾燥末、ヒハツ抽出物、ビオチン |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 不明 |
| 特典情報 | ・初回限定キャンペーンあり |
| 支払い方法 | クレジットカード、Amazon pay、後払い |
10位【マイケア ふるさと青汁】
マイケアの「ふるさと青汁」は女性に嬉しい健康・美容成分を多く含む明日葉を丸ごとギュッと豊富に含んだ青汁です。
「明日葉」は日本原産のスーパーフードとも言われており、ビタミンやミネラル、カルシウムはもちろん、美容や健康に役立つβカロテンや食物繊維も豊富に含む食材です。
さらに、「ふるさと青汁」は希少ポリフェノール「カルコン」や大注目の健康成分「LPS」も含んでいます。
若々しい自分を取り戻したい、元気に健康的な生活を送りたいという方におすすめです。
| 商品名 | マイケア「ふるさと青汁」 |
| 価格・内容量 | 3g×30包:3,693円〜 |
| 定期購入価格 | 定期購入価格 3,693円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・八丈島の明日葉を根っこまで余すことなく使用 ・明日葉、桑の葉、大麦若葉は国内産100% |
| 成分・原材料 | あしたば葉茎末、難消化デキストリン、直鎖オリゴ糖、あしたば根末、桑の葉末、大麦若葉末 |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 333.9Kcal(90gあたり) |
| 特典情報 | 購入金額5,832円以上で送料無料 |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、後払い(郵便局、コンビニ) |
11位【Biesty めっちゃ乳酸菌フルーツ青汁】
Biestyの「めっちゃ乳酸菌フルーツ青汁」は、名前の通り多くの乳酸菌が配合されています。
「めっちゃ乳酸菌フルーツ青汁」には乳酸菌が1箱あたり約7500億個も配合されています。
たくさんの乳酸菌が生きて腸まで届いて腸内環境にアプローチしてくれます。
また、22種類のフルーツエキスが配合されており、まるでフルーツジュースのように飲むことができます。
| 商品名 | Biesty「めっちゃ乳酸菌フルーツ青汁」 |
| 価格・内容量 | 90g(3g×30包):734円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 734円 2回目以降 4,298円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・乳酸菌7500億個配合 ・3種類の青汁成分 ・22種類のフルーツ・野菜エキス配合 |
| 成分・原材料 | 還元麦芽糖水飴、デキストリン、クマザサ粉末、緑茶粉末、果汁パウダー、明日葉粉末、モリンガ粉末、蓮葉粉末、野草発酵エキス粉末、乳酸菌末、フルーツ・野菜抽出エキス、緑茶抽出物、乳糖、植物発酵物、メロンプラセンタ抽出物、パイナップル果実抽出物、有胞子性乳酸菌、乳酸菌混合末、香料、甘味料、シクロデキストリン |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 詳細不明 |
| 特典情報 | ・初回限定割引あり |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、銀行振込、NP後払い(銀行、郵便局、コンビニ、LINE Pay) |
12位【ていねい通販 boco to deco(ボコとデコ)】

ていねい通販の「boco to deco」は、たった2種類の原材料のみで作られたシンプルな青汁です。
「boco to deco」に使われている明日葉は、化学肥料や農薬を使わない有機農法で作られたものです。
日本で唯一の明日葉の有機栽培を行っている、静岡県東近江市の農園永源寺マルベリー産のもとで収穫されたものを使用しています。
また、ヴィーガン認証済みであり、ヴィーガンの方でも飲むことができる青汁です。
| 商品名 | ていねい通販「boco to deco(ボコとデコ)」 |
| 価格・内容量 | 3g×20本:3,330円〜 |
| 定期購入価格 | 定期購入価格 3,330円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・原材料が2つだけの青汁 ・余計なものを一切入れていない ・ヴィーガン認証済み |
| 成分・原材料 | 有機明日葉粉末、さつまいもでんぷん |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 10.02Kcal(1本あたり) |
| 特典情報 | ・初めて購入でオリジナルマドラープレゼント ・30日間返品保証 ・全国送料無料 |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、振り込み、自動引き落とし |
13位【スクスクのっぽくん(こどもフルーツ青汁)】

スクスクのっぽくんの「こどもフルーツ青汁」は、お子様向けの青汁です。
野菜が足りないお子様のための健康習慣として開発されました。
子ども向けのため、他の青汁とことなり、50mlと1杯の量が少なくなっています。
また、お子様の好みに合わせて味を3種類用意しています。
飽きやすいお子様でも、味を変えながら飲むことができることが特徴です。
| 商品名 | スクスクのっぽくん「こどもフルーツ青汁」 |
| 価格・内容量 | 4g×30包:5,797円〜 |
| 定期購入価格 | 初回価格 5,797円 2回目以降 7,797円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・1日50mlに栄養を凝縮 ・味が3種類あり ・無料お試し可能 |
| 成分・原材料 | 大麦若葉末、サトウキビ等、黒糖、果汁パウダー、バナナパウダー、マンゴーパウダー、フラクトオリゴ糖、乳酸菌末、ビフィズス菌末、植物発酵エキス末、植物性乳酸菌、温州みかん、貝カルシウム、香料、酸味料、乳化剤、ビタミンDなど |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 14.04Kcal(1本4gあたり) 赤の恵:14.08Kcal(1本4gあたり) 黄色の恵:14.48Kcal(1本4gあたり) |
| 特典情報 | ・どのコースでも初回購入2000円OFF ・専用シェーカープレゼント |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、NP後払い |
14位【Pesca 成城青汁】

Pescaの「成城青汁」は日々ストレスを感じている方や、睡眠の質を高めたい方におすすめです。
「成城青汁」は、仕事や勉強などのストレスを緩和し、睡眠の質を高める効果があるGABAが配合されています。
睡眠の質を高めるとともに、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養を同時に補給することができます。
ストレスや疲労を軽減したい方は、ぜひ試してみてください。
| 商品名 | Pesca「成城青汁」 |
| 価格・内容量 | 1袋(10日分):2,200円〜 |
| 定期購入価格 | 定期購入価格 3,960円 3袋(1ヶ月分) *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・GABAによる睡眠の質改善 ・栄養と睡眠のダブルサポート |
| 成分・原材料 | デキストリン、大麦若葉粉末、難消化性デキストリン、ギャバ、還元麦芽糖水飴、ケール粉末、桑の葉粉末、明日葉粉末、ボタンボウフウ粉末、香料、微粒二酸化ケイ素、安定剤 |
| タイプ | 粉末タイプ |
| カロリー | 19.7Kcal(1日6gあたり) |
| 特典情報 | ・全国一律送料600円 ・定期コース送料無料 |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換、NP後払い |
15位【十黒梅(生搾りどくだみ青汁酒)】
十黒梅の「生搾りどくだみ青汁酒」は青汁を使用した健康酒です。
どくだみから作られた青汁に、黒糖と梅肉エキスを合わせてアルコール発酵させたものが、「生搾りどくだみ青汁酒」です。
「生搾りどくだみ青汁酒」は全て国内の自社で生産されています。
お酒好きだけど健康にも気を遣っていきたいという方におすすめです。
| 商品名 | 十黒梅「生搾りどくだみ青汁酒」 |
| 価格・内容量 | 300ml(1日1回30ml×10日分):2,980円〜 |
| 定期購入価格 | 定期購入価格 6,850円 *定期縛りなし! |
| 特徴 | ・青汁に黒糖と梅肉エキスを合わせアルコール発酵させた健康酒 ・農薬不使用、自然素材の発酵酒 |
| 成分・原材料 | どくだみ(高知県産)、加工黒糖(沖縄県産)、梅肉エキス(和歌山県産) |
| タイプ | 健康酒 |
| カロリー | 不明 |
| 特典情報 | ・お試し品送料無料 ・購入金額11,000円以上で送料無料 ・こぼれま栓プレゼント ・返金保証制度あり |
| 支払い方法 | クレジットカード、代金引換 |
食物繊維の摂取目安量について

食物繊維は、消化酵素で分解されにくく、ほとんどが体外へ排出されてしまいます。
かつては「食べ物のカス」といわれ、軽視されていた時代もありました。
現在では、五大栄養素(炭水化物、脂質、タンパク質、無機質、ビタミン)に次ぐ「第6の栄養素」として注目されています。
食物繊維は、整腸作用や、その他にも健康に良いさまざまな効果がある、重要な栄養素です。
しかし健康に欠かせない栄養素であるにも関わらず、現在ほとんどの日本人の食生活において、不足している食品成分なのです。
健康のためにも、積極的に食物繊維を摂ることがすすめられています。
食物繊維の摂取基準
厚生労働省は成人(18~29歳)の食物繊維の1日の目標摂取量※1を以下のようにしています。
- 成人男性:21g
- 成人女性:18g
出典:厚生労働省【日本人の食事摂取基準(2020年版)】
目標摂取量に対し実際の成人(20~29歳)の摂取量は以下のようになっています。
- 成人男性:17.5g
- 成人女性:14.6g
出典:厚生労働省【令和元年国民健康・栄養調査報告】
目標摂取量に対して、成人男性で3.5g、成人女性で3.4g不足している状態です。
食物繊維は、体になくてはならない栄養素というわけではありません。
しかし、「第6の栄養素」といわれるように、腸内環境の改善や生活習慣病の予防などに大変重要な働きをしています。
現在の平均摂取量と目標量の差から明らかなように、食物繊維の不足を積極的な摂取で補う必要があります。
食物繊維の摂取の目安
食物繊維には便通をよくする働きがあります。
食物繊維の健康的な摂取状況について、「1日1回、規則的な排便があること」が1つの目安になります。
この状態での人の排便量は、1日におよそ150gほどです。
この便量に見合った食物繊維を食事から摂取することが重要です。
まずは、1日当たりプラス3~4gの食物繊維摂取を目標にすることがすすめられます。
※1:生活習慣病の発症予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量。
食物繊維が多く含まれる食品
食物繊維は、穀類やイモ類、野菜、きのこ類、海藻類に多く含まれています。
穀類では、白米よりも玄米のほうが食物繊維が豊富です。
野菜では、ごぼうに特に食物繊維が豊富に含まれています。
きのこ類は、食物繊維以外にもミネラルやビタミンを多く含み、低カロリーであるということも嬉しい点です。
納豆は水溶性、不溶性の食物繊維をバランスよく豊富に含んでいるので、日々の食事に取り入れやすい食品としておすすめです。
キウイやブルーベリーなどの果物も食物繊維を多く含んでいます。
果物をデザートとして、いつもの食事に1品加えるだけでも手軽に食物繊維を摂ることができます。
また、普段の食事でも、食べ方や調理方法をひと工夫することで効率的に食物繊維を摂取することができます。
例えば、切干し大根はゆでた大根の2倍以上の食物繊維を含んでいます。
少しでも食物繊維の摂取量を増やせるよう、日常の食事の献立でも、食材や食品を意識することが重要です。
食物繊維を摂取できるおすすめの方法
不足している食物繊維量を補う献立メニューの考え方を以下にご紹介します。
主食の種類を変える
食物繊維量(お茶碗1杯150g相当)
- 白米 :0.45g
- 玄米 :2.1g
1日の食物繊維(お茶碗2.5杯/日)を4.2g増やすことができます。
食物繊維を多く含む副菜を1品(2品/日)追加する
副菜の食物繊維量(1品分)の例
- ブロッコリー(60g) :2.6g
- 菜の花(50g) :2.1g
- オクラ(40g) :2.0g
- エリンギ(40g) :1.7g
- えのきだけ(40g) :1.6g
- アボガド(90g) :4.8g
- 乾燥ひじき(5g) :2.2g
主食を白米から玄米に変えただけで食物繊維の1日当たりの摂取量不足を解消できます。
食物繊維を多く含む野菜や果物を追加すればさらに摂取量をアップすることができます。
献立メニューを上手に工夫し食物繊維不足は解消しましょう。
食物繊維が豊富に含まれる食べ物について詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。
食物繊維の働き

食物繊維は、人の消化酵素では消化することができません。
五大栄養素といわれる、炭水化物、脂質、タンパク質、無機質、ビタミンは消化酵素によって消化されますが、食物繊維は大腸まで消化されずに届きます。
現代人にとって腸内環境は、ストレスや偏った食生活、飲酒等で悪化しやすい環境条件が揃っており、加齢によっても腸内環境は悪化していきます。
食物繊維は消化されずに大腸まで届き、腸内環境を整えながらさまざまな働きをしてくれるのです。
腸を整える
食物繊維の摂取はお腹の調子を整えます。
腸の調子は、腸内細菌の善玉菌と悪玉菌のバランスにより決まります。
ストレスや偏った食生活、飲酒、加齢などによる善玉菌の減少が、腸内環境の悪化を招くのです。
腸内環境を整え、良くするためには、善玉菌を増やし悪玉菌を減らして、腸内細菌のバランスを変えることが必要です。
腸内の善玉菌を増やす食品には、以下のような食品があります。
- 食物繊維を含む食品
- ビフィズス菌や乳酸菌を含む食品
・ヨーグルトをはじめとする乳酸菌飲料
・納豆や漬物などの発酵食品
食物繊維は、便の体積を増やす材料になり、腸を刺激してぜん動運動を活発にし、便通を促進します。
食物繊維の摂取は同時に、腸内環境を整える腸内細菌の善玉菌を増やし、お腹の調子を整えます。
血糖値の上昇を抑える
食物繊維は、血糖値の急激な上昇を抑制します。
水溶性食物繊維の働きにより、糖の吸収速度が穏やかになり、食後の血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。
血中コレステロールを下げる
食物繊維には、血中のコレステロール濃度を下げる働きがあります。
水溶性食物繊維は、胃や腸内をゆっくり進みながら、コレステロールを吸着し、体外へ便と一緒に排出することにより、血中のコレステロール値を下げます。
生活習慣病の予防効果
食物繊維は生活習慣病を予防するための大事な栄養素です。
近年、食物繊維が糖尿病や動脈硬化などをはじめとする、生活習慣病の予防に効果があることが明らかになっています。
死因の多くを占める生活習慣病の予防に関わることから、食物繊維の重要性にさらに注目が集まっています。
食物繊維と生活習慣病の関係を以下に示します。
- 糖質や脂質の吸収を抑制することで脂質異常症、動脈硬化を予防
- 低カロリーで満腹感の得られやすい食品を摂取することで肥満を予防
- 食後の血糖値の急激な上昇を抑制することで糖尿病を予防
- 腸の有害物質の排出をすることで高血圧を予防
食物繊維と血糖値の関係について詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。
スポンサーリンク
水溶性食物繊維や不溶性食物繊維が不足すると?

現代の日本人は食物繊維の摂取量が目標値に届いておらず、ほとんどの人が食物繊維不足に陥っています。
食物繊維不足が深刻になると、以下のような病気にかかるリスクが上がります。
- 便の嵩が減り便秘になる
- 便秘になると痔や大腸がんになる
- 急激な血糖値上昇によって糖尿病になる
食事に気を遣わずに外食やファストフードなどで、食事を取ることが多いと野菜やくだもの、豆類を食べることが少なく、食物繊維不足に陥りやすいです。
スポンサーリンク
水溶性食物繊維や不溶性食物繊維を過剰摂取すると?

健康やダイエットに良いからと食物繊維を過剰に摂取すると、身体に悪影響を及ぼす可能性があります。
水溶性食物繊維は水分を含んでジェル状になり、エネルギーの吸収を抑える効果があります。
しかし、水溶性食物繊維によるエネルギー吸収を抑える働きが過剰になると、ビタミンやミネラルなど身体に必要な栄養素の吸収が阻害される可能性があります。
また、不溶性食物繊維の過剰摂取では便の嵩が増えすぎて、腸内で便をうまく運ぶことができず、便秘になることがあります。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の過剰摂取はお腹の調子を乱すことがあるので、まずは目標量摂取を目指してみましょう。
スポンサーリンク
食物繊維をうまく摂取して便秘を解消しよう

食物繊維は便秘改善に役立つ成分です。
食物繊維で便秘を解消するためのポイントをご紹介します。
水溶性食物繊維と腸の関係
水溶性食物繊維が便秘改善に役立つのは、便を柔らかくする作用があるためです。
一般的に、便秘の方は腸内で便が硬くなっています。
理由は、腸内に長くとどまる内に、便の中から水分が抜けてしまうためです。
水溶性食物繊維は、硬くなった便に水分を与えることで、ゼリー状にします。
すると便がスムーズに排出されやすくなるため、結果として便秘解消が期待できるというわけです。
不溶性食物繊維と腸の関係
不溶性食物繊維が便秘解消に役立つのは、腸内で膨張する性質があるためです。
具体的には、不溶性食物繊維は水分を吸うことで腸内で膨らみます。
不溶性食物繊維が腸内で膨張すると、2つの効果が期待できます。
1つめは、便のカサが増えることです。
2つめは、腸が適度に刺激されることです。
水分を含んだ不溶性食物繊維は、腸内にたまった便を巻き込みながら大きくなります。
つまり、ずっと腸に溜まっていた便が排出されやすい状態になるのです。
便が大きくなると、腸が内側から適度に刺激されます。
適度な刺激は腸の動きを活発化させるため、便がスムーズに排出されやすくなります。
便秘解消に最適な食物繊維の摂り方
便秘解消を狙うには、適量の食物繊維を摂ることが大切です。
あわせて、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスも大切にしましょう。
食物繊維をむやみに摂ると、かえって便通が乱れることがあるためです。
たとえば、不溶性食物繊維を摂りすぎると、かえって便秘が悪化することがあります。
理由は、不溶性食物繊維は水分に溶けにくい性質があるためです。
摂取しすぎると便が硬くなって、かえって腸内で詰まりやすくなるのです。
反対に水溶性食物繊維の摂りすぎは、下痢を引き起こすおそれがあります。
便通を正常に整えるには、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランス良く摂ることが大切です。
具体的には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維は1:2のバランスを保ちましょう。
便秘を解消するには、食物繊維と一緒に乳酸菌を摂ることも大切です。
乳酸菌は善玉菌の1種で、腸内環境を整える作用があります。
乳製品のエサは食物繊維です。
つまり食物繊維と一緒に摂ると、乳酸菌が活発化しやすくなるのです。
乳酸菌が豊富な食品は、ヨーグルトなどの発酵食品が代表的です。
ダイエットと食物繊維

毎日の食事で食物繊維をしっかり取ることは、ダイエット成功の鍵となります。
食物繊維をしっかり取ることで、便が出るようになり身体に不要なものを身体の外に排出してくれます。
さらに、太ってしまう原因でもある急激な血糖値の上昇を抑えることができます。
日本人の食物繊維摂取量の平均は約15gであり、目標量より少ないのでいつもの食事に食物繊維食材を足す必要があります。
また、食べるのが面倒くさくてサプリメントで補うと、過剰摂取になってしまい必要栄養素が吸収できない可能性があるので注意が必要です。
スポンサーリンク
食物繊維の水溶性・不溶性まとめ

ここまで、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違いや食物繊維の摂取量を中心にお伝えしてきました。
- 水溶性食物繊維はジェル状になり血糖値の上昇を緩やかにして、不溶性食物繊維は便の嵩を増やして腸の動きを活発にする
- 1日の食物繊維の目標摂取量は成人男性で21g以上、成人女性で18g以上
- 食物繊維の整腸作用や栄養をゆっくり吸収する作用によってダイエットのサポートになる
これらの情報が、皆様のダイエットや健康増進のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※この記事はアフィリエイト広告を含んでおります












.png)