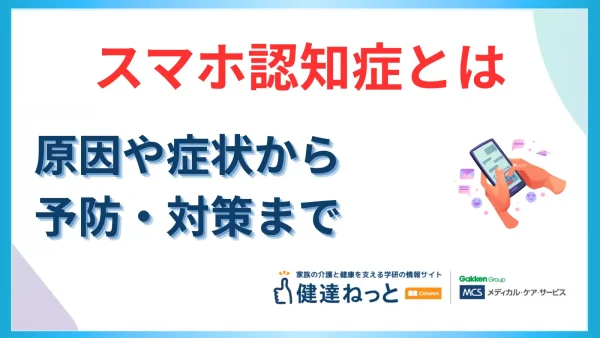- 「最近、人の名前がすぐに出てこない…」
- 「仕事や勉強に集中できず、ミスが増えた気がする」
- 「ちょっとしたことでも、すぐにスマホで調べてしまう」
このようなお悩みを抱えていませんか。
その症状、もしかしたらテレビやメディアで話題の「スマホ認知症」のサインかもしれません。
現代社会で急速に広がるスマホ認知症は、2025年6月に全国初となる「スマホ認知症外来」が開設されたことで、その深刻性がより一層注目されています。
当サイト「健達ねっと」を運営するメディカル・ケア・サービス株式会社では、全国の学校で認知症に関する出前授業を行うなど、正しい知識の普及に努めています(認知症・介護に関するアンケート調査)。
この記事では、スマホ認知症に関する漠然とした不安を解消し、ご自身の脳の健康を守るための具体的な一歩を踏み出せるよう、以下の点を網羅的に解説します。
- スマホ認知症の具体的な症状とセルフチェックリスト
- 脳機能が低下する3つのメカニズム
- 放置した場合に起こりうる4つの重大なリスク
- 今日から実践できる5つの予防・改善策
スマートフォンとの付き合い方を見直し、心身ともに健やかな毎日を取り戻しましょう。
スポンサーリンク
スマホ認知症とは?急増する現代病の正体
スマホ認知症とはどのような状態を指すのでしょうか。
ここでは、その代表的な症状から、混同されやすい若年性認知症やうつ病との違い、関連する用語まで、スマホ認知症の全体像を詳しく解説します。
スマホ認知症の代表的な症状
スマホ認知症の症状は、脳の機能低下に伴い多岐に渡ります。
特に、記憶力や集中力の低下は、日常生活や仕事に直接的な影響を及ぼすため注意が必要です。
これらの症状は、スマートフォンから受け取る情報量が脳の処理能力を超えてしまうことで発生します。
具体的な症状の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 人の名前や漢字など、知っているはずのことが思い出せない
- 新しい情報を覚えたり、物事の段取りを考えたりするのが苦手になる
- ケアレスミスが増え、作業効率が落ちる
- 感情の起伏が激しくなり、イライラしやすくなる
このような脳機能の低下は、詳しい原因が解明されつつある記憶障害のメカニズムとも共通点があり、軽視できないサインといえます。
正式病名は「スマホ認知症」ではない
「スマホ認知症」という名称は広く浸透していますが、これは医学的な正式病名ではありません。
あくまで、スマートフォンの過度な使用によって認知症に似た症状が現れる状態を指す、いわば通称です。
医学的事実として、DSM-5(米国精神医学会診断基準)やICD-11(WHO国際疾病分類)には記載がなく、日本認知症学会の認知症診断ガイドラインにも未記載です。
医療や研究の現場では、この状態を理解するために、以下のような様々な用語が使われています。
- デジタル認知症
- スマホ脳過労
- 情報過多症候群
認知症専門医の長田乾医師も著書で指摘している通り、認知機能には生活習慣や趣味など多様な要素が影響します(出典:健達ねっとSHOP)。
スマホ認知症も、単にスマートフォンの使いすぎというだけでなく、生活全体を見直す視点から多角的に捉えることが大切です。
若年性認知症やうつ病との違い
物忘れや意欲低下といった症状は、若年性認知症やうつ病とも共通するため、不安に感じる方も少なくありません。
しかし、スマホ認知症との間には、原因や症状の進行、回復の可能性において明確な違いがあります。
それぞれの特徴を、以下の表で比べてみましょう。
| 特徴 | スマホ認知症 | 若年性認知症 | うつ病 |
|---|---|---|---|
| 主な原因 | スマートフォンの過剰使用による脳疲労 | 脳の病的な変化(脳血管障害など) | 脳の機能障害、ストレス |
| 症状の特徴 | 状況により変動、物忘れは多い | 症状が持続・進行する | 強い抑うつ気分、興味の喪失 |
| 回復の可能性 | 原因除去で改善の可能性が高い | 進行を遅らせる治療が中心 | 適切な治療で回復可能 |
スマホ認知症の最大の特徴は、スマートフォンの使用を控えることで症状が改善する「可逆性」にある点です。
ただし、自己判断は禁物であり、症状が続く場合は専門医への相談が重要です。
若年性認知症の症状と特徴についても知っておくと、より冷静な判断につながります。
デジタル認知症やスマホ依存症との関係
スマホ認知症は、より広い概念である「デジタル認知症」の一種と位置づけられます。
デジタル認知症がパソコンやタブレットを含むデジタル機器全般の使用を原因とするのに対し、スマホ認知症は特にスマートフォンに起因する症状を指します。
また、「スマホ依存症」とも密接な関係があります。
スマホ依存症は、スマートフォンがないと不安になる精神的な依存状態を指し、これがスマートフォンの長時間利用につながり、結果としてスマホ認知症の症状を引き起こすケースが多く見られます。
- スマホ依存症(原因):精神的な依存状態
- スマホ認知症(結果):脳機能が低下した状態
つまり、根本的な問題はデジタル機器との付き合い方にあり、依存状態が脳の健康を損なうリスクを高めているといえるでしょう。
スポンサーリンク
あなたのスマホ脳は大丈夫?スマホ認知症セルフチェック
ご自身のスマートフォンとの付き合い方が、脳にどのような影響を与えているか気になりませんか。
ここでは、専門家の知見を元にしたセルフチェックリストを用意しました。
ご自身の状態を客観的に把握してみましょう。
日本初のスマホ認知症外来を開設した金町駅前脳神経内科の内野勝行院長が示す8項目のうち、3つ以上当てはまると要注意とされています。
記憶力・思考力に関する項目
- 人の名前や地名、物の名前がすぐに出てこない
- 漢字や簡単な英単語が思い出せない
- 物事の段取りを立てるのが苦手になった
- 調べ物をしても、内容が頭に入りにくい
これらの項目は、脳の情報処理能力が低下しているサインです。
すぐに検索する癖がつくと、脳が自ら記憶を引き出す機能が衰えてしまいます。
コミュニケーションに関する項目
- 相手の話の意図が理解しにくい、または聞き返すことが増えた
- 自分の考えを言葉でうまく表現できない
- 対面での会話より、SNSなど文字でのやり取りを好む
当社の認知症教育を担当する専門家も、人との直接的な対話の重要性を指摘しています(出典:認知症教育の出前授業)。
文字だけのコミュニケーションは、脳が表情や声のトーンといった非言語情報を処理する機会を奪い、共感力や思考力を低下させる可能性があります。
情緒・体調に関する項目
- 以前より怒りっぽくなった、あるいは涙もろくなった
- 夜中に目が覚める、寝つきが悪いなど睡眠に問題がある
- 慢性的な首や肩のこり、頭痛、眼精疲労がある
心と体は密接につながっています。
スマートフォンの長時間利用による心身へのストレスが、自律神経の乱れや体調不良として現れることも少なくありません。
行動に関する項目
- スマートフォンが手元にないと、理由もなく不安や焦りを感じる
- 食事中や誰かといる時でも、無意識にスマートフォンを触ってしまう
- 通知が来ていないか、何度も画面を確認する
これらの行動は、スマートフォンへの依存傾向を示唆しています。
無意識の行動が常態化している場合は、特に注意が必要です。
スマホ認知症が起こる3つの主な原因
なぜスマートフォンの使いすぎが、認知症のような症状を引き起こしてしまうのでしょうか。
その背景には、現代のデジタル社会特有の脳への負荷が関係しています。
ここでは、その主な3つの原因を科学的な視点から解説します。
情報過多による「前頭葉」の脳疲労
スマホ認知症の最大の原因は、脳が処理しきれないほどの情報に常に晒されることによる「脳疲労」です。
特に、思考や判断、感情のコントロールを司る「前頭葉」への負担が深刻です。
スクロールするだけで次々と流れ込んでくる膨大な情報は、脳の整理・記憶機能を麻痺させてしまいます。
このような状態は、精神的なストレスが脳に与える影響とも類似しており、放置すれば記憶力の低下に直結する可能性があります。
詳しくは「ストレスが記憶に与える影響」の記事もご参照ください。
ブルーライトによる睡眠の質の低下
「寝る直前までスマートフォンを見ている」という方は多いのではないでしょうか。
スマートフォン画面が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制する作用があります。
これにより、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりと、睡眠の質が著しく低下します。
睡眠は、脳が日中に得た情報を整理し、疲労を回復させるための重要な時間です。
医学的研究でも、良質な睡眠が脳機能維持に不可欠であることが強調されています。
睡眠不足が続くと、脳の老廃物がうまく除去されず、日中の集中力や思考力の低下につながります。
コミュニケーション能力の偏りと低下
SNSやメッセージアプリの普及により、私たちのコミュニケーションはテキスト中心に偏りがちです。
手軽で便利な一方、この変化が脳機能に思わぬ影響を与えています。
対面での会話では、言葉だけでなく相手の表情、声のトーン、仕草など五感を使って膨大な情報を処理しています。
しかし、テキストコミュニケーションでは、この複雑な情報処理の機会が失われます。
この結果、脳の社会性や共感性を司る機能が使われずに衰え、相手の感情を汲み取ったり、その場の空気を読んだりする能力が低下する可能性があるのです。
スマホ認知症がもたらす重大な4つのリスク
「一時的な不調だろう」とスマホ認知症のサインを軽視していると、心身に様々な悪影響が及ぶ可能性があります。
ここでは、放置した場合に考えられる4つの重大なリスクについて解説します。
早期に対策を講じることの重要性を理解しましょう。
日常生活への支障
記憶力や集中力の低下は、日常生活のあらゆる場面で支障をきたします。
| 場面 | 具体的な支障の例 |
|---|---|
| 仕事 | 会議の内容が頭に入らない、ケアレスミスが増える、業務効率が低下する |
| 学業 | 授業に集中できない、暗記が苦手になる、成績が低下する |
| 家事 | 献立を考えられない、買い忘れが増える、料理の段取りが悪くなる |
| 対人関係 | 約束を忘れる、会話が噛み合わない、友人関係が疎遠になる |
このようなパフォーマンスの低下が続くと、自己肯定感の喪失にもつながりかねません。
睡眠障害やうつ病など精神疾患への移行
ブルーライトによる睡眠の質の低下や、SNSでの他者との比較による精神的ストレスは、本格的な睡眠障害やうつ病の引き金となる可能性があります。
特に、脳が十分に休息できない状態が続くと、セロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れ、気分の落ち込みや意欲の低下といったうつ症状が現れやすくなります。
うつ病による記憶障害についての知識も、リスクを理解する上で役立ちます。
身体的な不調
スマホ認知症は、脳だけでなく身体にも不調をもたらします。
長時間同じ姿勢で画面を見続けることで、首や肩に過度な負担がかかり、「ストレートネック(スマホ首)」を引き起こします。
ストレートネックは、慢性的な頭痛やめまい、吐き気の原因となるほか、自律神経の乱れにもつながることが指摘されています。
また、画面の凝視は眼精疲労やドライアイの直接的な原因にもなります。
将来的な本物の認知症リスクの上昇
現時点で、スマートフォンの使いすぎが直接的にアルツハイマー型認知症などを発症させるという医学的証明はありません。
しかし、スマホ認知症の原因となる生活習慣、例えば「運動不足」「睡眠不足」「社会的孤立」などは、将来的な認知症の発症リスクを高める要因として知られています。
スマートフォンに依存した生活を続けることは、間接的に本物の認知症への扉を開いてしまう危険性をはらんでいるのです。
今すぐできる!スマホ認知症の治し方と予防策
スマホ認知症は、生活習慣を見直すことで予防・改善が可能です。
ここでは、誰でも今日から始められる5つの具体的な方法を紹介します。
当社の科学的介護手法「MCSケアモデル」のアプローチも参考に、脳をいたわる生活を始めましょう(出典:MCSケアモデル)。
1.スマートフォンと距離を置くデジタルデトックスを心がける
最も効果的なのは、物理的・心理的にスマートフォンと距離を置く「デジタルデトックス」です。
脳を情報過多の状態から解放し、休息時間を与えることが目的です。
具体的なアクションプランは以下の通りです。
- 時間を決める:「食事中」「入浴中」「就寝1時間前」はスマートフォンを触らない。
- 場所を決める:寝室やトイレにスマートフォンを持ち込まない。
- 通知をオフにする:緊急性のないアプリの通知は切り、受動的な情報受信を減らす。
いきなり全てを実践するのが難しければ、ひとつからでも構いません。
効果的なデジタルデトックス方法を参考に、自分に合ったやり方を見つけるのが継続のコツです。
2.脳を能動的に使えるように情報収集の方法を変える
スマートフォンでの検索は非常に便利ですが、頼りすぎると脳が「考える」ことをやめてしまいます。
意識的に脳を能動的に使う機会を増やしましょう。
- まず自分で考える:知らない言葉や漢字が出てきても、すぐに検索せず、まずは記憶を辿ってみる。
- 紙媒体に触れる:本や新聞、雑誌を読む。順序立てて情報を追うことで、思考力や読解力が鍛えられます。
- 道は人に聞く:外出先で道に迷ったら、地図アプリに頼る前に、近くの人に尋ねてみる。
このような小さな工夫が、脳の「検索機能」を再活性化させるトレーニングになります。
3.五感が刺激されるようにコミュニケーションを増やす
テキストだけでは得られない、五感を使ったコミュニケーションを意識的に増やしましょう。
当社の実践報告会でも、五感を刺激する対話が認知機能に良い影響を与える事例が多数報告されています(出典:認知症ケア実践・研究報告会)。
- 用件はメッセージでなく電話で伝える。
- 友人や家族と、直接会って食事や会話を楽しむ時間を作る。
- 趣味のサークルや地域のイベントに参加し、新しい人間関係を築く。
相手の表情を見ながら話すことで、脳の共感性を司る部分が活性化し、豊かな感情や思考を取り戻すきっかけになります。
4.良質な睡眠を確保する
脳の健康維持に、質のよい睡眠は不可欠です。
睡眠中に脳は情報を整理し、心身の疲労を回復させます。
メラトニンの分泌を妨げないよう、就寝前の環境を整えることが重要です。
- 就寝1~2時間前には、スマートフォンやPC、テレビの使用をやめる。
- 寝室の照明を暖色系の暗めのものにする。
- 朝起きたらカーテンを開け、太陽の光を浴びて体内時計をリセットする。
睡眠の質を改善する具体的な方法を実践し、脳がしっかりと休まる環境を作りましょう。
5.適度な運動を取り入れる
運動は、脳の血流を促進し、神経細胞の働きを活性化させる効果があります。
特に、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、記憶を司る「海馬」の機能を高めることが研究でわかっています。
- 週に2〜3回、30分程度の有酸素運動を習慣にする。
- エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やす。
- 家族や友人と一緒に運動すると、継続しやすく、コミュニケーションの機会にもなる。
認知症予防に効果的な運動方法を参考に、楽しみながら続けられる運動を見つけてみてください。
また、認知機能を改善する方法として、認知機能を改善するサプリメントを取り入れるのもひとつです。
健達ねっとでは、認知機能を改善するサプリメントの販売も行っています。
食生活はバランスよく主食・主菜・副菜を取るのが基本ですが、栄養を補助するものとして取り入れてみるのもよいでしょう。
スマホ認知症に関してよくある質問
最後に、スマホ認知症について多くの方が抱く疑問にお答えします。
専門家の見解や最新の情報を元に、不安や疑問を解消していきましょう。
スマートフォンは1日何時間以上使うと危険?
「1日に何時間以上使うと危険」という明確で統一された基準は、現在のところありません。
しかし、いくつかの研究が目安を示唆しています。
例えば、東北大学の川島隆太教授の研究では、スマートフォン等の利用が1時間を超えると学力が明確に低下し始め、3時間を超える子どもたちの脳の発達に影響が見られたと報告されています。
時間だけでなく、どのような目的で、どのような姿勢で使うかという「使い方」も重要です。
「だらだらと目的なく見続ける」時間が長いほど、脳への負担は大きくなります。
10代や子どももスマホ認知症になる可能性はある?
はい、可能性は十分にあります。
むしろ、脳が発達段階にある10代や子どもの方が、スマートフォンの過剰使用による影響を受けやすいと考えられています。
前述の東北大学の研究でも、インターネットの長期利用が子どもの脳の発達、特に言語能力や記憶を司る部分に悪影響を及ぼす可能性が示されました。
当社の認知症教育の出前授業でも、子どもたちのデジタルリテラシー向上の重要性を伝えており、各家庭で利用時間や場所のルールを決めることが極めて重要です。
症状が改善しないときはどこの病院(何科)を受診すればいい?
セルフケアを試みても症状が改善しない、あるいは日常生活に深刻な支障が出ている場合は、専門の医療機関を受診しましょう。
2025年6月に開設された「スマホ認知症外来」のような専門外来が最も望ましいですが、お近くにない場合は以下の診療科が相談先となります。
- 脳神経内科・脳神経外科:物忘れや頭痛など、脳機能に関する症状が強い場合。
- 心療内科・精神科:不安や気分の落ち込み、不眠など、精神的な症状が強い場合。
自己判断で「ただの疲れ」と放置せず、専門家による適切な診断を受けることが大切です。
まとめ
この記事では、現代病ともいえる「スマホ認知症」について、その症状から原因、リスク、そして具体的な対策までを網羅的に解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- スマホ認知症の正体:スマートフォンの過剰使用による脳疲労が原因で起こる、認知症に似た症状。正式な医学的病名ではなく、生活改善で回復の可能性がある。
- 主な原因:「情報過多による脳疲労」「ブルーライトによる睡眠不足」「コミュニケーションの偏り」の3つ。
- 放置するリスク:日常生活への支障、精神疾患への移行、将来的な認知症リスクの上昇など、心身に重大な影響を及ぼす。
- 有効な対策:デジタルデトックス、能動的な情報収集、対面コミュニケーション、良質な睡眠、適度な運動が効果的。
スマートフォンは私たちの生活に欠かせない便利なツールですが、その一方で、私たちの脳を静かに蝕む危険性もはらんでいます。
大切なのは、スマートフォンに「使われる」のではなく、主体的に「使いこなす」意識を持つことです。
この記事で紹介したセルフチェックや予防策を参考に、今日からご自身のスマートフォンとの付き合い方を見直してみてはいかがでしょうか。
その小さな一歩が、あなたの脳の健康を守り、より豊かで充実した未来へとつながっていくはずです。