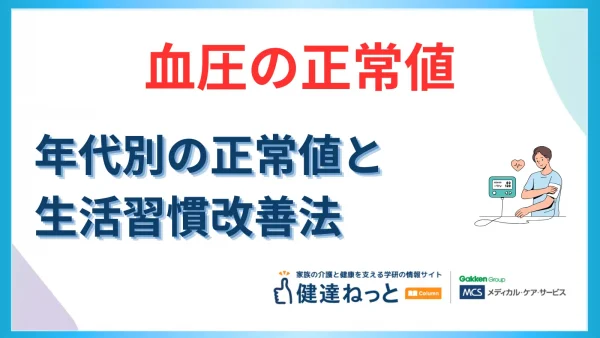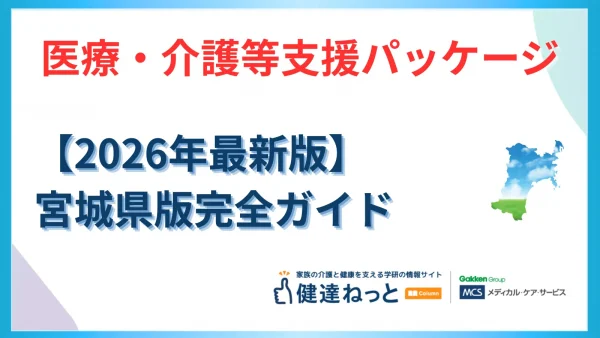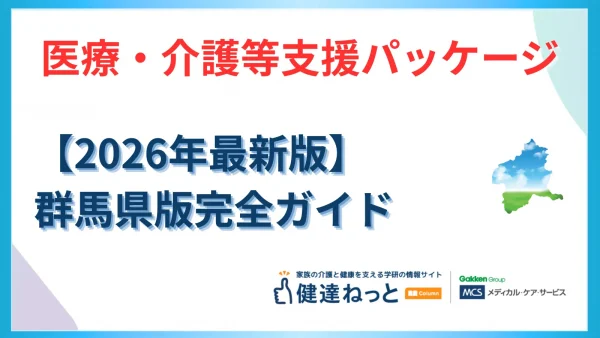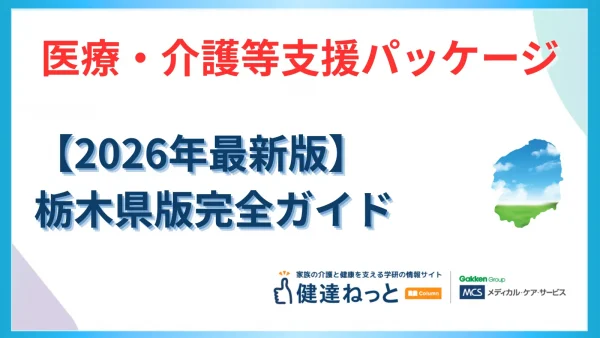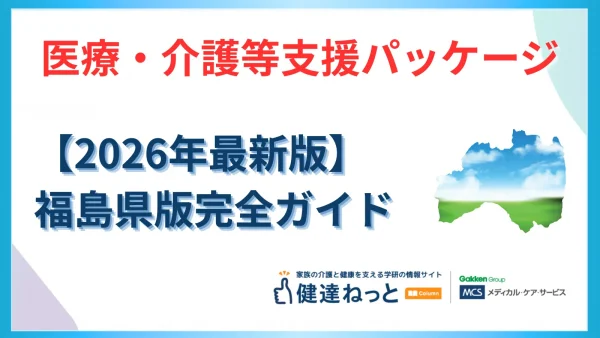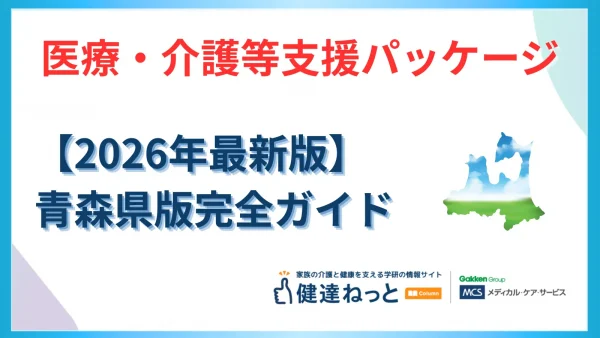- 「いつまでも健康で、穏やかな毎日を送りたい」
- 「病気でやりたいことを諦めたくない」
- 「大切な家族に心配をかけず、自分らしい人生を歩みたい」
健康診断の結果を見て、血圧の数値に一喜一憂しながら、このようにお考えではないでしょうか。
血圧は、私たちの健康状態を映し出す重要なバロメーターです。
しかし、その数値を正しく理解し、適切に管理できている人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、血圧に関するあなたの疑問や不安を解消します。
日本高血圧学会の最新ガイドラインに基づき、以下のポイントをどこよりも分かりやすく解説します。
- 一目で分かる血圧の正常値と高血圧の基準
- 20代から70代以上まで、年代・性別ごとの平均値
- 家庭でできる、血圧の正しい測定方法
- 血圧が高くなる原因と、放置するリスク
- 今日から始められる生活習慣の改善法
この記事を読めば、ご自身の血圧と正しく向き合い、未来の健康を守るための具体的な一歩を踏み出せます。
さあ、一緒に学んでいきましょう。
スポンサーリンク
【結論】一目で分かる!血圧の正常値と高血圧の基準
まず結論からお伝えします。
血圧の基準を正しく知ることは、健康管理のスタートラインです。
日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」では、測定場所によって基準値が異なります。
ご自身の数値を客観的に判断するために、まずはこの基準をしっかりと把握しましょう。
診察室血圧と家庭血圧の基準値一覧
血圧の正常値を判断する上で最も大切なのは、「診察室で測った血圧」と「家庭で測った血圧」の基準値が違うという点です。
緊張などから病院で測ると高めに出る傾向があるため、家庭血圧の基準は少し低く設定されています。
▼血圧値の分類(成人)
| 分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) |
|---|---|---|
| 正常血圧 | 収縮期120未満 かつ 拡張期80未満 | 収縮期115未満 かつ 拡張期75未満 |
| 正常高値血圧 | 120~129 かつ 80未満 | 115~124 かつ 75未満 |
| 高値血圧 | 130~139 かつ/または 80~89 | 125~134 かつ/または 75~84 |
| 1度高血圧 | 140~159 かつ/または 90~99 | 135~144 かつ/または 85~89 |
| 2度高血圧 | 160~179 かつ/または 100~109 | 145~159 かつ/または 90~99 |
| 3度高血圧 | 180以上 かつ/または 110以上 | 160以上 かつ/または 100以上 |
高血圧の診断基準は、診察室血圧が140/90mmHg以上、家庭血圧が135/85mmHg以上です。
この基準を元にご自身の血圧を確認してみてください。
家庭血圧が診察で優先される理由
現在の高血圧診療では、診察室の血圧よりも家庭で測定した血圧の値が重視される傾向にあります。
なぜなら、家庭でのリラックスした状態で繰り返し測定した血圧の平均値の方が、その人の本来の血圧をより正確に反映していると考えられるためです。
この考え方により、以下のような特殊な状態も把握できるようになりました。
- 白衣高血圧:家庭では正常なのに、診察室でのみ血圧が高くなる状態。
- 仮面高血圧:診察室では正常なのに、家庭では血圧が高い状態。自覚しにくく、心臓や血管へのリスクは持続的な高血圧と同等とされるため特に注意が必要です。
より正確な健康状態を把握するために、家庭での血圧測定を習慣にすることが非常に大切です。
「高値血圧」から放置すべきではない危険信号
上の表で「高値血圧」に分類された方は、まだ高血圧とは診断されませんが、決して安心はできません。
高値血圧は、将来的に高血圧症へ移行する可能性が高い「予備軍」といえる状態です。
この段階から生活習慣を見直すことで、本格的な高血圧への進行を防ぎ、薬物療法を回避できる可能性が高まります。
いわば、体からの「イエローカード」であり、生活を見直す絶好の機会と捉えましょう。
具体的な対策を早期に始めることが、未来の健康を守る鍵となります。
スポンサーリンク
年代・性別ごとの血圧正常値を徹底解説
絶対的な基準値だけでなく、「自分の年代ではどのくらいの数値が一般的なのだろう?」と気になる方も多いでしょう。
ここでは、年代や性別の平均値を見ていきます。
ご自身の数値と比べることで、健康状態をより深く理解するきっかけになります。
20~70代以上の男女別の血圧平均値
厚生労働省の調査によると、血圧の平均値は年齢とともに上昇する傾向が見られます。
また、一般的に男性の方が女性よりも高い傾向にありますが、女性も更年期以降は数値が上昇しやすくなります。
▼年代・性別ごとの収縮期血圧(上の血圧)の平均値
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20~29歳 | 122.2 mmHg | 112.8 mmHg |
| 30~39歳 | 124.8 mmHg | 115.8 mmHg |
| 40~49歳 | 129.9 mmHg | 120.5 mmHg |
| 50~59歳 | 134.3 mmHg | 126.2 mmHg |
| 60~69歳 | 137.9 mmHg | 134.4 mmHg |
| 70歳以上 | 136.2 mmHg | 135.1 mmHg |
ただし、これらはあくまで平均値です。
大切なのは、ご自身の血圧が「正常血圧」の範囲内に保たれているかどうかです。
年齢とともに血圧が上がりやすくなる理由
なぜ、年齢を重ねると血圧は上がりやすくなるのでしょうか。
主な原因は、血管の「老化」にあります。
若い頃の血管はしなやかで弾力性がありますが、加齢とともに徐々に硬く、もろくなっていきます。
これが「動脈硬化」とよばれる状態です。
- 弾力性の低下:血管が硬くなると、心臓が血液を送り出す際の圧力をうまく吸収・分散できません。
- 血管が狭くなる:血管の内壁にコレステロールなどが溜まり、血液の通り道が狭くなります。
硬く狭くなった血管に血液を流すため、心臓はより強い力で血液を押し出す必要があり、結果として血圧が上昇するのです。
このような加齢に伴う身体の変化については、健達ねっとから出版されている書籍『イラストで分かる 高齢者のからだ図鑑』で詳しく解説されています。
現役理学療法士による400点以上のイラストで、血管の老化などが視覚的に理解でき、血圧管理の重要性への納得感が深まります。
低血圧の基準と対処の必要性
高血圧とは逆に、血圧が低い「低血圧」で悩んでいる方もいるでしょう。
実は、高血圧のような明確な診断基準は低血圧にはありません。
一般的に、世界保健機関(WHO)では収縮期血圧(上の血圧)が100mmHg以下、拡張期血圧(下の血圧)が60mmHg以下を目安としています。
大切なのは、数値そのものよりも症状の有無です。
以下のリストに当てはまる症状がなく、日常生活に支障がなければ、体質的なものとして過度に心配する必要はないといわれています。
- 立ちくらみ、めまい
- 朝、すっきりと起きられない
- 頭痛、肩こり
- 疲れやすい、だるい
- 吐き気
しかし、これらの症状で生活に支障が出ている場合や急に血圧が低くなった場合は、何らかの病気が隠れている可能性もあるため、一度医療機関に相談しましょう。
近年、サルコペニアという疾患の認識が広まりつつあります。サルコペニアは老化現象の1種で、進行すると歩行困難や寝たきりに発展します。老化自体は避けられないものの、サルコペニアの予防で健康寿命を延ばすことは可能です。それではサル[…]
毎日できる!健康管理の第一歩となる正しい家庭血圧の測定方法
正確な血圧管理は、正しい測定方法を実践することが大前提です。
せっかく毎日測っていても、方法が間違っていては意味がありません。
ここでは、誰でも簡単に実践できる正しい測定のポイントを解説します。
ご自身の測定方法と比べながら確認してみてください。
【血圧計の選び方】手首式よりも「上腕式」がオススメ
家庭用血圧計には、腕に巻く「上腕式」と手首に巻く「手首式」があります。
手軽さから手首式を選ぶ方もいますが、より正確な測定のためには上腕式が推奨されています。
その理由は以下の通りです。
- 測定部位:上腕の動脈は心臓の高さに近く、血圧が安定します。手首は心臓から遠く、体の動きや手首の角度で数値が変動しやすくなります。
- 正確性:日本高血圧学会をはじめ、多くの専門機関が上腕式血圧計の使用を推奨しています。
これから購入する方や買い替えを検討している方は、ぜひ「上腕式」を選びましょう。
【最適な時間】朝と夜どちらに測るべきか
血圧は一日の中でも常に変動しています。
そのため、決まった時間に測定して変化のパターンを把握することが重要です。
測定のタイミングは、原則として1日2回、朝と夜に行います。
- 朝の測定:起床後1時間以内で、排尿後、朝食・服薬前に測定します。
- 夜の測定:就寝前に測定します。入浴や飲酒の直後は避けましょう。
この2回の測定を習慣にすることで、早朝高血圧や夜間高血圧など、診察だけでは見つけにくい異常の発見につながります。
【測定手順】正しい手順7つのポイント
正確な数値を測るための、具体的な手順を確認しましょう。
以下の7つのポイントを意識するだけで、測定の精度が格段に上がります。
- 静かな環境:テレビなどを消し、リラックスできる静かな部屋で測ります。
- 快適な室温:寒すぎたり暑すぎたりすると血圧は変動します。快適な室温を保ちましょう。
- 1~2分の安静:椅子に座って1~2分間安静にし、心と体を落ち着かせます。
- 正しい姿勢:背もたれのある椅子に深く座り、足は組まずに床につけます。
- 腕帯(カフ)を正しく巻く:カフの中心が心臓の高さになるように、腕をテーブルなどに乗せます。素肌か薄手のシャツの上に、指1本が入る程度の強さでぴったり巻きます。
- 測定中は動かない・話さない:測定中は体を動かしたり、会話したりしないようにします。
- 1機会に2回測定:1回の機会に2回測定し、その平均値を記録するのが望ましいとされています。
この手順を守ることが、信頼できるデータを得るための鍵です。
【禁止事項】測定前に避けるべき行動
血圧は些細なことでも変動します。
測定前に以下の行動を取ると、本来の血圧よりも高い数値が出てしまう可能性があります。
正しい値を把握するため、これらの行動は避けましょう。
- 喫煙:タバコを吸うと一時的に血圧が上がります。測定前30分は避けましょう。
- 飲酒:アルコールは血圧を変動させます。
- カフェイン摂取:コーヒー、紅茶、緑茶などのカフェイン飲料も血圧を上げる作用があります。
- 入浴・シャワー:入浴直後は血圧が変動しやすいので、時間を空けてから測定します。
- 運動や急な動作:体を動かした直後は血圧が上がっています。安静にしてから測りましょう。
高齢者の方で、嚥下機能の低下から測定中にむせや咳が出てしまう場合は、新潟医療福祉大学の西尾正輝教授が開発した「ノドトレ」を日頃から実践するのもオススメです。
嚥下機能が安定することで、測定時も安静を保ちやすくなり、より正確な数値の把握につながります。
【活用法】測定結果の記録と効果的な活用法
測定した血圧は、必ず記録に残しましょう。
記録することで、血圧の長期的な変化や傾向が分かり、治療や生活習慣改善の効果を客観的に評価できます。
記録のポイントは以下の通りです。
- 血圧手帳やアプリを利用する:測定した日時、収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数を記録します。体調の変化や気になる症状もメモしておくと役立ちます。
- すべての値を記録する:数値が高いからといって記録しなかったり、低い値だけを記録したりせず、測定したすべての値を正直に書き留めましょう。
- 診察時に持参する:記録したデータは、医師が診断や治療方針を決める上で非常に重要な情報となります。忘れずに持参するようにしましょう。
日々の記録は、あなたと医師をつなぐ大切なコミュニケーションツールになるのです。
血圧が平均値から逸脱する(血圧が高くなる)7つの主な原因
「なぜ自分の血圧は高いのだろう?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
高血圧の約9割は、特定の病気が原因ではない「本態性高血圧」とよばれ、様々な生活習慣や遺伝的要因が複雑に絡み合って発症します。
ご自身の生活を振り返りながら、当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
食塩(塩分)の過剰摂取
高血圧の最大の原因といわれるのが、食塩の摂りすぎです。
体内の塩分濃度が上がると、それを薄めるために体は水分を溜め込みます。
その結果、循環する血液の量が増え、血管の壁にかかる圧力、つまり血圧が上昇します。
日本高血圧学会が推奨する1日の食塩摂取量の目標は6g未満です。
麺類の汁を飲まない、漬物や加工食品を控える、香辛料や出汁を活用するなどの工夫で、無理なく減塩を始められます。
肥満(特に内臓脂肪)
肥満、特に内臓脂肪が増えると、血圧を上げるホルモンが分泌されたり、交感神経の働きが活発になったりして血圧が上昇します。
また、インスリンの働きが悪くなることで、腎臓での塩分排泄が滞り、血圧を上げる原因にもなります。
まずは、ご自身のBMI(体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m)が25未満になることを目指しましょう。
少しの減量でも、血圧の低下が期待できます。
運動不足
運動不足は、肥満の原因になるだけでなく、血圧に直接的な影響を与えます。
運動をすると、体内で血管を広げる物質が作られたり、自律神経のバランスが整ったりすることで、血圧が下がりやすくなります。
逆に運動が不足すると、血流が悪くなり、心臓はより強い力で血液を送り出す必要が出てくるため、血圧が上がりやすくなるのです。
日々の生活に意識的に運動を取り入れることが重要です。
過度な飲酒や喫煙
習慣的な飲酒は、血圧を上昇させることが分かっています。
アルコールは一時的に血管を広げ血圧を下げますが、飲み続けると交感神経を刺激し、心拍数を上げて血圧を上昇させます。
節酒の目安は、男性で1日あたり純アルコール20~30ml以下(ビール中瓶1本程度)、女性はその半分以下です。
また、喫煙は血圧管理において「百害あって一利なし」です。
タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させて一時的に血圧を急上昇させるだけでなく、長期的には動脈硬化を著しく進行させます。
禁煙は、血圧管理の必須項目といえるでしょう。
ストレスや睡眠不足
精神的なストレスや睡眠不足も、血圧を上げる大きな要因です。
ストレスを感じると、体を興奮させる交感神経が優位になり、血管が収縮して血圧が上がります。
この状態が慢性的に続くと、高血圧が定着してしまうのです。
また、睡眠中は通常、血圧が下がりますが、睡眠不足や睡眠の質が悪いと、夜間も血圧が高いままになり、心臓や血管への負担が大きくなります。
十分な休息とリラックスできる時間を持つことが大切です。
遺伝的要因
高血圧は、生活習慣だけでなく遺伝的な要因も関係することが知られています。
両親ともに高血圧の場合、子どもが高血圧になる確率は約50%、片親が高血圧の場合は約30%といわれています。
血圧が上がりやすい体質は遺伝する可能性があるのです。
- 塩分を体に溜め込みやすい体質
- 血圧を上げるホルモンが分泌されやすい体質
ご家族に高血圧の方がいる場合は、若いうちから生活習慣に気を配り、定期的に血圧をチェックすることが特に重要になります。
ほかの病気や薬の影響
高血圧の中には、何らかの特定の病気や使用している薬が原因で起こる「二次性高血圧」とよばれるものがあります。
これは高血圧全体の約1割を占め、原因となっている病気を治療することで血圧が改善する可能性があります。
原因となる主な病気や薬は以下の通りです。
- 病気:腎臓の病気、睡眠時無呼吸症候群、甲状腺の病気、副腎の腫瘍など
- 薬:一部の痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬)、ステロイド薬、漢方薬(甘草を含むもの)など
急に血圧が高くなった、若いのに血圧が高い、薬を飲み始めてから血圧が上がったなどの場合は、二次性高血圧を疑い、医師に相談することが大切です。
高血圧を放置することで起こりえる合併症
高血圧は、自覚症状がほとんどないまま静かに進行し、ある日突然、命に関わる病気を引き起こすことから「サイレントキラー(沈黙の殺人者)」とよばれています。
血圧が高い状態が続くと、全身の血管に常に強い圧力がかかり、動脈硬化が進行します。
その結果、様々な臓器に深刻なダメージを与えてしまうのです。
具体的にどのような病気があるか見ていきましょう。
【脳の病気】脳卒中(脳梗塞・脳出血)や血管性認知症
高血圧は、脳の血管に起こる病気の最大の危険因子です。
常に高い圧力にさらされた脳の血管はもろくなり、破れたり(脳出血)、詰まったり(脳梗塞)しやすくなります。
これらを総称して「脳卒中」といい、命を落としたり、体に麻痺などの重い後遺症が残ったりする原因となります。
また、小さな脳梗塞が多発したり、脳の血流が悪くなったりすることで、脳の機能が低下する「血管性認知症」のリスクも高まってしまうのです。
健達ねっとの書籍『認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣』でも、中年期の高血圧管理が老年期の認知症予防にいかに重要かが解説されています。
【心臓の病気】心筋梗塞、狭心症、心不全、心肥大
高い圧力に逆らって全身に血液を送り続けなければならない心臓には、非常に大きな負担がかかります。
その結果、様々な心臓の病気を引き起こします。
- 心筋梗塞・狭心症:心臓に栄養を送る冠動脈の動脈硬化が進み、血管が狭くなったり詰まったりする病気です。
- 心肥大:負担に耐えるため心臓の筋肉が厚く硬くなり、ポンプ機能が低下します。
- 心不全:長年の負担で心臓が疲弊し、全身に必要な血液を送り出せなくなった状態です。
これらは、突然死の原因にもなる非常に危険な病気です。
【腎臓の病気】腎硬化症、末期腎不全
腎臓は、細い血管の塊のような臓器で、血液をろ過して老廃物を排出する役割を担っています。
高血圧が続くと、この繊細な血管がダメージを受けて硬くなり、ろ過機能が徐々に低下していきます。
これが「腎硬化症」です。
さらに進行すると、腎臓がほとんど機能しなくなる「末期腎不全」という状態になり、生命を維持するために人工透析や腎移植が必要になります。
一度失われた腎機能は、元に戻すことが困難です。
【血管の病気】大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症
高血圧の影響は、心臓や脳だけでなく、全身の太い血管にもおよびます。
体の中心を走る最も太い血管である大動脈の壁が、高い圧力で弱くなり、こぶのように膨らんでしまうのが「大動脈瘤」です。
このこぶが破裂すると、大出血を起こし、極めて危険な状態に陥ります。
また、足の血管の動脈硬化が進み、血流が悪くなるのが「閉塞性動脈硬化症」です。
歩くと足が痛む、足が冷たいといった症状が現れ、進行すると足の組織が壊死してしまうこともあります。
【眼の病気】高血圧性網膜症
眼の奥には、網膜とよばれる光を感じるための神経の膜があり、そこにも細い血管が張り巡らされています。
高血圧によってこの網膜の血管が傷つくと、出血やむくみが起こり、視力低下や視野の欠損などを引き起こします。
これが「高血圧性網膜症」です。
また、高血圧は、加齢黄斑変性という失明につながる病気のリスクも高めることが知られています。
目の健康を守るためには、血圧管理と同時に、網膜を光のダメージから守るルテインなどの栄養素を意識的に摂取することも有効です。
健達ねっとが開発した機能性表示食品「健達ルテイン」は、目の黄斑色素量を維持する働きがあり、血圧管理に取り組む方の眼科的合併症予防の選択肢として活用できます。
低血圧に潜む代表的な合併症
高血圧のリスクは広く知られていますが、実は低血圧にも注意すべき合併症や、背景に隠れた病気の可能性があります。
「体質だから」と軽く考えず、どのようなリスクがあるのかを知っておくことが大切です。
特に、これまでになかった症状が現れた場合は注意が必要です。
失神やめまいによる転倒
低血圧に伴う症状の中で、最も直接的で危険なのが、失神やめまいによる転倒です。
急に立ち上がった際の立ちくらみ(起立性低血圧)などで意識を失い転倒すると、骨折や頭部外傷といった重大なケガにつながる可能性があります。
特に高齢者の場合、大腿骨骨折などが原因で寝たきりになってしまうケースも少なくありません。
日常生活での急な動作を避けるなどの注意が必要です。
QOL(生活の質)の低下
低血圧の症状は、命に直接関わらない場合でも、日々の生活の質(QOL)を大きく低下させることがあります。
- 朝起きるのがつらい
- 一日中、体がだるく疲れやすい
- 集中力が続かない
- 頭痛や肩こりが慢性化している
このような症状が続くことで、仕事や学業のパフォーマンスが低下したり、趣味や人付き合いを楽しめなくなったりと、精神的な負担も大きくなります。
精神的な不調
身体的な不調が長く続くと、精神面にも影響を及ぼすことがあります。
原因がはっきりしないだるさや倦怠感に悩み続けることで、気分が落ち込み、「うつ病」や「不安障害」といった精神疾患の引き金になる可能性も指摘されています。
体のつらさを一人で抱え込まず、必要であれば心療内科などへの相談も選択肢のひとつです。
背景に隠れた重篤な病気
特に注意が必要なのは、何らかの病気が原因で二次的に血圧が低くなっている「症候性低血圧」です。
この場合、低血圧は体からの危険信号(サイン)といえます。
以下のような病気が隠れている可能性があります。
- 心臓の病気:心筋梗塞や心不全など、心臓のポンプ機能が低下している。
- 内分泌系の病気:甲状腺機能低下症やアジソン病など、血圧を調整するホルモンの異常。
- 出血や脱水:消化管出血や外傷、激しい下痢や嘔吐により、体内の血液量が減少している。
- 薬剤の副作用:一部の降圧薬や向精神薬などの影響。
急に血圧が低くなった、強い症状を伴う、といった場合は、単なる体質と決めつけずに必ず医療機関を受診しましょう。
血圧を正常値に近づけるための5つの生活習慣改善法
原因とリスクを理解したところで、ここからは血圧を正常に保つための具体的なアクションプランを見ていきましょう。
高血圧の治療の基本は、薬ではなく生活習慣の改善です。
今日から始められる5つのポイントをご紹介します。
できることからひとつずつ、毎日の生活に取り入れてみてください。
食事療法
食事の改善は、血圧管理の要です。
ポイントは「減らすべきもの」と「増やすべきもの」を意識することです。
- 減塩:まずは1日の食塩摂取量を6g未満にすることを目指します。加工食品や外食を控え、出汁や香辛料を活用しましょう。
- カリウムを摂る:カリウムには、体内の余分な塩分(ナトリウム)を排出する働きがあります。野菜、果物、海藻類に多く含まれています。
- DASH食を意識する:高血圧予防のために開発された食事法で、カリウム、カルシウム、マグネシウム、食物繊維を豊富に含む食品(野菜、果物、低脂肪乳製品、全粒穀物など)を積極的に摂ります。
また、健達ねっとを運営するメディカル・ケア・サービス(MCS)の「MCS版自立支援ケア」では、高齢者の筋肉と血管の健康維持のために、1日約1,800mlの水分と約80gのタンパク質摂取を推奨しており、これらは血圧管理にも有効です。
適切な水分は血液の流れをよくし、良質なタンパク質は血管の弾力性を保ちます。
さらに、食事だけで補うのが難しい栄養素は、サプリメントで補うのもひとつの方法です。
中性脂肪の低下機能が報告されているDHA・EPAは、動脈硬化予防、ひいては高血圧改善にもつながります。
健達ねっと開発の機能性表示食品「健達DHA+EPA」などを活用するのもよいでしょう。
運動療法
定期的な運動は、血圧を下げるのに非常に効果的です。
特に、ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳などの「有酸素運動」が推奨されています。
これらの運動は、血管を広げ、心臓や肺の機能を高める効果が期待できます。
運動の目安は以下の通りです。
- 頻度:できれば毎日、少なくとも週に3日以上
- 時間:1回30分以上、または合計で週に180分以上
- 強度:「ややきつい」と感じる程度
大切なのは、無理なく続けることです。
まとまった時間が取れなくても、10分程度の運動を数回に分けて行うだけでも効果があります。
まずは、今より10分多く歩くことから始めてみてはいかがでしょうか。
適正体重の維持
肥満は高血圧の大きなリスク因子です。
体重を減らすだけで、血圧は面白いように下がることがあります。
一般的に、体重が1kg減ると血圧は1~2mmHg下がるといわれています。
目標は、肥満度を示す国際的な指標であるBMI(Body Mass Index)を25未満に保つことです。
BMIの計算式は以下の通りです。
- BMI = 体重(kg) ÷ {身長(m) × 身長(m)}
食事療法と運動療法を組み合わせ、長期的な視点で適正体重を目指しましょう。
急激な減量は体に負担をかけるため、1ヶ月に1~2kg程度のペースでゆっくりと減量するのが理想です。
お酒を控えて禁煙
お酒の飲み過ぎや喫煙の習慣は、血圧にとってマイナスでしかありません。
長年の習慣を変えるのは簡単ではありませんが、血圧管理のためには避けて通れない道です。
- 節酒:お酒を飲む習慣のある方は、量を減らすことから始めましょう。1日の適量は、純アルコール換算で男性20~30ml以下、女性10~20ml以下です。休肝日を設けることも効果的です。
- 禁煙:禁煙は、血圧だけでなく、がんや心臓病、脳卒中など、あらゆる病気のリスクを大幅に減らします。自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けるのもよい方法です。
健康のため、勇気を持って一歩を踏み出しましょう。
ストレス管理と質の高い睡眠
心と体の健康は密接につながっています。
日々のストレスを上手に解消し、質のよい睡眠をとることも、血圧の安定には不可欠です。
- 自分なりのストレス解消法を見つける:趣味に没頭する、好きな音楽を聴く、自然の中を散歩するなど、自分が心からリラックスできる時間を作りましょう。
- 規則正しい生活:毎日決まった時間に寝起きすることで、体内時計が整い、自律神経のバランスが安定します。
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる:38~40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かると、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。
- 快適な睡眠環境を整える:寝室の温度や湿度、音、光などを調整し、ぐっすり眠れる環境を作りましょう。
忙しい毎日の中でも、意識的に心と体を休ませる時間を持つことが大切です。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、血圧の正常値から、高血圧の原因、リスク、そして具体的な改善法までを網羅的に解説しました。
最後に、大切なポイントを振り返りましょう。
- 正常値の理解:血圧の正常値は、診察室で「120/80mmHg未満」、家庭で「115/75mmHg未満」です。高血圧だけでなく、「高値血圧」の段階から注意が必要です。
- 正しい測定の習慣化:健康管理の基本は、正しい方法で家庭血圧を測定し、記録することから始まります。日々の変化を把握することが、病気の早期発見につながります。
- 生活習慣の改善が鍵:血圧管理の主役は、薬ではなくあなた自身です。食事、運動、禁煙、ストレス管理など、今日からできることを見直し、実践することが未来の健康を守ります。
血圧の管理は、単に数値を下げることだけが目的ではありません。
その先にある、脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる病気を防ぎ、いつまでも自分らしく、大切な人と笑い合える豊かな人生を送るための、未来の自分への投資です。
この記事が、あなたの健康的な毎日への第一歩となることを心から願っています。
▼主要参考文献・信頼できるリソース