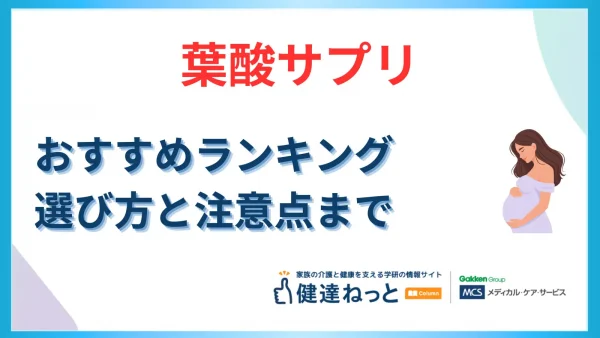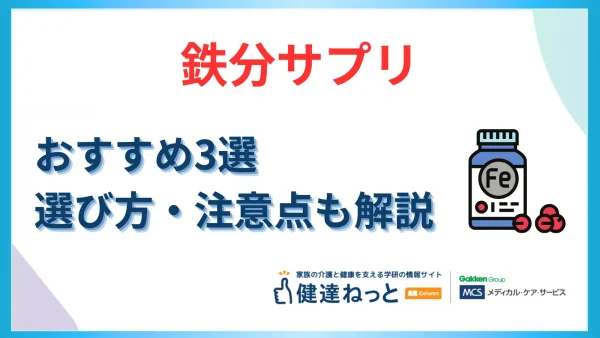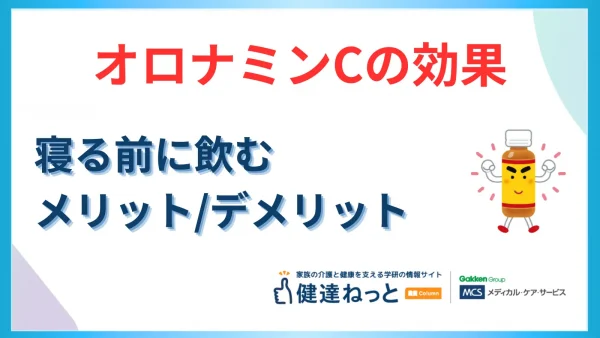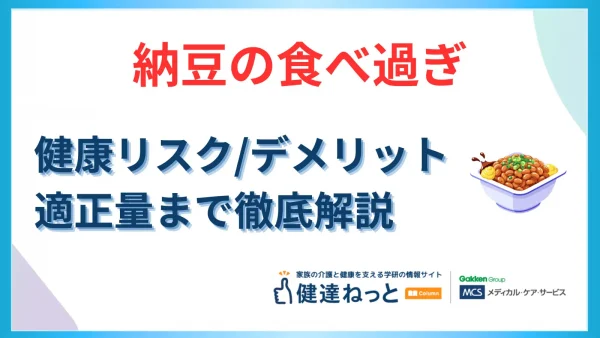にんにくは強い香りをもち、パスタ料理や炒め料理などに加えることで食欲をかき立てます。
またにんにくは滋養やスタミナ食材として豊富な栄養素を含み、疲労回復も期待できる食材です。
では具体的ににんにくにはどのような栄養や効果があるのでしょうか?
本記事ではにんにくの栄養について以下の点を中心にご紹介します。
- にんにくに含まれる栄養は?
- にんにくで得られる効果・効能は?
- 美味しいにんにくの選び方は?
にんにくの栄養について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スポンサーリンク
にんにくに含まれる栄養

にんにくはユリ科ネギ属の植物で、中央アジアが原産の香味野菜です。
独特な香りと風味をもち、球根や茎、葉を食用として世界各国で食べられています。
国内では青森県が生産量日本一を誇り、国内出荷の約7割を占めています。
にんにくは人間の健康を維持するための栄養素が多く含まれていることでも知られています。
可食部100gあたり
| 栄養素 | 含有量 |
| アリシン (mg) | 230 |
| カロテン (μg) | 2 |
| リン (mg) | 160 |
| 葉酸 (μg) | 93 |
| ビタミンB6(mg) | 1.53 |
アリシン
にんにく特有の香りの元になる物質です。
にんにくに含まれる無臭成分の「アリイン」と分解酵素の「アリナーゼ」が反応してにおいを発生させます。
にんにくは強い抗菌作用があり、昔は食中毒を防ぐ薬味として利用されていました。
その他ににんにくが持つ抗菌・抗カビ作用が、風邪予防やがん予防に効果があるといわれています。
体内でアリシンはビタミンB1と結合して「アリチアミン」を生成します。
アリチアミンはビタミンB1のように、糖質をエネルギーに代謝する作用があります。
アリチアミンの代謝率が上がることで、にんにくの滋養強壮の効果が発揮されるのです。
カロテン
カロテンには強い抗酸化作用があり、おもににんにくの芽の部分に多く含まれているといわれています。
カロテンはにんじんなどの赤い色素で、体内では「ビタミンA」に変換されます。
ビタミンAは目や皮膚の粘膜を健康に保ち、抵抗力が強くなる働きをします。
またビタミンAの主成分であるレチノールは、暗い場所でも視力を保ったり抗がん作用があることが注目されています。
リン
リンは骨や歯を正常な発達に導くためのミネラルの一種です。
カルシウムやマグネシウムとともに骨や歯を構成し、体内の細胞に存在しています。
リンの1日あたりの理想の摂取量は、
- 成人男性→1,000mg
- 成人女性→800mg
といわれています。
にんにくには100gあたり160mgのリンが含まれています。
穀類や肉・魚介・乳製品にもリンが多く含まれており、ほかの食品からもリンを補うことができます。
葉酸
葉酸は貧血を予防する働きがあり、葉物野菜に多く含まれています。
にんにくの場合は、芽の部分を中心に葉酸が含まれています。
葉酸もビタミンB1やB2などと同じ「ビタミンB群」の一種です。
葉酸は細胞や赤血球の合成・修復を助ける働きがあります。
また血液をスムーズに流し、動脈硬化を防ぐともいわれています。
葉酸は妊娠時期にとくに必要な鉄分やそのほかの栄養を補い、胎児の発育をサポートする重要な栄養素です。
ビタミンB6
ビタミンB6は、エネルギー代謝を助ける働きがあります。
たんぱく質や脂質の代謝の補酵素としての役割を担います。
ほかには赤血球に含まれるヘモグロビンを形成したり、免疫機能を正常に保つ働きがあります。
1日のビタミンB6の摂取目安は、成人で1.3mgといわれています。
にんにくには1.53mgが配合されており、ビタミンB6が豊富に含まれています。
またビタミンB6は水溶性ビタミンの一種で、余分なものは尿として排出されます。
葉酸に興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。
スポンサーリンク
にんにくで得られる効果・効能
 にんにくはスタミナ料理などに用いられ「体に良い」ということは多くの方が知っていると思います。
にんにくはスタミナ料理などに用いられ「体に良い」ということは多くの方が知っていると思います。
では「にんにく」にどのような効果・効能があるのかをご存知でしょうか?
にんにくが私たちの体にどのような良い影響をもたらしてくれるのか、まとめていきます。
疲労回復
にんにくを食べて疲労回復に大きな関わりがあるのは栄養素のアリシンです。
アリシンには代謝を上げる働きのほかに、たんぱく質の消化や胃液の分泌を増やす重要な働きをします。
胃液の分泌が活発になると栄養の吸収が良くなります。
また体の代謝が高まることで疲労回復を期待することができるのです。
冷え性の改善
「冷えは万病のもと」といわれるように、体を冷やすことでさまざまな病気を引き起こします。
手先が冷たいばかりでなく、血流が悪化して血栓を起こす原因にもなります。
にんにくの成分であるアリシンは、血管を広げ血流を促します。
また、体内の熱を発生させる細胞を刺激して体を温めます。
にんにくの硫黄成分が末梢神経まで拡張し、温かい血液を体の隅々まで届けてくれます。
そのため、血行を促進するにんにくは「冷え性の改善」に大きな効果を発揮します。
動脈硬化の予防
にんにくには「抗血栓作用」があり、血液をサラサラにする働きがあります。
「血栓」とは、血小板が集まって固まることで発生し血管を詰まらせる原因になることです。
にんにくに含まれる硫化化合物は、血小板が集まることを防ぎスムーズに血流を促します。
そのため心筋梗塞や脳梗塞の原因になる「動脈硬化」を予防することが期待できます。
免疫力を高める
にんにくの高い抗酸化力は「免疫力の向上」にも深い関わりがあります。
免疫力とは、体に侵入してきたウィルスや細菌などの異物を攻撃し病気を防ぐ体の仕組みのことです。
異物というのは外部からの侵入だけでなく、体の中のがん細胞にも当てはまります。
そのため免疫力を高めておくことは、がん予防にも繋がるということになります。
にんにくに含まれる「S-アリルシステイン」という物質が、体内の細胞を活発にし免疫力をアップさせます。
ガン細胞と闘うNK細胞が活発になることで、体に害を及ぼす細胞を攻撃し排除します。
冷え性の改善・免疫力を高めるについて興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。 「夏なのに手足が冷えている」「みんなは暑そうなのに自分だけ寒い」なんて感じたことはありませんか?夏も含めて一年中冷えに悩まされている方は多いと思います。本記事は、一年中つらい冷えに悩まされている冷え性の方に向けて、原因と対策をま[…] 冷え性改善の食べ物について「手足が冷たくてなかなか寝つけない…」「体が冷えてだるい…」日常生活でこうした冷えの症状があるとつらいですよね。冷えの症状があると病気になりやすいといわれています。冷え性を改善するに[…]
免疫力を高めると、風邪やさまざまな病気から身体を守ることができます。免疫力は普段の食事を意識するだけでも、風邪を予防して多くの良い効果をもたらしてくれます。では「免疫力を高める食べ物」はどのようなものがあるのでしょうか?本記[…]
タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]
美味しいにんにくの選び方
 にんにくは多くの栄養素のほかに「60%以上の水分」を含んでいます。
にんにくは多くの栄養素のほかに「60%以上の水分」を含んでいます。
美味しいにんにくとは、水分が多く新鮮でみずみずしい状態をさします。
美味しいにんにく選びのコツをご紹介しますので、ご参考にしてください。
- 色の白さ
- 形がキレイでハリがある
- 外側の皮と身にすき間がない
- 実が固く、重たい
にんにくは鮮度が落ちると、外の皮が変色して茶色くなります。
できるだけ白くてきれいな状態のものを選びましょう。
にんにくは全体的にキレイな丸みを帯びていて、ハリのあるものは水分が多いといわれています。
反対に痩せているにんにくは水分が抜けている可能性があります。
形はデコボコしていたり、縦長のにんにくは時間が経過していることが予想されます。
できるだけ全体的にふっくらした形のものが良いです。
外側の皮と中身との間にすき間が出来るのは、やせている証拠で古い可能性があります。
実は固く、ずっしりと重たいものが水分も豊富で新鮮な状態といえるでしょう。
にんにくを使ったレシピ

ここではにんにくの料理レシピを紹介します。
【簡単♪ 豚肉とレタスのにんにく炒め】
材料 2人分
- 豚肉小間切れ 200g
- レタス 1/3個
- にんにく 2片
- 塩コショウ(下味)少々
- しょう油 小1
- 砂糖 小1
- サラダ油 適宜
- 粗挽きコショウ 適宜
【作り方】
- レタスは食べやすい大きさにちぎっておきます
- 豚肉は少々塩コショウで下味をつけておきます
- にんにくはみじん切りにして、フライパンに油と一緒に入れ加熱します
- 豚肉を投入し火が通ったら、レタスとしょう油、砂糖を加えてサッと炒めます。
- レタスはシャキッとした食感が残るくらいで、お皿に盛り付けます
- 粗挽きコショウを振りかけて、完成
豚肉こま切れ肉やレタスは、火が通りやすく手軽に作れる時短レシピです。
豚肉のビタミン、にんにくの滋養作用、レタスの食物繊維を一緒に摂ることができます。
「時間をかけずに、体が元気になれる」おすすめの一品です。
【切って包むだけ♪ 鮭とにんにくのホイル焼き】
材料 2人分
- 鮭 2切れ
- にんにく 2片
- 玉ねぎ 1/4個
- えのき 1/2袋
- 人参 1/4本
- バター 小2
- 塩 少々
- ポン酢 大さじ2
- レモン 1/4個
- 粗挽き塩コショウ 適宜
- 小口ネギ 適宜
【作り方】
- ① 野菜はそれぞれカットします
- 玉ねぎ→薄切り
- にんにく→薄くスライス
- えのき→根元をカットして、半分に切る
- 人参→細切り
- ② アルミホイルを大きめに広げて、玉ねぎ、にんにく、えのき、人参、鮭、塩、バターを乗せる
- ③ アルミホイルを畳んで、蓋をする
- ④ 同じものをもう一つ作る
- ⑤ 180度に温めておいたオーブンで15分加熱する
- ⑥ 焼けたら、ポン酢やレモン、色どりに小口ネギを散らして、完成
オーブンに入れて焼くので、火加減の調整いらずで簡単にできます。
焼き時間が足りない場合は、追加で加熱してください。
魚や野菜はお好みのものをチョイスして代用OKです。
にんにくと野菜やたんぱく質も一緒に食べることが出来る簡単レシピです。
旬のにんにくは栄養価が高い
にんにくは年中スーパーなどで見かけるため、いつが旬なのか分かりづらい野菜のひとつです。
基本的ににんにくの旬は6〜8月頃といわれますが、栽培されている品種や土地によって収穫時期も変わります。
収穫したあとは1ヶ月ほど乾燥させてから出荷されます。
ある程度水分を抜いておくことで、貯蔵性が高まり長く保存できるようになります。
「旬の時期」はどの野菜においても、他の時期より新鮮で栄養価も高いといわれています。
厚生労働省の調査によると、年中出回っているトマトの栄養に大きな差がみられました。
トマト(100g)に含まれるビタミンの一種カロテンについて分析した結果は以下の通りです。
| 収穫時期 | カロテン含有量(μg) |
| 【旬の時期】7月 | 528 |
| 【旬ではない時期】11月 | 241 |
旬の時期と比べると、旬ではない11月収穫のトマトのカロテンの含有量は半分以下になっています。
この結果から、旬の時期に収穫されたにんにくも同様に栄養価に違いがでてきます。
旬の時期に収穫されたにんにくは、暑い夏の時期を乗り切るための滋養強壮の作用を最大限に発揮します。
そのほかのにんにくに含まれる栄養素も効率的に摂取することができるでしょう。
出典:厚生労働省【旬を取り入れた食生活】
にんにくの栄養まとめ
 ここまでにんにくの栄養についてお伝えしてきました。
ここまでにんにくの栄養についてお伝えしてきました。
にんにくの栄養について要点をまとめると以下の通りです。
- にんにくに含まれるおもな栄養は、アリシン、カロテン、リン、葉酸、ビタミンB6など
- にんにくで得られる効果・効能は、疲労回復や免疫力向上、冷え性改善など
- 美味しいにんにくの選び方は、全体的に丸みがありふっくらしている、実が固く重たいものなど
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。