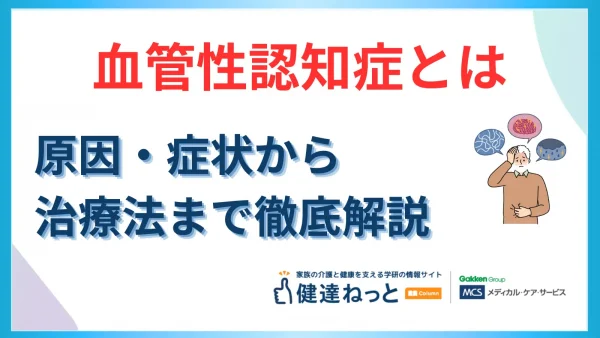- 「最近、親の物忘れが気になる…」
- 「さっきまで穏やかだったのに、急に怒り出すことがあるのはなぜ?」
- 「血管性認知症という言葉を聞いたけど、どのような病気なんだろう?」
ご家族のこのような変化に戸惑いや不安を感じていませんか。
もしかしたら、その症状は「血管性認知症」のサインかもしれません。
この記事では、血管性認知症の基本的な知識から、具体的な症状、そして進行を穏やかにするための予防法や治療、介護のコツまでを網羅的に解説します。
- 血管性認知症のメカニズムとアルツハイマー型との違い
- 見逃したくない初期症状と特徴的な症状
- 発症後の経過と進行を遅らせる5つの方法
- 最新の治療法とリハビリテーション
- 家族が穏やかに過ごすための介護のヒント
この記事を最後まで読めば、血管性認知症への漠然とした不安が解消され、ご本人とご家族が前向きに病気と向き合うための具体的な知識が身につきます。
正しい情報を元に、今日からできる対策を始めましょう。
スポンサーリンク
血管性認知症とは?まず知っておきたい基礎知識
血管性認知症について理解を深めるために、まずは基本的な知識から押さえましょう。
原因や他の認知症との違いを知ることで、適切な対応への第一歩を踏み出すことが可能となります。
脳の血管トラブルが原因で起きる認知症
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害が原因で脳の神経細胞が壊れ、認知機能が低下する病気です。
脳の血管が詰まったり破れたりすると、その先の細胞に酸素や栄養が届かなくなり、細胞が死んでしまいます。
どの部分の脳細胞がダメージを受けたかによって、現れる症状が異なるのが大きな特徴です。
例えば、記憶を司る部分が損傷すれば物忘れが、感情をコントロールする部分が損傷すれば感情の起伏が激しくなるといった症状が現れます。
このように、原因となる脳血管障害と症状が直結しているのが、血管性認知症の基本的なメカニズムです。
血管性認知症は、以下のように日本神経学会により定義されています。
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管の病気(”脳血管障害”、”脳卒中”とよびます)の結果、認知症になった状態を指します。
引用元:日本神経学会
アルツハイマー型認知症との4つの違い
血管性認知症は、最も多いアルツハイマー型認知症としばしば比較されます。
これら三大認知症の中でも、両者には症状の現れ方や経過に明確な違いがあります。
| 比較項目 | 血管性認知症 | アルツハイマー型認知症 |
|---|---|---|
| 原因 | 脳梗塞や脳出血などの脳血管障害 | 脳に異常なたんぱく質が溜まること |
| 症状の現れ方 | 脳血管障害が起きるたびに段階的に悪化 | ゆっくりと進行 |
| 主な症状 | まだら認知症、感情失禁、麻痺など | 物忘れ(特に最近の記憶)から始まる |
| 性差 | 男性に多い | 女性に多い |
このように違いはありますが、適切なケアによって症状が改善する可能性がある点は共通しています。
メディカル・ケア・サービスが開発した「MCSケアモデル」では、科学的根拠に基づくケアにより、認知症の方の85%以上に心身の状態改善が見られました。
この事実は、血管性認知症であっても、希望を持ってケアに取り組めることを示しています。
日本では2番目に多いタイプで男性に多い
血管性認知症は、日本ではアルツハイマー型認知症に次いで2番目に多いタイプの認知症です。
特に、生活習慣病のリスクが高い男性に多く見られる特徴があります。
これは、血管性認知症の引き金となる脳梗塞や脳出血が、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病と深く関わっているためです。
これらの病気は、男性の方が罹患率が高い傾向にあることが、結果として血管性認知症の男女比に影響していると考えられます。
超高齢社会に突入したことで、より増加している認知症の発症者数。認知症の発症者数の増加により、様々な研究が行われており、認知症の種類による男女比についても研究されています。そこで今回は血管性認知症について以下の項目を中心に解説して[…]
厚生労働省の統計データによると、若年性認知症において血管性認知症は17.1%を占め、アルツハイマー型認知症の52.6%に次いで多いことが確認されています。
社会全体で認知症への理解を深めることも重要です。
当社の調査では、子どもたちの92%が認知症に関する授業後に「イメージがよくなった」と回答しており、早期からの教育が偏見をなくし、地域全体で支える土壌を育むことにつながります。
スポンサーリンク
血管性認知症のサインを見抜く症状チェックリスト
血管性認知症は、早期にサインを捉え、対策を始めることが進行を緩やかにする鍵です。
ご家族やご自身の変化に気づくための、代表的な症状をチェックしていきましょう。
代表的な初期症状
血管性認知症の初期症状は、脳のどの部分がダメージを受けたかによって様々ですが、比較的よく見られるサインがあります。
以下のリストに当てはまる項目がないか、確認してみてください。
- 物事の判断や計画を立てるのが苦手になった
- 頭がぼーっとする時間が増えた
- 動作が以前よりもゆっくりになった
- 夜間に何度もトイレに起きる
- 物忘れはあるが、自覚していることが多い
- 感情の起伏が激しくなった
これらの症状は、他の病気や加齢によっても起こりえますが、複数が当てはまる場合は注意が必要です。
気になる変化があれば、ひとりで抱え込まず専門医に相談しましょう。
国立長寿医療研究センターによると、血管性認知症の初期症状には、意欲低下や自発性低下、夜間不眠や不穏などがあることが報告されており、アルツハイマー型認知症が物忘れで発症することと異なるため、見落とされている場合もあります。
特徴的な症状は「まだら認知症」と「感情失禁」
血管性認知症には、他の認知症と区別しやすい特徴的な症状があります。
それが「まだら認知症」と「感情失禁」です。
まだら認知症とは、脳のダメージを受けていない部分は正常に機能するため、できることとできないことがはっきりと分かれる状態を指します。
例えば、記憶力は低下しているのに、判断力は保たれているといったケースです。
そのため、日や時間帯によって状態がよく見えることもあり、周囲が「本当に認知症なのだろうか?」と混乱する原因にもなります。
国立精神・神経医療研究センターでは、障害された脳の部位によって症状が異なるため、一部の認知機能は保たれている「まだら認知症」が特徴であると説明されています。
感情失禁は、ささいなことで急に泣き出したり怒ったりと、感情のコントロールが難しくなる症状です。
これは脳の感情を司る部分が多発性脳梗塞などでダメージを受けることで起こります。
当社のグループホームでは、感情コントロールが難しい方に対し、地域の方々の協力を得て散歩を実現した事例があります。
周囲の理解と適切な関わりが、本人の望みを叶え、症状の安定につながることを示しているわけです。
身体に現れるのは歩行障害や麻痺など
血管性認知症は、物忘れなどの認知機能の障害だけでなく、身体的な症状を伴うことが多いのも特徴です。
脳の運動機能を司る部分がダメージを受けることで、以下のような症状が現れます。
- 歩行障害:小刻みで歩幅の狭い歩き方になる、足がすくんで前に出にくくなる
- 麻痺:手足の片側が動きにくくなる(片麻痺)
- 構音障害:ろれつが回りにくくなる
- 嚥下障害:食べ物や飲み物が飲み込みにくくなる
これらの身体症状は、転倒や誤嚥性肺炎のリスクを高め、生活の質(QOL)を大きく低下させる原因となります。
そのため、認知機能へのアプローチと同時に、身体機能のリハビリテーションが非常に重要になってくるのです。
気になる血管性認知症になったその後
「血管性認知症と診断されたら、この先どうなるのだろう?」という不安は、ご本人にもご家族にも共通するものです。
病気の経過と予後について正しく理解し、将来に備えましょう。
脳細胞の回復は難しいが、進行を食い止めることは可能
一度壊れてしまった脳細胞を元に戻すことは、現在の医療では困難です。
しかし、血管性認知症は、その後の生活習慣や治療によって、病気の進行を食い止めたり、緩やかにしたりすることが可能です。
最大のポイントは、新たな脳血管障害を起こさないことにあります。
原因となる高血圧や糖尿病などの生活習慣病をしっかり管理し、脳卒中の再発を予防することが、認知機能のさらなる低下を防ぐ上で最も重要です。
血管性認知症の経過は、その後の取り組み次第で大きく変わります。
悲観的になりすぎず、今できることに目を向けて、前向きに治療や予防に取り組む姿勢が大切です。
ただし、段階的に悪化していく
血管性認知症の進行は、アルツハイマー型認知症のように緩やかに進むのではなく、「段階的」に進むという特徴があります。
これは、小さな脳梗塞などを再発するたびに、階段を下りるように症状が悪化するためです。
状態が安定している期間(踊り場)と、急に症状が悪化する期間(階段)を繰り返しながら進行していきます。
そのため、昨日までできていたことが今日できなくなるといった、急な変化に本人も家族も戸惑うことが少なくありません。
このような認知症の進行の仕方を知っておくことで、心の準備ができます。
しかし、適切なケアで改善するケースもあります。
当社の中国事業所では、自立支援ケアと医療連携により、傾眠がちで肺炎を繰り返していた方の身体機能が回復し、歩行器なしで歩けるようになった事例があります。
諦めずにケアを続けることの重要性がわかります。
引用元:認知症ケア実践・研究報告会
かかった人の平均寿命
血管性認知症の人の平均寿命は、診断されてから約5〜7年というデータがありますが、これはあくまで平均値であり、個人差が非常に大きいのが実情です。
寿命に影響を与える最も大きな要因は、原因疾患である脳血管障害や、それに伴う合併症です。
特に、寝たきりになることによる誤嚥性肺炎や感染症は、生命予後を左右する重要なリスクとなります。
逆にいえば、脳卒中の再発予防を徹底し、リハビリによって身体機能を維持し、肺炎などの合併症を防ぐことができれば、より長く穏やかな生活を送ることも可能です。
数字に一喜一憂するのではなく、日々の健康管理を丁寧に行うことが何よりも大切だといえるでしょう。
【最重要】血管性認知症の進行を防ぐ・発症を予防する5つの方法
血管性認知症は、生活習慣と深く関わっています。
つまり、日々の暮らしを見直すことが、最も効果的な予防策であり、進行を遅らせる鍵となるのです。
今日から始められる5つの方法を紹介します。
1.最大のカギは「脳卒中の再発予防」
血管性認知症の進行を防ぐ、あるいは発症を予防する上で、最も重要なことは脳卒中の再発予防です。
新たな脳梗塞や脳出血を防ぐことが、認知機能の維持に直結します。
脳卒中の予防は、血管性認知症と診断された方はもちろん、まだ発症していない方にとっても重要です。
特に、高血圧や糖尿病などのリスクを抱えている方は、脳梗塞の予防に真剣に取り組む必要があります。
具体的な予防策は、この後で解説する生活習慣病の管理や食事、運動などが中心となります。
これらを総合的に実践し、脳の血管を守ることが、認知症予防の核心であると理解してください。
国立循環器病研究センターでも、脳卒中に付随して起こる血管性認知症には生活習慣の改善など脳卒中予防が効果的であることが報告されています。
2.生活習慣病の徹底管理
高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、動脈硬化を進行させ、脳の血管にダメージを与える最大の危険因子です。
これらの病気の管理を徹底することが、血管性認知症の予防には不可欠です。
特に高血圧の対策は重要で、医師の指導のもとで血圧を適切にコントロールする必要があります。
治療の基本は以下の通りです。
- 定期的な受診:医師の診察を定期的に受け、薬を正しく服用する
- 血圧測定の習慣化:家庭で血圧を測り、日々の変動を記録する
- 生活習慣の改善:減塩、適度な運動、禁煙などを継続する
生活習慣病は自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的な健康診断でご自身の体の状態を把握し、早期に対策を始めることが大切です。
日本神経学会によると、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病や心臓の病気など、様々な病気が原因となって起こるとされています。
3.今日からできる食事療法
食事による生活習慣病予防は、血管性認知症の予防に直結する重要なアプローチです。
特に脳梗塞後の食事療法では、塩分と脂肪のコントロールが鍵となります。
| ポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| 減塩 | 1日の塩分摂取量を6g未満に抑える。だしや香辛料をうまく活用する。 |
| 脂肪 | 動物性脂肪(肉の脂身、バター)を控え、植物性油や魚の油(DHA・EPA)を摂る。 |
| 野菜・果物 | カリウムが豊富な野菜や果物を積極的に摂り、余分な塩分の排出を促す。 |
| 水分補給 | 血液がドロドロになるのを防ぐため、こまめに水分を摂る。 |
さらに、認知機能の維持をサポートする成分を補うのもよいでしょう。
当社が販売する機能性表示食品「記憶の王道」や「プラズマローゲンBOOCSスペシャル60」は、中高年の認知機能の一部である言語記憶力や認知機能速度の維持をサポートします。
4.無理なく続ける運動習慣
適度な運動は、血圧を下げ、血糖値やコレステロール値を改善するなど、生活習慣病の予防に大きな効果があります。
認知症予防のための運動療法として、特に推奨されるのが有酸素運動です。
手軽に始められるウォーキングは、無理なく続けられるオススメの運動です。
「1日30分、週に3回」を目安に、少し汗ばむくらいのペースで歩く習慣をつけましょう。
また、血管性認知症では嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。
新潟医療福祉大学の西尾正輝教授が開発した「ノドトレ」は、1回5秒でできる喉のトレーニングで、嚥下機能の維持・向上に科学的エビデンスがあります。
このような専門的なプログラムを取り入れるのも有効な手段です。
5.禁煙と節度ある飲酒
喫煙は、血管を傷つけ動脈硬化を促進する最大の要因のひとつです。
血管性認知症の予防・進行抑制のためには、禁煙が絶対条件といえます。
自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
また、過度な飲酒は高血圧や脂質異常症の原因となり、脳卒中のリスクを高めます。
アルコールは「節度ある適度な量」を守ることが大切です。
一般的に、1日の適量は以下の通りです。
- ビール:中瓶1本(500ml)
- 日本酒:1合(180ml)
- ワイン:グラス2杯(200ml)
- ウイスキー:ダブル1杯(60ml)
休肝日を週に2日以上設けるなど、肝臓を休ませることも忘れないようにしてください。
健康的な生活習慣を確立することが、脳の健康を守る一番の近道です。
血管性認知症の治療とリハビリテーション
血管性認知症の治療は、進行を食い止める「予防的な治療」と、残された機能を最大限に活かす「リハビリテーション」が二つの大きな柱となります。
それぞれの具体的な内容について見ていきましょう。
主流で行われるのは薬物療法
血管性認知症の薬物療法は、根本的な治療薬がないため、脳卒中の再発予防と症状の緩和を目的として行われます。
主に以下の4種類の薬が用いられます。
脳卒中を予防する薬
脳の血流を悪化させないことが最も重要です。
血液をサラサラにして血栓ができるのを防ぐ「抗血小板薬」や「抗凝固薬」が、脳梗塞の再発予防のために処方されます。
生活習慣病の薬
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患をコントロールするための薬です。
「降圧薬」「血糖降下薬」「脂質異常症治療薬」などがあり、医師の指示通りにきちんと服用を続けることが不可欠です。
周辺症状を抑える薬
意欲の低下やうつ状態、不眠、幻覚、妄想といった、認知機能障害に伴って現れる精神症状(BPSD)を和らげるための薬です。
「抗うつ薬」「睡眠薬」「抗精神病薬」などが、症状に応じて慎重に用いられます。
認知機能改善薬
アルツハイマー型認知症で使われる認知機能改善薬が、血管性認知症の意欲低下や自発性の低下といった症状に対して有効な場合があります。
ただし、保険適用外となることもあり、効果も限定的です。
日本神経学会によると、血管性認知症に効果がある薬剤は今のところ存在しませんが、脳卒中の再発予防のために高血圧などの生活習慣病の治療が不可欠とされています。
機能維持・向上のためのリハビリテーション
失われた機能を取り戻すというよりも、今ある能力を維持し、低下を防ぐことを目的とした認知症リハビリが重要です。
専門職と連携しながら、高齢者向けのリハビリサービスを活用しましょう。
理学療法
歩く、立つ、座るといった基本的な動作能力の維持・改善を目指します。
理学療法士が、個々の状態に合わせて筋力トレーニングやバランス訓練、歩行訓練などを行います。
転倒を予防し、安全な日常生活を送るための土台を作る重要なリハビリです。
認知症ケアにおける理学療法士の役割は非常に大きいといえます。
作業療法
食事や着替え、入浴などの日常生活動作(ADL)や、料理や買い物といった応用的な動作(IADL)の訓練を行います。
作業療法士が、趣味活動や手芸などを通じて、手の細かな動きや思考力、集中力を高め、生活の質(QOL)の向上を支援します。
言語聴覚療法
ろれつが回りにくい(構音障害)、言葉が出てこない(失語症)、飲み込みが悪い(嚥下障害)といった症状に対して、言語聴覚士が専門的な訓練を行います。
口や舌の体操、発声練習、飲み込みの訓練などを通じて、コミュニケーションと食事の楽しみを支えます。
当社の「SIDE別運動プログラム」は、個々の身体状況に合わせて転倒予防や歩行安定を目指す独自の運動手法です。
また、「MCSケアモデル」では、運動、栄養、医療連携を包括的に行うことで、85%以上の方で改善実績を上げています。
「認知症を超える。」をブランドメッセージとし、認知症高齢者対応のグループホーム「 愛の家」を主軸に介護事業所を300か所…
「認知症を超える。」をブランドメッセージとし、認知症高齢者対応のグループホーム「 愛の家」を主軸に介護事業所を300か所…
血管性認知症になった本人と家族が穏やかに過ごすための介護のコツ
血管性認知症の方と穏やかに暮らすためには、病気の特性を理解し、適切な対応を心がけることが大切です。
ご本人とご家族、双方の負担を軽くするための介護のヒントを紹介します。
本人への接し方
血管性認知症の方は、できることとできないことが混在する「まだら認知症」の状態にあるため、プライドが傷つきやすい傾向があります。
以下の点を心がけ、本人の尊厳を守る接し方が重要です。
- できないことを責めない:失敗を指摘したり、叱ったりせず、さりげなく手助けする。
- できることは本人に任せる:過剰に手伝うのではなく、本人が自分でできることを見つけて役割を持ってもらう。
- 感情的にならず、ゆっくり話す:本人が混乱しないよう、穏やかな口調で、短く分かりやすい言葉で伝える。
- 自尊心を尊重する:子ども扱いせず、ひとりの大人として敬意を持って接する。
特に高齢者の食事サポートでは、思い出の食事などを通じて会話を弾ませる「回想法」が有効です。
当社の「ハルと思い出めぐりごはん」は、回想法を活用し、食欲と栄養改善につなげる食事支援プログラムです。
感情失禁が起きた時の対応
突然泣き出したり怒ったりする「感情失禁」は、本人にもコントロールできない脳の症状です。
家族が冷静に対応することが、本人を安心させ、症状を落ち着かせることにつながります。
| 対応のポイント | 具体的な行動 |
|---|---|
| 冷静に受け止める | 驚いたり、一緒になって感情的になったりしない。「つらいね」「悲しいね」と気持ちに寄り添う。 |
| 環境を変える | 場所を変えたり、好きな音楽をかけたりして、本人の気分転換を図る。 |
| 原因を探らない | 「なぜ泣いているの?」と問い詰めると、本人をさらに混乱させるため避ける。 |
| 安全を確保する | 興奮している場合は、本人や周囲が怪我をしないよう、危険な物を遠ざける。 |
感情失禁は、脳のダメージによる症状であり、本人のわがままではないと理解することが第一歩です。
音楽療法やアロマセラピーといった認知症の非薬物療法も、心を落ち着けるのに役立つ場合があります。
安全な在宅環境の整え方
血管性認知症の方は、歩行障害や麻痺を伴うことが多く、転倒のリスクが非常に高い状態にあります。
安全に暮らせるよう、住環境を見直すことが重要です。
- 段差の解消:敷居やカーペットの縁など、小さな段差につまずかないよう、スロープを設置したり、固定したりする。
- 手すりの設置:廊下やトイレ、浴室など、移動や立ち座りの際に体を支えられる場所に手すりを設置する。
- 照明の確保:廊下や足元を明るく照らす。夜間はセンサーライトなどを活用する。
- 整理整頓:床に物を置かないようにし、動線を確保する。
正しい知識を持つことは、家族の介護負担を心理的に軽くします。
当社の「認知症教育の出前授業」では、授業後、子どもから「祖父を避けていたけれど、これからは多く訪れたい」という感想が寄せられました。
病気への理解が、家族関係をよりよいものに変える力を持っています。
「認知症を超える。」をブランドメッセージとし、認知症高齢者対応のグループホーム「 愛の家」を主軸に介護事業所を300か所…
困った時に利用できる公的サービスと支援制度
介護はひとりで抱え込むものではありません。
不安や悩みを分かち合い、負担を軽くするために、利用できる公的なサービスや支援制度を積極的に活用しましょう。
最初の相談窓口は「地域包括支援センター」
「どこに相談すればよいかわからない」という時に、最初の窓口となるのが地域包括支援センターです。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が常駐し、高齢者の健康や福祉、介護に関する様々な相談に無料で応じてくれます。
認知症に関する相談はもちろん、介護保険サービスの利用方法、医療機関の紹介、成年後見制度の案内など、幅広い支援を行っています。
市区町村のウェブサイトや役所で場所を確認し、まずは電話をかけてみましょう。
介護の負担を軽くする「介護保険サービス」
介護保険制度を利用すれば、1〜3割の自己負担で様々な介護サービスを受けることが可能です。
要介護・要支援認定を受けることで、ケアマネジャーが本人や家族の状況に合わせたケアプランを作成してくれます。
| サービスの種類 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 在宅サービス | ヘルパーが自宅を訪問する「訪問介護」、リハビリを行う「デイケア」、短期宿泊の「ショートステイ」など |
| 施設サービス | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などへの入所 |
| 地域密着型サービス | 小規模多機能型居宅介護、グループホームなど、住み慣れた地域での生活を支えるサービス |
また、要介護状態になるのを防ぐための介護予防サービスもあります。
これらのサービスをうまく組み合わせることで、介護者の負担を軽減し、共倒れを防ぐことが可能です。
不安や悩みを分かち合える「家族会」
同じ立場の介護者同士が集まり、情報交換や悩み相談ができる「認知症の人と家族の会」などの家族会も、大きな心の支えとなります。
介護の体験談を聞いたり、日頃の苦労を打ち明けたりすることで、孤独感が和らぎ、「悩んでいるのは自分だけではない」と感じることが可能です。
また、当社では全国の事業所が参加する「認知症ケア実践・研究報告会」を年1回開催し、最新のケア技術や事例を共有しています。
このような全国規模で蓄積された知見は、よりよいケアを目指す上での貴重な情報源となります。
予防の段階では、認知症専門医が執筆した「認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣」のような書籍から、具体的な生活習慣を学ぶのも有効です。
スポンサーリンク
まとめ
この記事では、血管性認知症の原因から症状、予防、治療、介護のコツまでを詳しく解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって引き起こされる認知症です。
そのため、最大の予防・進行抑制策は、高血圧などの生活習慣病を管理し、脳卒中の再発を防ぐことにあります。
発症後は、脳卒中を起こすたびに段階的に症状が進行する特徴がありますが、適切な治療やリハビリ、そして周囲の理解とサポートによって、進行を緩やかにし、穏やかな生活を続けることは十分に可能です。
もしご家族やご自身に気になるサインがあれば、ひとりで悩まず、かかりつけ医や地域包括支援センターに相談してください。
早期に正しい知識を得て、適切な一歩を踏み出すことが、ご本人とご家族の未来を守ることにつながります。