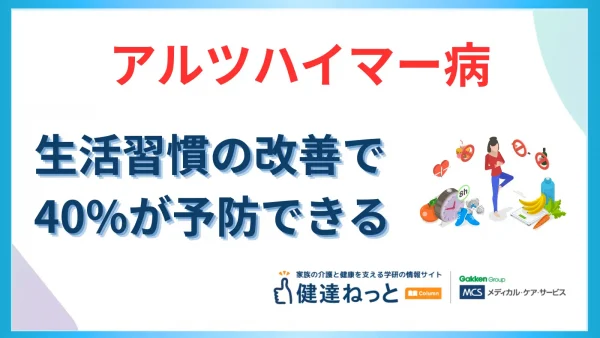- 「最近、親のもの忘れが気になる…」
- 「もしかして、認知症の始まりなのだろうか?」
- 「自分自身の将来も、少し不安に感じる…」
親を想うからこそ、このような不安を感じてしまうのは自然なことです。
大切な家族には、いつまでも健康でいてほしい。
そして自分自身も、穏やかで自分らしい老後を送りたい。
そのように願っている方が多いかと思います。
結論からいうと、アルツハイマー病を含む認知症は、日々の生活習慣を見直すことで、そのリスクを低減できる可能性が最新の研究で示されています。
この記事を読むことで、以下のことが明確になるでしょう。
- アルツハイマー病のリスクを高める14の危険因子
- 今日からすぐに実践できる7つの予防的な生活習慣
- 親子関係を大切にしながら、生活改善をサポートするコツ
この記事は、介護と健康の専門家であるメディカル・ケア・サービス(学研グループ)が運営する「健達ねっと」が、科学的根拠に基づいて解説します。
未来への漠然とした不安を、「今できること」という具体的な希望に変えるための一歩を、一緒に踏み出しましょう。
スポンサーリンク
アルツハイマー病と生活習慣の気になる関係
「アルツハイマー病は遺伝だから仕方ない」と思っていませんか?
実は、日々の暮らし方が、発症リスクに深く関わっていることが分かってきました。
リスクを高める14の危険因子
アルツハイマー病は、ある日突然発症するわけではありません。
長年の生活習慣の積み重ねが、発症のリスクを高める一因となることが、近年の研究で明らかになっています。
認知症の専門家による詳しい解説は、認知症の権威と語る「40代からの認知症予防」や生活習慣から認知症を予防する専門家インタビューでご覧いただけます。
国際的な医学雑誌『ランセット』の委員会は、2020年の報告で12の危険因子を提示し、2024年には新たに2つの因子(高LDLコレステロール血症、視力障害)が追加され、14の危険因子となりました。
これらの因子は、私たちの努力次第で改善できるものが多く含まれています。
| カテゴリー | 危険因子 |
|---|---|
| 若年期(45歳未満) | 教育期間の短さ |
| 中年期(45~65歳) | 難聴、頭部外傷、高血圧、過度の飲酒、肥満、高LDLコレステロール血症(新規) |
| 老年期(65歳以上) | 喫煙、うつ病、社会的孤立、運動不足、大気汚染、糖尿病、視力障害(新規) |
これらのリスクを正しく理解し、ひとつずつ対策を講じることが、未来の健康を守る鍵となります。
アルツハイマー病の予防については、科学的根拠がある5つの予防法で詳しく解説しています。
認知症の45%は予防が期待できる
「認知症は避けられない」という考えは、もう過去のものです。
前述のランセット委員会の2024年最新報告では、14の危険因子を適切に管理することで、認知症の約45%は発症を遅らせたり、予防したりできる可能性があると結論づけています。
これは、私たちの選択と行動が、未来を大きく変える力を持つことを示す、非常に希望のあるメッセージといえるでしょう。
この考え方は世界的な潮流となっており、世界保健機関(WHO)も認知機能低下と認知症のリスク低減に関するガイドラインを発表しています。
その中で推奨されている項目には、以下のようなものがあります。
- 身体活動の実施
- 禁煙
- 栄養バランスのよい食事
- アルコールの適正な摂取
- 体重管理
つまり、特別なことではなく、健康的な生活を心がけることこそが、最も効果的な認知症予防策なのです。
また、MCI(軽度認知障害)の段階で適切な対策を講じることで、認知症への進行を防ぐことが可能です。
スポンサーリンク
今日から始めるアルツハイマー病を遠ざける7つの生活習慣
リスクが分かったところで、次はいよいよ具体的なアクションです。
毎日の暮らしの中に、脳の健康を守るヒントは多く隠されています。
【食事】脳を守る「地中海式食事法」と和食のススメ
脳の健康は、日々の食事から作られます。
特に、アルツハイマー病予防の観点から世界的に注目されているのが「地中海式食事法」です。
これは、野菜や果物、魚、オリーブオイルなどを豊富に使い、肉や乳製品を控える食事スタイルで、脳の炎症を抑え、神経細胞を保護する効果が期待されています。
最新の研究解析では、地中海食をきちんと守ることによって、認知症の発症リスクが21%低くなることが示されています。
生活習慣の改善による健康維持については、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
私たち日本人にとっては、伝統的な和食も大変有効です。
ポイントとなる食材の頭文字をとった「まごわやさしい」を意識すると、バランスが整いやすくなります。
| 食事法 | 主な食材 |
|---|---|
| 地中海式食事法 | 野菜、果物、全粒穀物、豆類、ナッツ類、魚介類、オリーブオイル |
| 和食(まごわやさしい) | まめ、ごま、わかめ(海藻)、やさい、さかな、しいたけ(きのこ)、いも |
認知症予防に効果的な食べ物については、認知症になりやすい食べ物と予防食品で詳しく解説しています。
また、食事による生活習慣病予防も合わせてご参考ください。
食事だけでは摂取が難しい栄養素については、機能性表示食品の活用も選択肢のひとつです。
健達ねっとでは、記憶力の維持に関する機能性表示食品「記憶の鉄人」(PQQ配合)や「記憶の王道」(鶏由来プラズマローゲン配合)を取り扱っています。
これらは中高年の認知機能をサポートする成分として、言語記憶力や注意力、判断力の維持に役立つとされているのです。
また、腸内環境と脳の健康の関係(脳腸相関)に着目した「メモリービフィズス菌」なども、記憶力維持の新たなアプローチとして注目されています。
サプリメントを検討される際は、機能性表示食品など科学的根拠に基づいた製品を選ぶことが大切です。
【運動】無理なく続く「コグニサイズ」で脳も体も活性化
運動が体にいいことは誰もが知っていますが、特に脳の健康維持には不可欠です。
運動は脳の血流を促進し、神経細胞の成長を促す「脳由来神経栄養因子(BDNF)」の分泌を活発にします。
中でもオススメなのが、国立長寿医療研究センターが開発した「コグニサイズ」です。
これは、計算やしりとりなどの知的課題と運動を組み合わせたもので、脳と体を同時に活性化させる効果が期待できます。
家庭で簡単にできるコグニサイズの例は、以下の通りです。
- ステップ運動: 踏み台昇降をしながら、100から3を引き続ける
- ウォーキング: 散歩をしながら、前の人の服装の色を覚えておく
- しりとり: 足踏みをしながら、動物の名前でしりとりをする
ポイントは「少し間違えてしまうくらいの、少し難しい課題」に挑戦すること。
これにより脳が活性化します。
コグニサイズの具体的な方法については、アルツハイマー病への効果的な脳トレで詳しくご紹介しています。
また、認知症予防に効果的な趣味についても合わせてお読みください。
運動を始める際の具体的な方法については、健達ねっとが監修する「ふたりウォーク」という書籍で詳しく解説しています。
ひとりでは続かないウォーキングも、家族や友人と一緒に行うことで継続しやすくなり、認知症予防だけでなくコミュニケーションの向上にもつながります。
また、腰痛などで運動に不安がある方には、理学療法士監修の「コシトレ」で、安全で効果的なストレッチ方法を学ぶことが可能です。
高齢期の身体的特徴を理解した上で運動を始めたい方には、400点以上のイラストで解説した「高齢者のからだ図鑑」も勉強になるでしょう。
これらの専門書籍は、現役の理学療法士や医療専門家が執筆しており、自宅でも安全に実践できる内容となっています。
【知的活動】「楽しい」が一番の脳トレ!趣味や学びのススメ
脳の健康を保つには、脳を使い続けることが大切です。
新しいことに挑戦したり、趣味に没頭したりする知的活動は、脳内に新たな神経回路(シナプス)を作り出し、脳の機能が衰えにくくなる「認知予備能(コグニティブ・リザーブ)」を高めます。
難しい計算ドリルやパズルだけが脳トレではありません。
日常生活の中に、脳をワクワクさせる活動は多々あります。
知的活動のポイントは、以下の通りです。
- 指先を使う活動: 料理、裁縫、楽器演奏、絵画など
- 戦略を考える活動: 囲碁、将棋、麻雀、ボードゲームなど
- 新しい知識を学ぶ活動: 語学学習、資格の勉強、読書、美術館めぐりなど
- 計画を立てる活動: 旅行の計画、家計簿の作成など
最も重要なのは、本人が「楽しい」と感じ、主体的に取り組めることです。
義務感でいやいや行うよりも、夢中になれることを見つける方が、脳へのよい刺激となり、長続きします。
【社会参加】人との交流が最高の刺激
社会的孤立は、うつ病と並んでアルツハイマー病の大きな危険因子とされています。
人とのコミュニケーションは、脳のさまざまな領域を同時に使う、非常に高度な知的活動です。
会話の内容を理解し、自分の考えをまとめ、適切な言葉を選んで相手に伝える。
この一連のプロセスが、脳機能の維持に非常に効果的です。
積極的に社会と関わるためのヒントは、以下の通りです。
- 地域の趣味のサークルや同好会に参加する
- ボランティア活動を始める
- 友人や知人と定期的に会う約束をする
- 家族との会話の時間を大切にする
- 行きつけのお店を作り、店員さんと顔なじみになる
社会参加の効果については、実際の介護現場でも多くの改善事例が報告されています。
例えば、愛の家グループホームでは、「人の役に立つ」ことを生きがいにされていた男性利用者が、得意な掃除作業を通じて他の利用者や職員との関係性を築き、表情が明るくなったケースがあります。
また、利用者同士のつながりから生まれる安心感も重要で、共同生活の中で自然に生まれる交流が、認知症の進行抑制によい影響を与えることが確認されています。
家庭においても、家事の手伝いや地域活動への参加など、「人の役に立つ」実感を得られる活動を見つけることが、認知機能の維持に効果的です。
これらの事例は、全国287ホームでの実践から得られた知見であり、家庭でのケアにも応用できる貴重な情報です。
【睡眠】質を高めて脳のゴミを洗い流す
睡眠は、単なる休息ではありません。
脳の健康を維持するための、非常に重要なメンテナンス時間です。
睡眠中、脳内では「グリンパティックシステム」という仕組みが働き、日中の活動でたまった老廃物を洗い流しています。
この老廃物の中には、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβも含まれています。
質のよい睡眠を十分にとることは、脳のゴミ掃除を促し、病気のリスクを遠ざけることにつながるのです。
睡眠の質を高めるための工夫は、以下の通りです。
- 毎日同じ時間に起き、朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 日中は適度な運動を心がける
- 就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控える
- 寝室は暗く、静かで快適な温度に保つ
- カフェインやアルコールの摂取は、就寝の数時間前までにする
単に長く寝るだけでなく、ぐっすりと深く眠る「睡眠の質」を意識することが、脳を守るためには不可欠です。
※参考:適切な睡眠で、認知症から脳を守る
■見落とされがちな「のどの健康」も重要
アルツハイマー病の予防において見落とされがちなのが、嚥下(えんげ)機能の維持です。
のどの筋力低下は誤嚥性肺炎のリスクを高めるだけでなく、栄養摂取不良により脳の健康にも影響を与える可能性があります。
健達ねっとでは、西尾正輝教授(国際医療福祉大学)監修による「ノドトレ」を提案しています。
これは30年の研究成果を元に開発された、1回わずか5秒の簡単な嚥下機能向上プログラムです。
日々の生活習慣に無理なく取り入れられ、のどの筋力維持を通じて、食事をより安全に楽しめます。
のどの健康は、栄養摂取の質に直結し、ひいては脳の健康維持にもつながる重要な要素です。
【禁煙・節酒】今からでも遅くない生活改善
喫煙と過度の飲酒が、アルツハイマー病のリスクを高めることは、数多くの研究で指摘されています。
喫煙は、動脈硬化を促進して脳の血流を悪化させるだけでなく、脳に直接的な酸化ストレスを与え、神経細胞を傷つけます。
また、過度のアルコール摂取は、脳を萎縮させ、認知機能の低下を招くことが知られています。
「もう年だから…」と諦める必要はありません。
禁煙や節酒は、何歳から始めても脳の健康によい影響をもたらします。
今日からできる具体的なステップは、以下の通りです。
- 禁煙: まずは本数を減らすことから始める。禁煙外来など専門家の助けを借りるのも有効
- 節酒: 週に2日以上の「休肝日」を設ける。飲む場合は、量を決めてゆっくり楽しむ
これらの習慣は、アルツハイマー病だけでなく、さまざまの生活習慣病の予防にもつながります。
自分の体と未来のために、今からでも生活改善に取り組む価値は十分にあります。
【生活習慣病の管理】高血圧・糖尿病は脳のサイレントキラー
高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、「脳のサイレントキラー」ともいえます。
これらの病気は、脳の細い血管にダメージを与え、動脈硬化を進行させます。
その結果、脳の血流が悪くなり、神経細胞に十分な酸素や栄養が届かなくなってしまうのです。
これは、アルツハイマー病のリスクを高めるだけでなく、脳梗塞や脳出血を原因とする「血管性認知症」の直接的な引き金にもなります。
生活習慣病の管理で大切なポイントは、以下の通りです。
- 定期的に健康診断を受け、自身の体の状態を把握する
- 医師の指示に従い、処方された薬はきちんと服用する
- 家庭で血圧や血糖値を定期的に測定し、記録する
- 塩分や糖分、脂肪分を控えたバランスのよい食事を心がける
生活習慣病と認知症の関係について詳しくは、生活習慣病と認知症予防の深い関係をご覧ください。
特に糖尿病が認知症リスクを高める理由や、高血圧管理の重要性について理解を深めましょう。
かかりつけ医とよく相談し、病気を適切にコントロールすることが、認知症予防の重要な柱となります。
親にどう伝える?生活習慣の改善を穏やかに提案する3つのコツ
予防法が分かっても、親にどう伝えればいいか悩む方は多いでしょう。
伝え方ひとつで、相手の受け取り方は大きく変わります。
命令ではなく「一緒に」スタンスで誘う
「健康のために運動しなさい」と一方的に指示されると、誰でも反発したくなるものです。
特に親世代は、子どもから命令されることに抵抗を感じる場合があります。
大切なのは、「あなたのため」というスタンスではなく、「私たちのために一緒にやろう」という誘い方です。
共通の目標を持つことで、親は「やらされる」のではなく、「協力する」という前向きな気持ちになりやすくなります。
具体的な誘い方の例は、以下の通りです。
- 「最近、運動不足だから、一緒にウォーキングを始めない?」
- 「新しい健康レシピを試したいんだけど、味見を手伝ってほしいな」
- 「テレビで脳トレクイズをやっていたから、どっちが早く解けるか競争しよう!」
親とのコミュニケーションに悩んでいる方は、親の心を解きほぐす「ナッジ」の魔法や介護をラクにするコミュニケーション術も参考にしてみてください。
あくまで対等な立場で、一緒に楽しむ仲間として誘うことが、スムーズな第一歩につながります。
本人のプライドを傷つけない
長年の人生経験を積んできた親にとって、プライドは非常に大切なものです。
「もの忘れがひどくなった」「これもできなくなったの?」といった、できないことを指摘する言葉は、相手の自尊心を深く傷つけ、心を閉ざす原因になります。
たとえ心配から出た言葉であっても、相手を否定するような表現は避けなければなりません。
重要なのは、相手の尊厳を守り、敬意を払う姿勢です。
言葉選びで気をつけたいポイントは、以下の通りです。
- 否定しない: 「それは違う」ではなく、「そういう考え方もあるんだね」と一度受け止める
- 比較しない: 「〇〇さんはできているのに」といった言葉は決して使わない
- 感謝を伝える: 「手伝ってくれてありがとう」「さすがだね」など、感謝や尊敬の気持ちを言葉にする
- 失敗を責めない: 「私もよくやるよ」と共感を示し、安心させる
相手をひとりの人間として尊重する当たり前の姿勢が、信頼関係を維持し、穏やかな対話を可能にします。
楽しさを重視する
生活習慣の改善は、長く続けることに意味があります。
そのためには、「義務」や「我慢」といったネガティブな要素をできるだけなくし、「楽しい」「嬉しい」というポジティブな感情と結びつける工夫が不可欠です。
本人が心から楽しめることを見つける手伝いをすることが、家族にできる最大のサポートといえるでしょう。
「楽しさ」を演出するためのアイデアは、以下の通りです。
- 目標をゲーム化する: ウォーキングの歩数を記録し、目標達成したらカレンダーにシールを貼る
- ご褒美を用意する: 減塩の食事を1週間続けたら、少しだけ好きなお菓子を一緒に食べる
- 環境を変える: いつもと違う公園まで散歩に行く、新しいレシピ本を買って一緒に料理する
- 趣味を活かす: 園芸が好きな親なら、ベランダで野菜を育てることを提案する
本人の興味や関心に合わせて、健康的な活動が自然と生活の一部になるようにサポートすることが理想です。
実際の認知症ケアの現場では、「6つの目指す状態」と「12の解決方法」を体系化したMCSケアモデルが、287ホーム3,821名の方々に85%以上の改善実績をもたらしています。
この手法から学べる家族向けのポイントをご紹介します。
- ■本人の「できること」に着目する
「できないこと」に注目しがちですが、現在できていることや得意なことを見つけて褒めることが重要です。
例えば、掃除が好きだった方には簡単な片付けをお願いし、感謝の言葉を伝えるなど、役割を感じてもらう関わり方が効果的です。 - ■具体的な数値目標を設定する
「水分を多めに」ではなく「1日1,800ml」、「たんぱく質を意識して」ではなく「1日80g」など、具体的な目標設定により、本人も家族も取り組みやすくなります。 - ■記録を共有する
日々の変化を記録し、家族で共有することで、小さな改善も見逃さず、継続的な支援につながります。
この記事でご紹介した生活習慣による認知症予防について、より専門的な知識を得たい方には、健達ねっとが取り扱う「認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣」をオススメします。
この書籍は、多くの認知症患者を診察してきた認知症専門医が、数多くの論文を分析して執筆したものです。
生活習慣や既往歴、趣味や嗜好まで、「認知予備能」をキーワードに、科学的根拠に基づいた予防方法を詳しく解説しています。
また、介護に携わる方向けには、管理栄養士監修の「ハルと思い出めぐりごはん」で、回想法を活用した食事レシピや、介護食への対応方法も学ぶことが可能です。
これらの専門書籍は、認知症予防と向き合う皆様の継続的な学習をサポートいたします。
まとめ:未来は今日の生活習慣から
アルツハイマー病のリスクは、日々の生活習慣を見直すことで低減できる可能性があります。
この記事では、科学的根拠に基づいた7つの具体的な習慣と、大切なご家族への伝え方のコツをご紹介しました。
- 食事、運動、知的活動、社会参加、睡眠、禁煙・節酒、生活習慣病の管理が予防の柱です。
- 完璧を目指す必要はありません。まずは「これならできそう」と思えることからひとつ、始めてみましょう。
その小さな一歩が、あなたとあなたの大切な家族の未来を、より明るく健やかなものへと導いてくれます。
「健達ねっと」は、これからも皆様の健康と暮らしに寄り添い、信頼できる情報をお届けしてまいります。