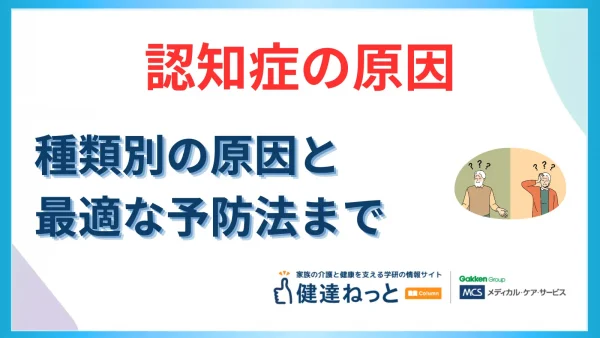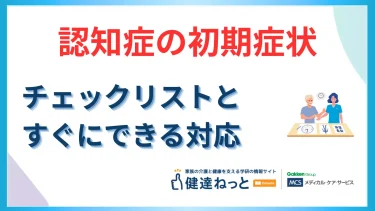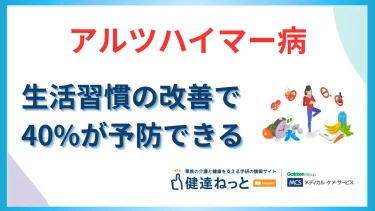- 「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」
- 「自分自身の記憶力に自信がなくなってきた…」
- 「認知症の原因ってそもそも何?予防できるなら対策したい」
- 「もし家族が認知症になったら、どうすればいいのだろう…」
このような不安や疑問を感じていませんか。
年齢を重ねるにつれて、ご自身や大切なご家族の健康について考える機会は増えるものです。
特に認知症は、誰にでも起こりうる身近な問題でありながら、漠然とした不安を抱きやすいテーマといえます。
この記事では、そのような不安を解消し、前向きな一歩を踏み出すために必要な情報を網羅的に解説します。
この記事を読めば、以下のポイントが明確になるでしょう。
- 認知症の正しい知識と、原因となる4つの代表的な病気
- 認知症のリスクを高める14の最新要因
- 科学的根拠に基づき、今日から実践できる5つの予防法
- 認知症の進行を早める原因と、家族ができる具体的な対処法
認知症は「なったら終わり」ではありません。
原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、発症や進行を遅らせることが可能です。
この記事が、あなたとあなたの大切な家族の、健やかで安心な未来を守るための一助となれば幸いです。
スポンサーリンク
そもそも認知症とは?原因の前に知るべき基礎知識
認知症の原因を理解する前に、まずは「認知症とは何か」という基本的な知識を整理しましょう。
正しい知識は、漠然とした不安を解消し、適切な対応をとるための第一歩となります。
認知症は特定の病名ではなく、症状の総称(症候群)
認知症とは、ひとつの病気の名前ではなく、さまざまな原因によって脳の機能が低下し、日常生活に支障が出ている「状態」を指す言葉です。
厚生労働省によると、認知症では記憶力だけでなく、時間や場所が分からなくなる、計画を立てて物事を実行できないなど、複数の認知機能に障害が見られます。
この状態は、原因となる病気に応じた適切なケアによって、症状の改善が期待できます。
実際に、健達ねっとを運営するメディカル・ケア・サービス株式会社では、科学的根拠に基づく「MCSケアモデル」を通じて、認知症の方の85%以上で周辺症状や心身の状態改善を実現しています。
「認知症によるもの忘れ」と「加齢によるもの忘れ」の違い
「最近もの忘れが多いから、認知症かもしれない」と心配になる方も多いかもしれません。
しかし、加齢による自然なもの忘れと、病的な認知症によるもの忘れには、明確な違いがあります。
厚生労働省の資料によれば、加齢によるもの忘れは「体験したことの一部」を忘れるのに対し、認知症は「体験したことのすべて」を忘れてしまうという特徴があります。
この違いを理解しておくことが、変化に早く気づくための重要なポイントです。
| 項目 | 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ |
|---|---|---|
| 忘れる範囲 | 体験の一部(例:夕食のメニュー) | 体験の全体(例:夕食を食べたこと自体) |
| 自覚 | もの忘れの自覚がある | もの忘れの自覚がないことが多い |
| 進行 | あまり進行しない | ゆっくりとだが確実に進行する |
| 日常生活 | 大きな支障はない | 支障が出てくる |
| 探し物 | あれば思い出せる | 探したこと自体を忘れてしまう |
例えば、認知症による記憶障害があっても、感情を伴う記憶は残りやすいといわれています。
健達ねっとの「愛の家グループホーム帯広東12条」では、武田清子さん(仮名)が5年経っても夫との思い出を鮮明に覚えていたという事例もあり、心に寄り添うケアの重要性を示しています。(引用元:施設事例)
認知症の初期症状について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」「さっき言ったことを何度も聞いてくるのは、年のせい?」「もしかして、認知症の始まり…?」ご家族のささいな変化に、このような不安を抱えていませんか。その不安の裏には、「この先ど[…]
日本の認知症患者の現状と将来設計
日本は世界でもトップクラスの長寿国ですが、それに伴い認知症の方も増加しており、もはや他人事ではない社会全体の課題となっています。
2024年5月に厚生労働省が公表した最新データによると、65歳以上の高齢者における認知症の有病率は12.3%、その前段階である軽度認知障害(MCI)は15.5%にのぼります。
これは、高齢者の約4人に1人が認知症またはそのリスクを抱えている計算です。
この傾向は今後も続くと見られ、2040年には認知症高齢者が584.2万人(高齢者の約7人に1人)に達すると予測されています。
このような社会状況を受け、健達ねっとでは全国の小中学校で「認知症教育の出前授業」を実施し、次世代への理解を広める活動にも力を入れています。
認知症の進行段階について詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
認知症の方と関わるうえで知っておきたい認知症の進行段階や進行スピード。初期から末期までその症状はさまざまですが、どのように進行し症状が現れるのでしょうか?今回、認知症がどのように進行するのかご紹介した上で、その特徴や対策方法につ[…]
スポンサーリンク
4大認知症の発生原因とそれぞれの特徴
認知症を引き起こす原因となる病気は70種類以上あるといわれていますが、その中でも特に多いのが「4大認知症」です。
それぞれの原因と特徴を知ることで、より具体的な対策を考えられます。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、認知症の原因として最も多く、全体の過半数を占めています。
脳に「アミロイドβ」や「タウ」という特殊なタンパク質が異常に蓄積し、神経細胞を傷つけることで発症します。
初期には新しいことを覚えられないといった「もの忘れ」から始まり、ゆっくりと進行するのが特徴です。
しかし、適切なケアによって進行を穏やかにすることは可能です。
健達ねっとの「MCS版自立支援ケア」では、水分やタンパク質の摂取、個別の運動プログラムといった科学的根拠に基づくケアにより、85%以上の方で状態改善という高い実績を上げています。
アルツハイマー病の詳しい症状や診断については下記をご覧ください。
「最近、親のもの忘れがひどくなった気がする…」「もしかして、アルツハイマー型認知症の始まり…?」「もしそうなら、もう治らないの…?」親の些細な変化に、このような不安を感じていませんか。大切な家族だからこそ、心配は尽きず、[…]
血管性認知症
血管性認知症は、アルツハイマー型に次いで多い認知症です。
脳梗塞や脳出血といった脳卒中(脳血管障害)によって脳の神経細胞がダメージを受けることが原因で発症します。
高血圧や糖尿病などの生活習慣病が主な引き金となり、症状がよくなったり悪くなったりを繰り返しながら、階段状に進行する「まだら認知症」も特徴のひとつです。
愛知県弥富市の「愛の家グループホーム弥富」では、脳出血後遺症のある方が、地域住民の温かい見守りの元、一人で散歩できるまでに改善した事例もあり、生活習慣の管理と社会的な支えの重要性を示しています。
(引用元:施設事例)
血管性認知症の特徴について詳しくは以下で解説しています。
脳血管性認知症は、三大認知症の一つです。しかし脳血管性認知症は、その他の認知症と異なり、予防が可能です。予防するためにも、脳血管性認知症の特徴について、理解しておく必要があります。本記事では、脳血管性認知症の症状や原因、その他の[…]
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、認知症全体の10~15%を占めるといわれています。
脳の神経細胞に「レビー小体」という異常なタンパク質が蓄積することが原因で発症します。
記憶障害よりも先に、以下のような特有の症状が現れることが多いのが特徴です。
- 具体的な幻視:「そこに人がいる」など、実際にはないものがハッキリと見える
- 認知の変動:頭がハッキリしている時と、ボーっとしている時が波のように繰り返される
- パーキンソン症状:手足の震え、筋肉のこわばり、小刻み歩行など
- レム睡眠行動異常症:睡眠中に大声で叫んだり、暴れたりする
2025年3月には新たな関連遺伝子が発見されるなど、研究が進められている分野でもあります。
レビー小体型認知症の症状や診断基準について詳しく知りたい方は下記で解説しています。
アルツハイマー型認知症、血管性認知症と並んで三大認知症の1つでもあるレビー小体型認知症。認知症は種類によって、原因や前兆、症状が異なります。本記事では、レビー小体型認知症の原因について以下の点を中心に解説します。[…]
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、思考や理性をコントロールする「前頭葉」と、言語を担う「側頭葉」が萎縮することで発症します。
65歳未満で発症する若年性認知症の原因としても比較的多いのが特徴です。
初期症状として、もの忘れよりも人格の変化や行動異常が目立ちます。
例えば、社会のルールを守れなくなったり、同じ行動を何度も繰り返したりします。
記憶力は保たれていることが多いため、周囲から誤解されやすく、病気への正しい理解が特に重要です。
その他
これまで紹介した4大認知症のほかにも、さまざまな原因で認知症は起こります。
中には、正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫のように、原因となる病気を早期に治療することで症状が改善・回復する可能性のある「治る認知症」も存在します。
気になる症状があれば、自己判断せずに専門医に相談することが大切です。
認知症の発症数の上位を占める三大認知症。種類によって認知症の症状や原因はさまざまです。皆様は、種類ごとの特徴や違いをご存知でしょうか?本記事では、三大認知症について以下の点を中心にご紹介します。三大認[…]
【要注意】認知症のリスクを高める14の要因
認知症の発症には、年齢や遺伝だけでなく、長年の生活習慣が深く関わっていることが分かっています。
2024年8月にイギリスの医学誌「ランセット」が発表した最新報告では、14の修正可能なリスク要因をすべて解消することで、世界の認知症の45%は予防できる可能性があると示されました。
ここでは、特に重要な要因を解説します。
難聴
難聴は、認知症の最も大きなリスク要因とされています。
耳からの音の刺激が減ることで脳の活動が低下し、また、会話が困難になることで社会的に孤立しやすくなるためです。
日本では1,400万人以上が加齢性難聴を患っているといわれ、補聴器の使用など早期の対策が認知機能の低下を防ぐ鍵となります。
難聴と認知症の関係については以下でも詳しく解説しています。
耳の聞こえにくさを感じたとしても、加齢によるものだとそのままにしていませんか?難聴を軽視することは、認知症の発症を進めることに繋がりかねません。この記事では、難聴と認知症の関係について以下を中心にご紹介します。[…]
頭部外傷
過去に頭を強く打った経験も、認知症のリスクを高めます。
スポーツや交通事故などで意識を失うほどの頭部外傷を負うと、脳の神経細胞がダメージを受け、将来的に認知症を発症しやすくなる可能性があります。
日常生活では、転倒予防やヘルメット着用など、頭部を守る意識が大切です。
高血圧
中年期(40〜65歳)の高血圧は、認知症の重要なリスク要因です。
血圧が高い状態が続くと脳の血管がダメージを受け、血管性認知症やアルツハイマー型認知症のリスクを高めます。
塩分を控えた食事や適度な運動、必要に応じた服薬など、早期からの血圧管理が将来の認知症予防につながります。
WHOが推奨する高血圧管理による認知症予防については以下も参考にしてみてください。
認知症は脳の認知機能に障害が現れる病気で、主に加齢が原因で発症します。WHOは認知症リスク低減のためのポイントとして「高血圧の管理」を指摘しています。高血圧と認知症にはどのような関係があるのでしょうか?認知症のリスクを低減す[…]
過度の飲酒
長期間にわたる過度な飲酒は、脳を萎縮させ、認知機能を低下させる直接的な原因となります。
また、ビタミンB1の欠乏によるアルコール性認知症を発症するリスクもあります。
厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は1日平均純アルコールで20g程度です。
休肝日を設けるなど、お酒との付き合い方を見直しましょう。
肥満
中年期の肥満も、認知症のリスクを高める要因のひとつです。
肥満は、高血圧や糖尿病などを引き起こしやすく、これらが間接的に認知症の原因となります。
また、肥満自体が脳の炎症を引き起こす可能性も指摘されています。
適正体重を維持するための食生活や運動習慣が大切です。
喫煙
喫煙は、認知症発症のリスクを高めるとされています。
タバコに含まれる有害物質は、動脈硬化を促進して脳の血流を悪化させるほか、脳の神経細胞を直接傷つけることも分かっています。
禁煙は、いつから始めても遅すぎることはありません。
ご自身の健康のためにも、禁煙に取り組むことが強く推奨されます。
うつ病
高齢期のうつ病は、認知症のリスクを高めることが報告されています。
うつ病になると物事への関心や意欲が低下し、脳への刺激が少なくなりがちです。
また、ストレスホルモンが記憶を司る「海馬」を萎縮させる可能性も指摘されています。
気分の落ち込みが続く場合は、早めに専門医に相談することが大切です。
社会的孤立
他者との交流が少なく、社会的に孤立している状態も、認知症のリスクを高める要因です。
人との会話は、脳のさまざまな領域を使う高度な知的活動であり、認知機能を維持するための重要な刺激となります。
趣味のサークルに参加するなど、積極的に社会と関わる機会を持つことが認知症予防につながるのです。
健達ねっとでは、浦和レッズとの連携事業などを通じて、高齢者の方が地域社会とつながる場を提供しています。
>参考:浦和レッズ連携事業
運動不足
習慣的な運動が不足していると、認知症のリスクが高まります。
運動は、脳の血流を改善し、神経細胞の成長を促す物質を増やす効果があります。
また、生活習慣病の予防やストレス解消など、他のリスク要因を減らす効果も期待できるのです。
ウォーキングなど気軽に始められるものから生活に取り入れましょう。
大気汚染
近年、大気汚染も認知症のリスク要因として注目されています。
自動車の排気ガスなどに含まれる微小粒子状物質が、体内で炎症を引き起こし、脳の神経細胞にダメージを与えると考えられています。
交通量の多い道路沿いを避けて散歩するなど、少しの工夫がリスク低減につながるかもしれません。
糖尿病
糖尿病、特に2型糖尿病は、認知症のリスクを高めることが分かっています。
高血糖の状態は血管を傷つけ、脳梗塞などのリスクを高めることが可能です。
また、血糖値を下げるインスリンが効きにくくなる状態は、アルツハイマー型認知症の原因物質の分解を妨げると考えられています。
血糖値のコントロールは、認知症予防においても非常に重要です。
糖尿病をはじめとする生活習慣病と認知症の関係については、専門医が解説した以下の記事をご確認ください。
東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科荒木 厚 先生生活習慣病を改善することで、認知症を予防できる近年、わが国では、欧米型の生活様式への変化により、糖尿病、肥満症などの生活習慣病が増えています。これらの疾患は認[…]
ストレス
慢性的なストレスも認知症の危険因子と考えられています。
過度なストレスは、うつ病のリスクを高めるほか、ストレスホルモンを介して脳の海馬を傷つけ、記憶力を低下させる可能性があります。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身の健康を保つことが大切です。
ストレスと認知症の関係について詳しく知りたい方は以下も参考にしてみてください。
高齢化が進む日本において、年々増加している認知症。種類によっては、症状や原因は大きく異なります。私たちにとって身近なストレスも原因になり得ることを知っていますか?本記事では、ストレスと認知症の関係について以下の点[…]
視力障害(2024年新追加)
2024年のランセット委員会報告書で新たに追加されたリスク要因のひとつが視力障害です。
視力の低下により外部からの刺激が減少し、認知機能の低下につながる可能性が指摘されています。
適切な眼科検診と視力矯正が認知症予防に重要であることが示されています。
高コレステロール(2024年新追加)
もうひとつの新たなリスク要因が中年期の高LDLコレステロールです。
LDLコレステロール値の上昇は血管性疾患のリスクを高め、間接的に認知症の発症リスクを増加させると考えられています。
今からできる認知症の予防・進行を遅らせる5つの方法
認知症のリスク要因を知ると不安になるかもしれませんが、その多くは日々の生活を見直すことで対策が可能です。
ここでは、科学的にも効果が期待されている5つの予防法を紹介します。
地中海食やDASH食を参考にバランスのよい食事を摂る
認知症予防において、食生活は非常に重要な役割を果たします。
特に、地中海沿岸の伝統的な食事「地中海食」や、高血圧予防のための「DASH食」は、認知機能の維持に役立つことが多くの研究で示されています。
これらの食事は、果物、野菜、全粒穀物、魚、オリーブオイルなどを中心とした栄養バランスのよいものです。
健達ねっとの「MCS版自立支援ケア」でも、科学的根拠に基づいた栄養管理によって、認知症状の改善を実現しています。
日々の食事の補助として、健達ショップの機能性表示食品などを活用するのもひとつの方法です。
認知症予防に効果的な食事について詳しくは以下をご覧ください。
私たちの体には、食事から摂取する栄養が欠かせません。栄養バランスを考えた食事は体を動かすエネルギー源になると同時に、認知症予防にも効果的とされています。今回は、認知症の発症を防ぐ栄養素やそれを含む食物、予防に適した食事を紹介します。[…]
ウォーキングなどの有酸素運動や筋トレなど適度な運動をする
運動は、認知症予防の柱のひとつであり、その効果は科学的に証明されています。
運動には、脳の血流を促進するだけでなく、神経細胞の保護や再生を促す効果も期待できるのです。
厚生労働省の資料でも、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることが推奨されています。
無理のない範囲で、週に2〜3回、1回30分程度から始めるのがオススメです。
健達ねっとでは、個々の身体状況に合わせたオリジナルの運動プログラムを開発し、その普及に努めています。
(参考:SIDE別運動プログラム)
認知症予防に効果的な運動方法について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
認知症は、加齢とともに誰でも発症する可能性があります。「認知症になるのは仕方ない」と諦めるのではなく、徹底した認知症予防が重要です。様々な認知症予防法がありますが、「運動」が効果的であることを知っていますか?今回は認知症に対する[…]
読書・ゲーム・新しいことへの挑戦で脳を活性化させる
脳も体と同じで、使わなければ機能が衰えていきます。
日頃から頭を使う習慣を持つことは、脳の神経ネットワークを強化し、認知症になりにくい脳(認知予備能)を作ることにつながります。
読書やゲーム、楽器の演奏、新しいことへの挑戦など、楽しみながら継続できる活動が脳の活性化に効果的です。
認知症の前段階であるMCIと診断されても、1年で約16〜41%の方が健常な状態に回復するといわれており、このような認知トレーニングが回復を後押しする可能性があります。
脳トレーニングの具体的な方法についてはこちらの記事をご参照ください。
テレビやゲームなどをきっかけに、「脳トレ」という言葉を知っている方は多いのではないでしょうか?また、超高齢社会に突入したことにより、認知症の予防と脳トレに興味がある方も多いはずです。本記事では、認知症予防と脳トレについて以下の項[…]
社会参加により人との交流で刺激を得る
人とのコミュニケーションは、脳にとって非常に高度な活動です。
相手の話を聞き、理解し、自分の考えを言葉にして伝えるプロセスは、脳のさまざまな機能を同時に使います。
社会的孤立は認知症の大きなリスク要因であるため、友人との会話や地域のイベントへの参加など、人とのつながりを大切にしましょう。
健達ねっとでは、「愛の家こども食堂」の運営などを通じて、認知症の方が社会とつながり続ける機会を創出しています。
質のよい睡眠をとって脳の老廃物を除去する
睡眠は、単に体を休めるだけでなく、脳の健康を保つためにも不可欠です。
眠っている間に、脳内では日中の活動で溜まった老廃物が洗い流されています。
アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβもこの仕組みで除去されるため、睡眠不足や質の低下は認知症のリスクを高めます。
質のよい睡眠を確保するため、毎日同じ時間に寝起きする、適度な運動をするといった工夫を心がけましょう。
健達ねっとでは、嚥下機能を高める「ノドトレ」を提供しており、睡眠時無呼吸症候群の改善にも貢献します。
睡眠と認知症の関係について専門医が以下で詳しく解説しています。
睡眠と物忘れの問題は、加齢とともに増えていきます。今回は、老年期の睡眠障害の特徴、睡眠障害と認知症の複雑な関係、そして、睡眠障害を改善し、認知症のリスクを下げるにはどのような生活をするのがよいかについてお話しした[…]
認知症が一気に進む原因とは?急な変化があった時の対処法
認知症はゆっくり進行することが多いですが、ある出来事をきっかけに、症状が急激に悪化したように見えることがあります。
その原因と、家族ができる対処法を知っておくことは、本人と家族の負担を減らすために非常に重要です。
急激な環境の変化(入院・引っ越し・介護者の交代)
認知症の方にとって、環境の変化は非常に大きなストレスとなり、混乱や不安を引き起こす最大の要因のひとつです。
入院や施設への入所、引っ越し、親しい介護者の交代といった出来事は、時間や場所が分からなくなる見当識障害を悪化させ、せん妄(意識の混濁)などを引き起こす原因となります。
このような急な状態の変化が、周囲からは「認知症が一気に進んだ」ように見えてしまうのです。
健達ねっとの施設では、環境が変わっても本人の世界観を否定しません。
例えば「仕事に来ている」という認識の方には洗濯物たたみをお願いするなど、その方の世界に合わせた支援を行うことで、不安の軽減を図っています。
入院による認知症悪化の詳しいメカニズムと対策については以下を参考にしてみてください。
超高齢社会の日本において、年々増加している認知症。認知症は家族の介護負担が大きく、入院する方も多いです。医療体制が整った環境であれば、家族の方も安心できます。一方で、入院生活によって認知症が悪化してしまった方がいるのも事実です。[…]
身体的な不調(感染症・脱水・便秘・薬の副作用)
認知症の方は、ご自身の体調不良をうまく言葉で伝えられないことがよくあります。
感染症や脱水、便秘、薬の副作用といった身体的な不調は、脳の働きに直接影響し、せん妄などを急激に悪化させる原因となります。
普段と様子が違うと感じたら、まずは身体的な問題がないかを確認することが大切です。
健達ねっとの「MCS版自立支援ケア」では、水分摂取の徹底や医師と連携した減薬など、身体状態を整えることからアプローチし、認知症状の改善につなげています。
精神的なストレス(不安・孤独・叱責される経験)
認知症の方は、記憶や判断力が低下していても、感情は豊かに残っています。
そのため、失敗を強く叱責されたり、言動を頭ごなしに否定されたりする経験は、強いストレスとなり、不安や興奮、うつ状態などを引き起こします。
これにより、徘徊や物盗られ妄想といった症状が悪化することがあるのです。
健達ねっとの施設では、「家に帰りたい」という訴えに対しても、思いを否定せずに寄り添い、本人の不安な気持ちを受け止めるケアを実践しています。
認知症の方の不穏状態への対処法については、以下で詳しく解説しています。
超高齢社会の日本において、年々増加している認知症。認知症の症状は多岐に渡り、介護者の負担が大きいものばかりです。その中でも、不穏症状に戸惑っている家族も多いのではないでしょうか?不穏の原因や対処法を把握し、症状を改善させることが[…]
家族や周囲が本人のためにできること
認知症の進行を穏やかにするためには、家族や周囲の人の関わり方が非常に重要です。
健達ねっとの豊富な施設体験談からは、以下のようなポイントが有効であることが分かっています。
- 本人のペースを尊重する:急かしたりせず、本人が自分のペースで行動できるように見守る。
- 役割を持って生きがいを:掃除など、本人が得意なことで役割を持ってもらい、自信や生きがいを感じられるように支援する。
- 思いや希望を否定しない:「食べたい」「行きたい」といった本人の思いを受け止め、可能な範囲で実現する手伝いをする。
- 安心できる環境を作る:穏やかで一貫した対応を心がけ、本人が安心して過ごせる環境を整える。
これらの対応は、認知症の進行を遅らせるだけでなく、ご本人の尊厳を守り、穏やかな生活を支える上で不可欠です。
まとめ
この記事では、認知症の原因となる4大疾患から、最新の研究で明らかになったリスク要因、そして今日から実践できる予防法まで、幅広く解説しました。
認知症の原因は多岐にわたりますが、決して「なったら終わり」の病気ではありません。
医学誌「ランセット」の最新報告が示すように、生活習慣の見直しなどによって認知症の45%は予防・進行遅延が可能であるという事実は、私たちに大きな希望を与えてくれます。
重要なのは、原因を正しく理解し、ご自身や家族に合った対策を早期から始めることです。
健達ねっとを運営するメディカル・ケア・サービスでは、科学的根拠に基づく「MCSケアモデル」により、ご入居者様の85%以上で状態改善という実績を上げています。
これは、適切なケアと周囲のサポートによって、認知症の方がその人らしい穏やかな生活を続けられる可能性を証明するものです。
この記事で得た知識を元に、まずは生活習慣をひとつ見直す、家族と話し合うきっかけにするなど、あなたにできる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
その小さな一歩が、あなたと大切な人の未来を守る大きな力となるはずです。