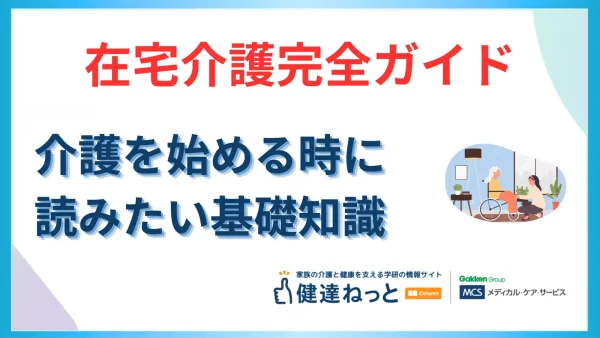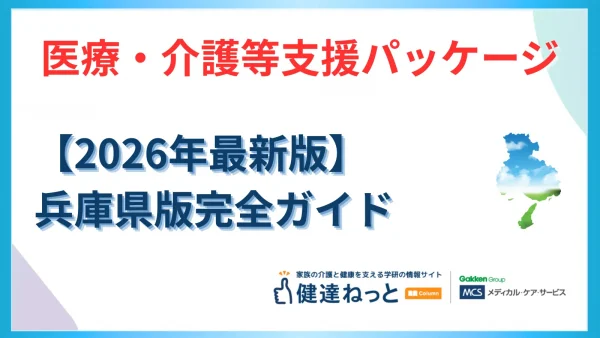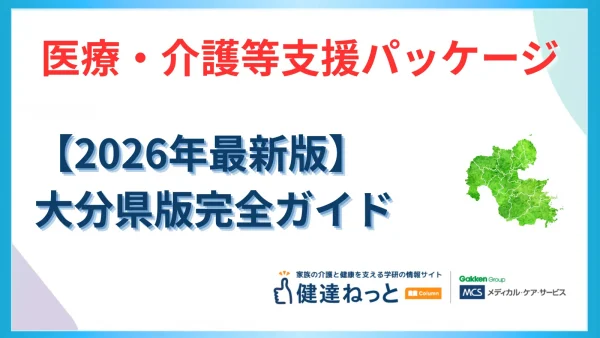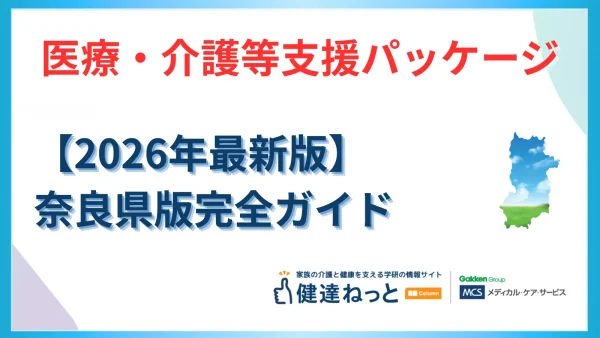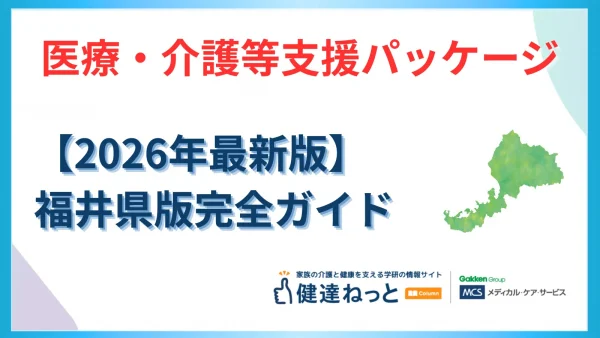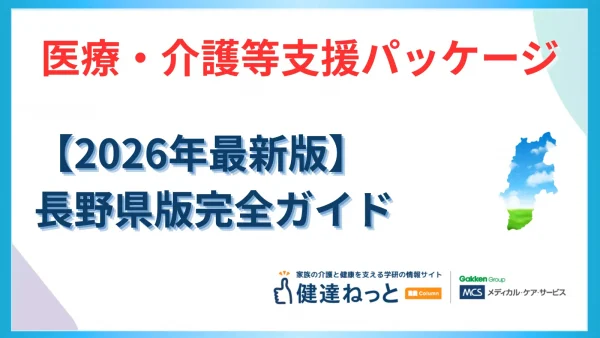- 「親の介護、そろそろ考えないと…でも、何から始めればいいんだろう?」
- 「在宅介護って、費用はどれくらいかかるの?」
- 「仕事と介護の両立なんて、本当にできるんだろうか…」
- 「もし自分が倒れたら…と考えると、夜も眠れない」
このような不安を抱えながら、在宅介護という大きなテーマを前に、たったひとりで立ちすくんでいませんか。
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
大切な家族を支えたいという愛情と、自分の生活を守りたいという現実の間で、心が揺れ動くのは当然のことです。
この記事は、そのようなあなたのための「羅針盤」です。
複雑で分かりにくい在宅介護の全体像を、専門的な知見に基づき、どこよりも分かりやすく解き明かします。
この記事を読むことで、あなたは以下の情報を手に入れられます。
- 在宅介護で使えるサービスの種類と、その賢い使い方
- 要介護認定からサービス開始までの具体的な7つのステップ
- 気になる費用の目安と、負担を軽くするための公的制度
- 「共倒れ」を防ぎ、家族みんなで乗り越えるための5つの戦略
読み終える頃には、漠然とした不安が「こうすればいいのか!」という具体的な安心と希望に変わり、明日から何をすべきかが明確になっているはずです。
さあ、一緒に未来への確かな一歩を踏み出しましょう。
また、在宅介護については以下の連載マガジンも参考にしてみてください。
スポンサーリンク
在宅介護とは?施設介護との違いの基礎知識
在宅介護を考える上で、まずその基本的な定義と、施設介護との違いを正しく理解しておくことが大切です。
どのような選択肢があり、それぞれにどのような特徴があるのかを知ることで、ご本人やご家族にとって最適な介護の形を見つけるための第一歩となります。
在宅介護は「住み慣れた家」で暮らし続けるための選択肢
在宅介護とは、その名の通り、介護が必要な状態になっても施設に入所せず、これまで生活してきたご自宅で介護サービスを受けながら暮らし続ける介護の形を指します。
訪問介護やデイサービスといったさまざまな「居宅サービス」を組み合わせ、一人ひとりの心身の状態や生活環境に合わせたオーダーメイドのケアプランを作れるのが特徴です。
何よりも、長年愛着のある我が家で、家族や親しい人々に囲まれながら、自分らしい生活リズムを維持できるという点は、ご本人にとって大きな精神的な支えとなるでしょう。
住環境が変わらないため、環境の変化によるストレスが少なく、心穏やかに過ごせるといったメリットがあります。
施設介護と比較したメリットとデメリット
在宅介護は多くの利点がある一方、ご家族の協力が不可欠となる側面もあります。
施設介護と比較した場合のメリット・デメリットを正しく理解し、ご家族の状況と照らし合わせて検討することが重要です。
| 項目 | 在宅介護 | 施設介護 |
| メリット | ・住み慣れた環境で生活できる ・家族との時間を保ちやすい ・個別性の高いケアが可能 ・費用を抑えられる場合がある | ・24時間体制の専門的ケア ・家族の介護負担が少ない ・緊急時の対応が迅速 ・他の入居者との交流がある |
| デメリット | ・家族の身体的、精神的負担 ・緊急時の対応に不安 ・住宅改修が必要な場合がある ・社会的孤立のリスク | ・住環境が大きく変わる ・集団生活への適応が必要 ・費用が高額になる場合がある ・面会時間などの制約 |
全国でグループホームを運営するメディカル・ケア・サービス(MCS)の実践データでは、たとえ認知症があっても、在宅に近い環境で築かれた職員との信頼関係が記憶に残り続ける事例が報告されています。
これは在宅介護のメリット・デメリットを考える上で、住み慣れた環境や人間関係がもたらす効果の大きさを示唆しているといえるでしょう。
在宅介護を支えるのは在宅医療
在宅介護を継続していく上で、介護サービスと並行して考えなければならないのが「在宅医療」との連携です。
厚生労働省では、「できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す」とする在宅医療・介護の推進方針を示しています。
高齢になると、多くの方が何らかの持病を抱えていたり、体調を崩しやすくなったりします。
そのため、介護の専門家であるケアマネジャーだけでなく、かかりつけ医や訪問看護師といった医療の専門家との連携が不可欠になります。
日々の健康管理や服薬指導、急な体調変化への対応、そして人生の最終段階におけるケアまで、医療チームがそばにいてくれる安心感は、在宅介護を力強く支える土台となるのです。
特に認知症の方の在宅介護では、医療との連携が症状の安定につながることも少なくありません。
そのノウハウを元に、介護に関して以下の書籍も出版しています。
あわせて参考にしてみてください。
・介護のことになると親子はなぜすれ違うのか ナッジでわかる親の本心
・お互いが歩み寄る介護実践 45のヒント
・介護・ケアワークの「なぜ?何?」クエスチョン
スポンサーリンク
在宅介護で武器となるサービス一覧
在宅介護は、ご家族だけで抱え込むものではありません。
介護保険制度には、あなたの介護を支えるための強力な「武器」となるサービスが数多く用意されています。
これらのサービスを賢く組み合わせることで、ご本人の自立を支援し、ご家族の負担を大きく軽減することが可能です。
自宅に来てもらう「訪問サービス」
専門スタッフがご自宅を訪問し、日常生活のサポートや専門的なケアを提供するサービスです。
厚生労働省の定義では、「訪問介護」とは、訪問介護員等が、利用者(要介護者等)の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものです。
住み慣れた環境を離れることなく、必要な支援を受けられるのが最大のメリットといえます。
主な訪問サービスには、以下の通りです。
- 訪問介護(ホームヘルプ):食事や入浴、排泄などの「身体介護」と、掃除や洗濯、買い物などの「生活援助」
- 訪問看護:看護師が訪問し、健康状態のチェックや医療処置、服薬管理など
- 訪問入浴:専用の浴槽を自宅に持ち込み、入浴の介助
- 訪問リハビリテーション:理学療法士などが訪問し、身体機能の維持・回復のためのリハビリを実施
訪問介護サービスは在宅介護の基本となり、医療的ケアが必要な場合は訪問看護サービスとの連携が重要です。
日中の居場所とリハビリができる「通所サービス」
ご本人が日中に施設へ通い、食事や入浴、レクリエーション、機能訓練などを受けるサービスです。
厚生労働省によると、通所介護は「利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、また、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的」とするサービスです。
家にこもりがちになるのを防ぎ、心身機能の維持や社会的な交流を促す目的があります。
また、ご家族にとっては、日中の介護負担が軽減され、ご自身の時間を持てる「レスパイトケア」としての役割も大きいのが特徴です。
代表的な通所サービスは以下の通りです。
- 通所介護(デイサービス):生活機能の維持・向上を目指し、さまざまなレクリエーションや他の利用者との交流
- 通所リハビリテーション(デイケア):医師の指示の元、より専門的なリハビリテーションに重点を置いたサービスを提供
日中の居場所としてデイサービスを利用したり、身体機能の改善を目指してデイケアに通ったりと、目的に応じて選ぶことが可能です。
介護者の休息と緊急時対応ができる「宿泊サービス」
介護者が病気や冠婚葬祭、あるいは休息を取りたい時などに、短期間だけ施設に宿泊して介護を受けられるサービスです。
在宅介護を長く続けていくためには、介護者が休息を取り、心身をリフレッシュさせることが不可欠です。
このようなレスパイトケアの目的で計画的に利用することで、共倒れを防ぎ、在宅介護の継続性を高められます。
宿泊サービスには、主に2つの種類があります。
- 短期入所生活介護(ショートステイ):特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ):介護老人保健施設などに入所し、看護や医学的管理の元での介護、機能訓練など
ご本人の状態に合わせて、適切な施設を選ぶことが大切です。
24時間・柔軟な対応ができる「複合型・地域密着型サービス」
より多様なニーズにきめ細かく応えるため、「訪問」「通所」「宿泊」を組み合わせたサービスや、お住まいの地域に根差したサービスも整備されています。
特に、住み慣れた地域での生活を継続したいと願う方々にとって、心強い支えとなるでしょう。
個別のニーズに対応する主なサービスは以下の通りです。
- 小規模多機能型居宅介護:ひとつの事業所が「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」を柔軟に組み合わせて提供
- 看護小規模多機能型居宅介護:小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」の機能が加わり、医療ニーズの高い方にも対応可能
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:24時間365日、定期的な訪問と随時の通報に対応し、切れ目のないケアを提供
これらのサービスは、なじみのスタッフから継続的なケアを受けられるというメリットがあります。
保険の枠を超えて支える「保険外・自治体サービス」
介護保険サービスは、できることや利用回数に規定があります。
その枠だけではカバーしきれないニーズに応えるのが、保険外の自費サービスや、各自治体が独自に行う支援サービスです。
例えば、ご家族のための家事代行や通院以外の外出の付き添い、安否確認の電話サービスなど、内容は多岐にわたります。
MCSが開発した「MCS版自立支援ケア」は、科学的根拠に基づくアセスメントでご本人の状態を把握し、自立を支援するケアモデルです。
このような科学的アプローチは在宅介護にも応用可能で、保険サービスと組み合わせることで、より質の高い生活を目指せます。
「認知症を超える。」をブランドメッセージとし、認知症高齢者対応のグループホーム「 愛の家」を主軸に介護事業所を300か所…
介護保険サービスを主軸としながら、これらのサービスを賢く補完的に利用することで、より柔軟で豊かな在宅生活を実現することが可能になります。
自宅での自立した生活を援助することを居宅介護支援と言います。少子高齢化が進む日本で、居宅介護支援は重要な役割を担っています。居宅介護支援事業所とはどのような役割を持つのでしょうか?また、どのようなサービスを提供するのでしょうか?[…]
要介護認定からサービス開始までの在宅介護の完全ロードマップ
在宅介護を始めるには、まず公的な「ものさし」である要介護認定を受け、介護の必要度を判定してもらう必要があります。
手続きは複雑に感じるかもしれませんが、ひとつずつステップを踏んでいけば大丈夫です。
ここでは、相談からサービス開始までの流れを7つのステップに分けて解説します。
ステップ1.相談
介護に関する悩みや不安が生じたら、まずはお住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談しましょう。
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支える総合相談窓口で、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーといった専門家が無料で相談に乗ってくれます。
厚生労働省によると、地域包括支援センターの主な業務は「介護予防支援および包括的支援事業(1.介護予防ケアマネジメント業務、2.総合相談支援業務、3.権利擁護業務、4.包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)」です。
何から始めればよいか分からない、という段階でも親身に対応し、必要な手続きや利用できるサービスについて教えてくれる、在宅介護の最初のパートナーです。
ステップ2.申請
介護保険サービスを利用するためには、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行う必要があります。
申請には、申請書と介護保険被保険者証、そしてマイナンバーカードなどが必要となります。
ご本人が申請に行くのが難しい場合は、ご家族や地域包括支援センター、すでに入院・入所している施設などが代理で申請することも可能です。
要介護認定の申請手続きの詳細は、お住まいの自治体のウェブサイトなどで確認しておくとスムーズです。
ステップ3.認定調査
申請を行うと、市区町村の認定調査員がご自宅などを訪問し、ご本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。
この認定調査は、介護の必要度を判断するための非常に重要なプロセスです。
調査員は、麻痺の有無や日常生活の動作、認知機能、コミュニケーション能力など、全国共通の基準に基づいた項目について質問をします。
ご本人のありのままの状況を正確に伝えるため、ご家族もぜひ同席し、普段の様子や困っていることなどを具体的に補足説明しましょう。
ステップ4.審査・認定結果の通知
認定調査の結果と、かかりつけ医が作成する「主治医意見書」を元に、コンピュータによる一次判定が行われます。
その後、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、一次判定の結果や調査の特記事項などを総合的に審査し、最終的な要介護度を判定(二次判定)します。
要介護度は、「自立(非該当)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の8段階に区分され、申請から原則30日以内に結果が通知されます(参考:厚生労働省)。
ステップ5.ケアマネージャー選び
要支援・要介護の認定を受けると、介護サービスの計画(ケアプラン)を作成する専門家である「ケアマネジャー」を選ぶことになります。
ケアマネジャーは、ご本人やご家族の希望を聞き、膨大なサービスの中から最適な組み合わせを提案し、事業者との連絡調整まで行う、在宅介護の「司令塔」です。
信頼できるケアマネージャーの選び方を参考に、複数の事業所の情報を集め、相性がよく、親身に相談に乗ってくれるパートナーを見つけることが、その後の在宅介護の満足度を大きく左右します。
ステップ6.ケアプランの作成
ケアマネジャーが決まったら、ご本人やご家族の状況、希望などを詳しく伝え、どのような生活を送りたいかを一緒に話し合いながら、具体的なケアプランを作成していきます。
「週に2回デイサービスに通って、他の人と交流したい」「訪問ヘルパーさんに、入浴の介助と掃除をお願いしたい」など、ご本人の意思を最大限に尊重することが大切です。
このケアプランが、その後の在宅介護の設計図となります。
完成したプランの内容に納得したら、署名・捺印をして同意します。
ステップ7.サービス事業者との契約・利用開始
ケアプランで利用することが決まった各サービス事業者と、個別に契約を結びます。
契約の際には、サービスの内容や料金、緊急時の対応などについて、重要事項説明書を元に詳しい説明を受けます。
内容をよく理解し、納得した上で契約を交わしましょう。
契約が完了すれば、いよいよケアプランに沿った在宅介護サービスの利用がスタートします。
サービス開始後も、ケアマネジャーが定期的に訪問し、プランが適切かどうかの確認(モニタリング)を行ってくれます。
在宅介護で必要な住環境設備と福祉用具
安全で快適な在宅介護を実現するためには、ご自宅の環境を整えることも非常に重要です。
手すりの設置や段差の解消といった住宅改修や、介護ベッドなどの福祉用具を活用することで、ご本人の自立を促し、介護するご家族の身体的な負担を軽減できます。
介護保険を利用して、費用負担を抑えながら環境を整えることが可能です。
導線設計
ご本人が日常的によく移動する場所、特に寝室からトイレ、浴室への動線を「メイン動線」と考え、安全対策を優先的に行うことが重要です。
廊下に手すりを設置したり、小さな段差につまずき防止のスロープを置いたりするだけでも、転倒リスクを大幅に減らすことが可能です。
また、部屋の整理整頓を心がけ、床に物を置かないようにすることも、安全な動線確保の基本となります。
夜間の移動に備えて、足元を照らすセンサーライトなどを設置するのも効果的です。
主要用具
介護保険を利用して、費用の一部負担でレンタルまたは購入できる福祉用具は、在宅介護の強い味方です。
身体の状態に合わせて適切な用具を選ぶことで、生活の質(QOL)を大きく向上させられます。
厚生労働省によると、福祉用具貸与の対象は13品目で、要介護度に応じて利用可能な用具が異なります。
代表的な福祉用具は以下の通りです。
- 特殊寝台(介護ベッド):背上げや高さ調節の機能があり、起き上がりや移乗を助ける
- 車いす:屋内外の移動をサポート
- 歩行器・歩行補助つえ:安定した歩行を助け、転倒を防ぐ
- 手すり:工事を伴わない、置くだけのタイプなど
- ポータブルトイレ:寝室からトイレまでの移動が困難な場合に設置
福祉用具のレンタルや購入については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談し、最適なものを選びましょう。
住宅改修の対象と申請のコツ
手すりの取り付けや段差の解消、滑りにくい床材への変更、和式トイレから洋式トイレへの交換など、比較的小規模な住宅改修も介護保険の給付対象となります。
厚生労働省によると、支給限度基準額20万円まで、費用の7〜9割が支給されます。
支給限度基準額は、要支援・要介護区分にかかわらず定額で生涯20万円までです。
しかし、要介護状態区分が3段階以上上がった場合には、再度20万円まで住宅改修費が支給されます(参考:厚生労働省)。
住宅改修を成功させるコツは以下の通りです。
- 必ず工事前に申請:事前の申請がないと保険給付を受けられないため注意が必要
- ケアマネジャーに相談:どの改修が必要か、専門的な視点からアドバイス
- 複数の業者から見積もり:適正な価格と内容で工事を行ってくれる業者を選ぶ
これらのポイントを押さえることで、制度を最大限に活用し、安全な住環境を整えることが可能です。
在宅介護の費用と負担を軽くする制度活用術
在宅介護を始めるにあたり、多くの方が最も心配するのが「お金」の問題ではないでしょうか。
在宅介護の費用は、要介護度や利用するサービスによって大きく変動します。
しかし、その仕組みと負担を軽減するための制度を正しく知ることで、漠然とした不安を解消し、計画的な資金準備が可能になります。
費用の内訳
在宅介護にかかる費用は、大きく2つに分けられます。
ひとつは、介護保険サービスを利用した際の自己負担額です。
所得に応じて、サービス費用の1割〜3割を負担します。
ただし、要介護度ごとに月々の利用上限額(区分支給限度基準額)が定められており、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となるので注意が必要です。
もうひとつは、介護保険の適用外となる費用です。
具体的には、デイサービスなどでの食費やおむつ代、医療費、交通費などがこれにあたります。
これらの費用は全額自己負担となるため、事前に予算に組み込んでおく必要があります。
サービス組み合わせ例と月額費用シミュレーション
実際にどれくらいの費用がかかるのか、要介護2の方(自己負担1割)をモデルケースにシミュレーションしてみましょう。
2024年現在、要介護2の区分支給限度基準額は19,705単位(約197,050円)です(参考:厚生労働省)。
あくまで一例ですが、具体的なイメージを掴む参考にしてみてください。
| サービス内容 | 利用回数 | 介護保険自己負担額(目安) |
| 訪問介護(身体介護30分) | 週2回 | 約3,200円 |
| 訪問看護 | 週1回 | 約2,300円 |
| 通所介護(デイサービス) | 週3回 | 約9,000円 |
| 福祉用具レンタル(ベッド・車いす) | – | 約1,200円 |
| 合計 | 約15,700円 | |
| <保険外費用> | ||
| デイサービスの食費 | 12回 | 約9,600円 |
| おむつ・消耗品代 | – | 約10,000円 |
| 月額費用の合計目安 | 約35,300円 |
MCSの287ホーム、3,821名に及ぶケアデータ分析では、科学的根拠に基づく自立支援ケアが、介護度の改善や医療費の削減につながることが示唆されています。
これは、長期的な経済負担の軽減にも貢献する可能性があります。
必ず使うべき負担軽減制度
高額な費用がかかった場合でも、家計の負担を軽減するためのセーフティネットが用意されています。
これらの制度は申請が必要なものも多いため、知っているかどうかが大きな差につながります。
必ず押さえておきたい制度は以下の通りです。
- 高額介護サービス費制度:1か月の介護保険自己負担額の合計が、所得に応じた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度。厚生労働省によると、一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円。
- 高額医療・高額介護合算療養費制度:医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合算し、基準額を超えた場合に、その超えた分が支給される(参考:厚生労働省)。
- 医療費控除:おむつ代や訪問看護の利用料などが、税金の控除対象となる場合
自治体によっては、独自の助成金や介護手当を設けている場合もあるため、ケアマネジャーや市区町村の窓口で確認してみましょう。
「共倒れ」を防ぐ在宅介護での家族の負担を減らす5つの戦略
在宅介護は、いつまで続くか分からない長い道のりです。
大切なのは、介護者であるご家族が、決して無理をしすぎないこと。
「自分が頑張らなくては」という思いが、気づかぬうちに心と身体を追い詰め、「共倒れ」という最悪の事態を招きかねません。
ここでは、そうならないための5つの具体的な戦略をご紹介します。
レスパイト戦略:「ショートステイ」「デイサービス」活用
レスパイトとは「休息」を意味する言葉です。
デイサービスやショートステイを計画的に利用し、介護者が意識的に介護から離れる時間を作ることが、在宅介護を長く続ける秘訣です。
「サービスを利用するのは、なんだか申し訳ない…」と感じる必要はまったくありません。
介護者が心身ともに健康でいることこそが、ご本人にとって最大の利益となるのです。
自分の趣味の時間や、友人と会う時間などを確保し、リフレッシュすることを心がけましょう。
ワンオペ回避戦略:家族会議の進め方と「役割分担シート」
介護を特定の一人だけに任せる「ワンオペ介護」は、非常に危険です。
兄弟や親族が集まり、「誰が」「何を」「いつ」やるのかを具体的に話し合う家族会議を開きましょう。
その際、感情的にならず、現状の課題や費用、それぞれの想いを共有することが大切です。
話し合った内容は、「役割分担シート」のような形で書き出し、全員が見える化すると効果的です。
| 役割 | 担当者 | 具体的な内容 |
| キーパーソン | 長男・〇〇 | ケアマネジャーとの主な連絡、全体の調整 |
| 金銭管理 | 長女・△△ | 介護費用の支払い、公的制度の申請 |
| 通院付き添い | 次男・□□ | 月1回の定期通院の付き添い |
| 安否確認 | 全員 | 曜日を決めて、毎日誰かが電話 |
このように役割を明確にすることで、一人にかかる負担を分散し、チームで介護に取り組む意識が生まれます。
仕事両立戦略:介護休業・介護休暇を使いこなすための知識
「介護離職」は、ご家族にとっても社会にとっても大きな損失です。
働きながら介護を続けるために、法律で定められた支援制度を知っておきましょう。
知っておくべき主な制度は以下の2つです。
- 介護休業:対象家族1人につき、通算93日まで取得できる休業制度。雇用保険から介護休業給付金も支給される。厚生労働省によると、介護休業給付金は、「対象家族について93日を限度に3回までに限り支給」される。
- 介護休暇:通院の付き添いや手続きなどのために、年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、時間単位で取得できる休暇
これらの介護休暇と介護休業制度は、労働者の権利です。
ひとりで抱え込まず、会社の上司や人事部に相談し、制度を積極的に活用しましょう。
テクノロジー戦略:月数千円で安全を買う「見守りカメラ」「センサー」活用術
近年、介護分野でもテクノロジーの活用が進んでいます。
月額数千円から利用できる見守りサービスやセンサー機器を導入することで、離れていてもご本人の安全を確認でき、介護者の精神的な負担を大きく軽減できます。
在宅介護で役立つ主なテクノロジーは以下の通りです。
- 見守りカメラ:スマートフォンから室内の様子を確認でき、会話も可能
- 開閉センサー:玄関ドアや窓に設置し、開閉をスマートフォンに通知
- ベッドセンサー:ベッド上の起き上がりや離床を検知し、転倒防止に役立つ
- 服薬支援サービス:設定した時間になると薬ケースが開き、服薬を促す
MCSの施設でも、睡眠センサーなどを活用した科学的介護を実践しています。
これらの技術を在宅介護に取り入れることで、24時間体制の見守りが難しいという課題を補うことが可能です。
身体負担軽減戦略:腰を痛めない介護技術と福祉用具の活用
誤った方法での介助は、介護者の腰痛など身体的な不調の原因となります。
てこの原理などを応用し、小さな力で効率的に介助を行う「ボディメカニクス」という介護技術を学ぶことが、ご自身の身体を守る上で非常に重要です。
また、食事介助時の誤嚥性肺炎は、介護者が最も注意すべきリスクのひとつです。
新潟医療福祉大学の西尾正輝教授が開発した「ノドトレ」は、1回5秒の簡単なトレーニングで嚥下機能を向上させる科学的エビデンスに基づいたプログラムです。
このような専門的な知識を取り入れることも、介護者の技術的な負担軽減につながります。
福祉用具と正しい知識、この両輪で身体的負担を最小限に抑えましょう。
在宅介護の具体的な課題と解決策のケーススタディ
在宅介護では、ご本人の病気や状態によって、直面する課題もさまざまです。
ここでは、よくある4つのケースを取り上げ、具体的な課題と解決策を、MCSが運営する施設での改善事例を元に解説します。
これらの事例は、在宅介護における問題解決のアプローチのヒントとなるはずです。
ケース1.認知症:徘徊・暴言・介護拒否への対応
認知症の症状は、ご本人もご家族も混乱させ、在宅介護を困難にする大きな要因です。
特に、目的もなく歩き回る「徘徊」や、突然の暴言、入浴や着替えを拒否するといった行動は、対応に苦慮するご家族が少なくありません。
大切なのは、その行動の裏にあるご本人の不安や混乱した気持ちを理解しようとすることです。
頭ごなしに否定せず、まずは気持ちを受け止め、安心できる言葉をかけることが第一歩となります。
認知症のこだわりへの対応も同様に、寄り添う姿勢が大切です。
ケース2.寝たきり:褥瘡予防・医療的ケア・訪問看護の重要性
寝たきりの方の在宅介護では、専門的な知識とケアが不可欠です。
特に注意したいのが、長時間同じ姿勢でいることで皮膚が圧迫され、血流が悪くなって組織が壊死してしまう「褥瘡(じょくそう)」、いわゆる床ずれです。
褥瘡を予防するためには、2時間おきの体位変換や、体圧分散マットレスの活用が基本となります。
また、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要になる場合も多く、その際は訪問看護師との密な連携が生命線となります。
ご家族だけで抱え込まず、専門家の力を最大限に活用することが重要です。
ケース3.一人暮らし・遠距離介護:見守り体制の構築と緊急時連絡網
お子さんが遠方に住んでいるなど、高齢者の一人暮らしが増えています。
この場合の在宅介護では、「いかにして見守り体制を築くか」が最大のテーマです。
前述した見守りカメラやセンサーといったテクノロジーの活用はもちろん、地域との連携も非常に重要になります。
愛知県の望月ユウ子さんの事例では、地域住民の協力による見守り体制を構築し、一人での散歩を実現しました。
民生委員や近隣住民、配食サービス業者など、地域社会の目を借りて、多角的な見守りネットワークを作ることが、孤立を防ぎ、いざという時の早期発見につながります。
>愛の家グループホーム 弥富「”その人らしさ”を支える、地域との関わり」で詳細を見る
ケース4.看取り:人生の最終段階を家で穏やかに過ごすためのACPと緩和ケア
「最期は住み慣れた自宅で迎えたい」と希望される方は少なくありません。
その願いを実現するためには、事前の準備と意思表示が重要になります。
「人生会議(ACP)」とは、もしもの時のために、ご本人が望む医療やケアについて、前もって家族や医療・ケアチームと話し合い、共有するプロセスのことです。
また、痛みや苦しみを和らげる「緩和ケア」を中心に、訪問診療医や訪問看護師がチームとなって、穏やかな最期を迎えられるよう支援します。
ご本人の尊厳を守り、ご家族が後悔なくお見送りできるよう、専門家と共に準備を進めましょう。
スポンサーリンク
在宅介護が「もう限界かもしれない」と感じた時の処方箋
どんなに準備をしても、どんなに工夫をしても、在宅介護には心身の限界が訪れることがあります。
大切なのは、そのサインを見逃さず、無理をしすぎないこと。
「限界」は失敗ではありません。
介護の形を見直すための、重要な軌道修正のシグナルなのです。
危険を知らせる「限界シグナル」チェックリスト
ご自身の状態を客観的に把握するために、以下の項目をチェックしてみましょう。
3つ以上当てはまる場合は、危険信号が灯っている可能性があります。
- よく眠れない日が続いている
- 食欲がなく、体重が減ってきた
- ささいなことでイライラしたり、涙もろくなったりする
- 趣味など、今まで楽しめていたことが楽しめない
- 介護以外のことを考える余裕がまったくない
- 頭痛や腰痛など、身体の不調が続いている
- 介護中に、ご本人に対して強い言葉をぶつけてしまうことがある
介護の負担から介護うつに陥る方も少なくありません。
ひとりで抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。
今すぐできる「ケアプランの見直し」と「サービス追加」
限界を感じたら、まずは在宅介護の司令塔であるケアマネジャーに「正直にしんどい」と伝えましょう。
ケアマネジャーは、現状の課題を整理し、解決策を一緒に考えてくれる最も身近な専門家です。
例えば、デイサービスの利用日数を増やしたり、ショートステイを定期的に組み込んだりするなど、ケアプランを見直すことで、ご家族の負担を軽減できる場合があります。
使えるサービスはまだ残っているかもしれません。
諦める前に、まずは相談してみましょう。
「施設介護」を検討するタイミングと判断基準
ケアプランを見直しても、在宅での生活が困難になるケースもあります。
その場合、「施設介護」はご本人とご家族の双方を守るための、前向きで重要な選択肢となります。
以下のような状況が見られる場合は、施設入所を具体的に検討するタイミングといえるでしょう。
- 医療的ケアの必要性が高い:痰の吸引や経管栄養などが24時間必要になった場合
- 認知症の症状が重度化:徘徊や暴力・暴言が頻繁になり、ご家族の対応が困難になった場合
- 介護者の健康状態の悪化:介護者自身が体調を崩し、介護の継続が難しくなった場合
在宅にこだわりすぎることが、かえってご本人の安全を脅かし、ご家族を追い詰める結果になっては本末転倒です。
専門家と相談しながら、最適なタイミングで次のステップへ進む勇気も必要です。
スポンサーリンク
ひとりで悩まない在宅介護の相談窓口一覧
在宅介護は、情報戦であり、チーム戦です。
ひとりで悩まず、さまざまな専門家や仲間とつながることが、長い道のりを乗り越えるための最大の力となります。
あなたの状況に応じて、頼れる相談窓口を知っておきましょう。
公的な総合相談窓口
介護に関する最初の入り口として、まず頼るべき場所です。
介護保険の手続きから、地域のサービス情報まで、あらゆる相談に対応してくれます。
介護の相談窓口は、あなたの悩みを整理し、適切な専門機関に繋いでくれるハブの役割を果たします。
- 地域包括支援センター
- 市区町村の高齢者福祉担当課
ケアプランの相談
具体的な介護サービスの利用計画に関する相談窓口です。
ケアマネジャーは、ご本人やご家族の希望に沿って、最適なサービスを組み合わせたケアプランを作成してくれます。
- 居宅介護支援事業所
認知症の悩み
認知症の症状や対応方法について、専門的なアドバイスを受けられます。
医療的な相談から、日々の生活の悩みまで、幅広く対応しています。
厚生労働省により全国的に整備されている認知症疾患医療センターでは、認知症の専門相談、鑑別診断、薬物療法・非薬物療法、地域連携、認知症の人やその家族に対する診断後支援を行っています。
また、公益社団法人認知症の人と家族の会では、無料電話相談(0120-294-456)を平日10:00~15:00に実施しています(認知症の人と家族の会)。
認知症相談は、ご本人とご家族の双方にとって心強い支えとなるでしょう。
- 認知症疾患医療センター
- 認知症の人と家族の会
同じ立場の仲間とつながる
専門家への相談とは別に、同じ立場で介護をしている仲間と悩みを分かち合うことも、大きな心の支えになります。
共感し合える仲間がいることで、孤独感が和らぎ、前向きな気持ちを取り戻せることも少なくありません。
- 地域の家族介護者の会
- 社会福祉協議会
MCSでは、未来を担う子ども達への認知症教育にも力を入れています。
家族だけでなく、地域全体で介護を支えるという意識を育むことが、これからの社会には不可欠です。
―「認知症の祖父を避けていたけれど、これからは祖父の家を多く訪れたい」― 当社は、小・中・高校生を主な対象とし、認知症…
スポンサーリンク
在宅介護に関してよくある疑問
ここでは、在宅介護に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
正しい知識を持つことが、不要なトラブルを避け、よりよい介護につながります。
在宅介護においてやってはいけないことは?
ご本人の尊厳を傷つけ、安全を脅かす行為は、決して許されません。
特に以下の点は、虐待と見なされる可能性もあるため、絶対に避けるべきです。
- 身体的拘束:ご本人の意思に反して、ベッドに縛り付けたり、部屋に閉じ込めたりする行為
- 介護放棄(ネグレクト):食事を与えない、おむつを替えないなど、必要な介護を意図的に行わないこと
- 心理的虐待:暴言を吐いたり、無視をしたりして、精神的に苦痛を与えること
- 医療行為:医師や看護師の指示なく、インスリン注射や褥瘡の処置などを行うこと
追い詰められて、つい手や口が出てしまいそうになったら、それはあなた自身が助けを求めるべきサインです。
すぐにケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみてください。
サービス併用するのはあり?
はい、もちろん可能です。
むしろ、在宅介護はさまざまなサービスを効果的に併用することが基本となります。
例えば、「平日はデイサービスに通い、週末は訪問介護を利用する」「訪問看護と訪問リハビリを組み合わせて、医療と機能回復の両面からアプローチする」といったように、ケアマネジャーと相談しながら、ご本人の状態やご家族の生活リズムに合わせて、最適なサービスの組み合わせ(ケアプラン)を作っていきます。
介護保険サービスと、保険外の自費サービスを組み合わせることも、もちろん可能です。
ケアマネージャーの変更と不満時の対応は?
ケアマネジャーは在宅介護を共に進める重要なパートナーですが、人間同士なので相性の問題や、方針が合わないことも起こりえます。
もし不満や疑問を感じた場合は、まずはご本人に直接、具体的に伝えてみましょう。
それでも改善が見られない場合や、直接言いにくい場合は、ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所の管理者や、市区町村の介護保険担当課、地域包括支援センターに相談することが可能です。
そして、最終的にはケアマネジャーを変更することもできます。
我慢し続ける必要はありませんので、勇気を出して相談してみてください。
まとめ
この記事では、在宅介護の基本的な知識から、具体的なサービス、手続きの流れ、費用の話、そしてご家族の負担を軽くするための戦略まで、網羅的に解説してきました。
在宅介護は、決して楽な道のりではありませんが、正しい知識と準備があれば、不安を安心に変え、乗り越えていくことが可能です。
最も大切なポイントは、「決してひとりで抱え込まない」ということです。
介護保険には、あなたの介護を支えるためのさまざまなサービスが用意されています。
そして、あなたの周りには、ケアマネジャーをはじめ、医師、看護師、地域の相談員など、頼れる専門家が多くいます。
在宅介護という長い旅路は、始まったばかりかもしれません。
しかし、あなたにはもう、進むべき道を示す地図と、頼れる仲間がいます。
この記事を参考に、まずは「地域包括支援センター」に電話を一本かける、あるいは、ご家族と今後のことを話し合う場を設けるなど、今日からできる小さな一歩を踏み出してみてください。
その一歩が、ご本人と、そしてあなた自身の未来を、よりよい方向へと導くはずです。