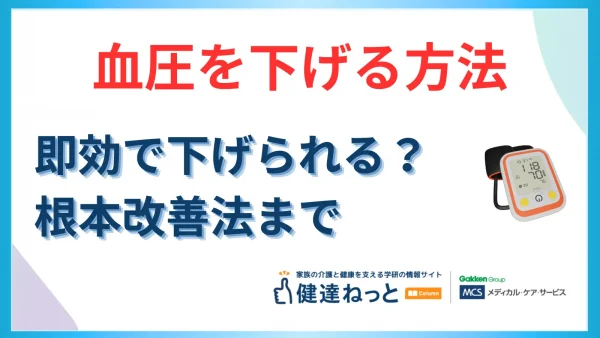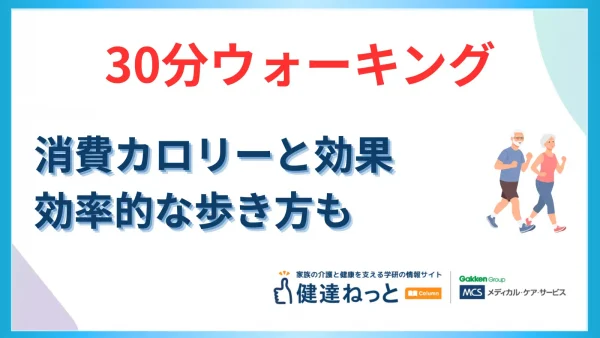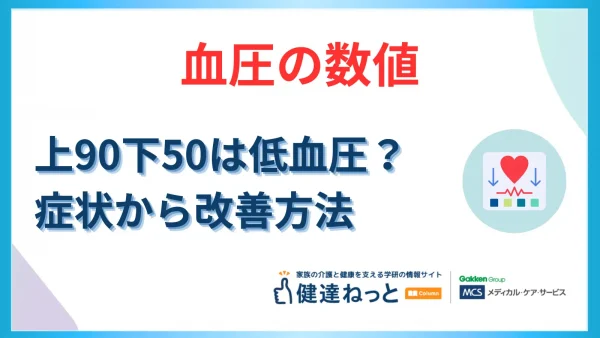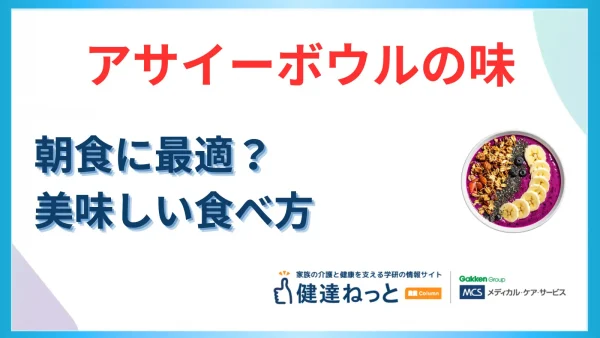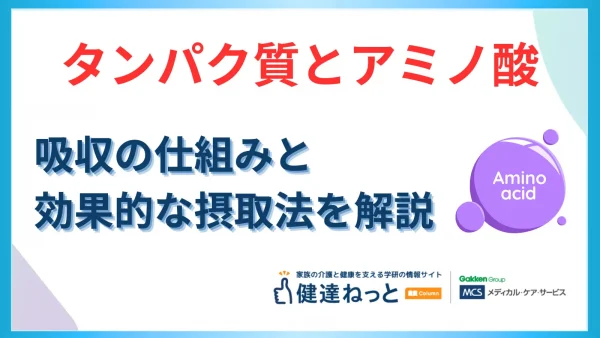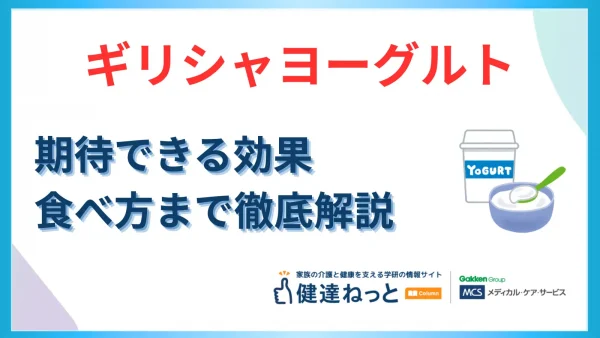- 「健康診断で血圧が高いと指摘された…」
- 「このまま放置したら、将来大きな病気になってしまうのでは…」
- 「今すぐどうにかしたいけど、血圧を下げる即効性のある方法ってないの?」
このような不安や焦りを感じていませんか。
大切なご自身の健康のことだからこそ、心配になるのは当然です。
血圧の数値は日々の体調やストレスでも変動するため、一喜一憂してしまう方も少なくありません。
この記事では、そのようなお悩みを解決するために、「血圧を下げる即効性」という疑問の真相から、日々の生活で実践できる具体的な改善策まで、科学的根拠を元に徹底解説します。
- 結論:医学的に安全な「即効性のある方法」は存在しないという事実
- 応急処置:一時的に血圧を落ち着かせる3つの方法
- 食事改善:血圧に影響を与える飲み物・食べ物の選び方
- 生活習慣:根本から血圧を安定させる7つの習慣
この記事を最後まで読めば、血圧に関する正しい知識が身につき、いたずらに不安を募らせることなく、ご自身の健康と向き合うための具体的な第一歩を踏み出せるようになります。
スポンサーリンク
【結論】即効性のある血圧を下げる方法は存在しない
「血圧を今すぐ下げたい」と焦る気持ちはよくわかります。
しかし、その疑問に医学的な視点から真っ直ぐにお答えします。
医学的根拠に基づいて明確にお伝えすると、血圧を即座に正常値まで下げる安全で効果的な方法は存在しません。
急激な血圧低下は脳血流の低下や臓器虚血を引き起こす可能性があります。
脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な合併症を引き起こすリスクがあるため、医学的に危険とされています。
高血圧の改善には、継続的な生活習慣の見直しと適切な医療管理が不可欠です。
高血圧の治療は長期的な取り組みが必要であることが示されています。
まずは医学的根拠に基づいた高血圧の正しい理解を深め、焦らずじっくりと取り組む姿勢が大切になります。
スポンサーリンク
【応急処置】今すぐ血圧を下げたい(落ち着かせたい)時に試せる3つの方法
即効性はないとわかっても、一時的な血圧上昇には対処したいものです。
ここでは、あくまで応急処置として心身を落ち着かせる3つの方法を紹介します。
深呼吸でリラックスする
ストレスや緊張による一時的な血圧上昇には、深い呼吸を意識することが効果的です。
ゆっくりとした深い呼吸は、興奮状態のときに優位になる交感神経の働きを抑え、リラックスしているときに優位になる副交感神経を活性化させるためです。
これにより、心拍数が落ち着き、血管の緊張がほぐれて血圧の安定につながります。
私たち健達ねっとが提供する介護ケアの指針「MCSケアモデル」でも、高齢者の心身の安定を図るために呼吸法を重視しています。
ご自宅で簡単にできる深呼吸の方法は以下の通りです。
- STEP1:楽な姿勢で座り、鼻から4秒かけてゆっくり息を吸い込む
- STEP2:7秒間、息を止める
- STEP3:口から8秒かけてゆっくりと息を吐き切る
この呼吸法を数回繰り返すことで、心身がリラックスモードに切り替わります。
効果的なストレス管理方法や自律神経を整える13の方法とあわせて、日々の習慣に取り入れてみましょう。
血圧を下げる効果が期待できるツボを押す
東洋医学に基づくツボ押しも、応急的な対処法のひとつとして知られているものです。
ツボを刺激することで血行が促進され、自律神経のバランスが整うことで、一時的に血圧が落ち着く効果が期待できるといわれています。
特に「人迎(じんげい)」というツボは、血圧の急な変動を抑える効果が期待されます。
のどぼとけのすぐ横で、脈を感じる部分にあり、指で軽く触れるように刺激するのがポイントです。
その他、血圧安定に役立つとされる主なツボを以下にまとめました。
| ツボの名前 | 場所 |
|---|---|
| 合谷(ごうこく) | 手の甲の親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみ |
| 手心(しゅしん) | 手のひらの中央 |
| 完骨(かんこつ) | 耳の後ろにある骨のふくらみの下のくぼみ |
これらのツボを、気持ちよいと感じる程度の強さで5秒ほどゆっくり押し、離す動作を数回繰り返してみてください。
ただし、これはあくまで一時的な対処法であり、根本的な改善にはつながらないことを理解しておきましょう。
ぬるめのお湯で手足を温める
38~40℃程度のぬるめのお湯で手や足を温めることで、リラックス効果が期待できます。
手足の末梢血管が広がることで血流が改善され、副交感神経が優位になり心身が落ち着くためです。
この方法は、健達ねっとの血圧の正常値に関する記事でも、安全なリラックス法として推奨しています。
42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激し、逆に血圧を上昇させてしまう可能性があります。
そのため、40℃程度のぬるめの湯で5-10分程度に留めることが推奨されています。
入浴によるリラックス効果を最大限に引き出すためにも、必ずぬるめのお湯を使用してみてください。
- 方法:洗面器などに38~40℃のお湯を張り、10~15分ほど手首や足首までつける
- タイミング:就寝前などリラックスしたいとき
- 注意点:熱すぎるお湯は避ける
手軽にできるリフレッシュ方法として、日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【即効性よりも継続が重要】今すぐ見直したい血圧に影響する飲み物や食べ物
血圧管理は、一朝一夕で成し遂げられるものではありません。
即効性を求めるよりも、毎日の食生活を着実に改善していくことが、最も確実な道といえます。
血圧を下げる効果が報告されている飲み物・食べ物
血圧が高めの方に適した成分として、GABA(γ-アミノ酪酸)が注目されています。
GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されており、機能性表示食品などにも活用されています。
例えば、健達ねっとが販売する「血圧ケアサプリメント」も、このGABAを機能性関与成分とした製品です。
GABAが血圧を下げるメカニズムが解明されており、末梢神経に存在するGABAb受容体と結合することによって、血管を収縮させるノルアドレナリンという物質の分泌を抑制することで血圧が低下すると考えられています。
1日30mg以上のGABA摂取で効果が期待され、正常血圧者には影響を与えず、血圧高めの方にのみ降圧効果を示すことが確認されています。
GABAの他にも、血圧によい影響を与えるとされる飲み物や食品があります。
- ココア・緑茶:カカオポリフェノールやカテキンが血管の健康をサポート
- お酢:主成分の酢酸が血圧を穏やかにする働きが報告されている
- 乳製品:カルシウムやカリウムが豊富で、血圧調整に関与する
GABAの詳しい効果と含有食品について知り、これらの食品を毎日の食生活にうまく取り入れていくことが、血圧管理の第一歩となります。
血圧対策で積極的に摂りたい食べ物・栄養素
血圧管理においては、特定の食品を摂るだけでなく、栄養バランスの取れた食事が基本です。
特に意識して摂取したい栄養素と、それらを多く含む食品について解説します。
カリウムを多く含む食品
カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分の主成分)を腎臓から尿として体外へ排出するのを助ける重要なミネラルです。
塩分の摂りすぎは高血圧の大きな原因となるため、カリウムを積極的に摂ることは、効果的な血圧対策となります。
私たち健達ねっとの「MCS版自立支援ケア」でも、高齢者の健康維持のために、野菜や果物を十分に摂ることを重視しています。
カリウムは様々な食品に含まれていますが、特に豊富な食材は以下の通りです。
| 食品カテゴリ | 具体的な食材例 |
|---|---|
| 野菜 | ほうれん草、かぼちゃ、枝豆、アボカド |
| 果物 | バナナ、キウイフルーツ、メロン |
| いも類 | さつまいも、じゃがいも、里いも |
| 海藻類 | 昆布、ひじき、わかめ |
これらのカリウムが豊富な食材一覧を参考に、毎日の食事にバランスよく取り入れましょう。
ただし、腎臓に疾患がある方はカリウムの摂取制限が必要な場合があるため、必ず医師に相談してみてください。
カルシウム・マグネシウムを含む食品
カルシウムにも血圧を安定させる効果があり、マグネシウムも血圧の調整に欠かせないミネラルです。
カルシウムは骨の健康だけでなく、血管の収縮や弛緩にも関わっています。
また、マグネシウムはカルシウムの働きを助け、血管を広げて血圧を下げる効果が期待されます。
マグネシウムが血圧の1日のリズム(概日リズム)の調節に重要な役割を果たし、日々の活動期における血圧上昇を抑制する仕組みが解明され、心臓の健康に重要なミネラルとして注目されています。
健達ねっとのオリジナル商品「骨育注意報」にも、吸収性の高い海水由来のマグネシウムが配合されています。
以下の食品を意識して摂取し、不足しがちなミネラルを補いましょう。
- カルシウム:牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、豆腐、小松菜
- マグネシウム:ほうれん草、アーモンド、大豆製品、玄米、ひじき
食物繊維が豊富な食品
食物繊維は、腸内環境を整える働きでよく知られていますが、血圧管理においても重要な役割を果たします。
食物繊維は、食事に含まれるナトリウムの吸収を穏やかにし、体外への排出を促す効果があります。
また、コレステロール値を改善する働きもあり、動脈硬化の予防、ひいては血管の健康維持につながるのです。
健達ねっとの書籍「ハルと思い出めぐりごはん」で紹介している高齢者向けのレシピにも、食物繊維が豊富な食材がふんだんに使われています。
- 水溶性食物繊維:海藻類、こんにゃく、大麦、果物(水に溶けやすく、コレステロールや糖の吸収を緩やかにする)
- 不溶性食物繊維:きのこ類、豆類、ごぼう、玄米(水に溶けにくく、便通を促す)
これらの食品をバランスよく食事に取り入れることで、血圧だけでなく、総合的な生活習慣病の予防が期待できます。
【要注意】血圧を上げる可能性のある飲み物・食べ物
血圧を下げる努力と同時に、血圧を上げる可能性のある食品を避けることも非常に重要です。
知らず知らずのうちに摂取しているものが、血圧を上げる原因になっているかもしれません。
特に注意したいのは、塩分(ナトリウム)が多い食品です。
ラーメンやうどんの汁、加工食品、漬物などには多くの塩分が含まれています。
高血圧の食事療法完全ガイドでも指摘されているように、これらの摂取は控えるように心がけましょう。
また、飲み物にも注意が必要です。
| 注意すべき飲み物 | 理由 |
|---|---|
| 糖分の多い清涼飲料水 | 過剰な糖分は肥満につながり、血圧を上げる原因となる |
| アルコール | 適量を超えた飲酒は、血圧を上昇させることがわかっている |
| カフェイン飲料 | 一時的に血圧を上昇させる作用があるため、飲み過ぎには注意が必要 |
これらの食品や飲み物を完全に断つ必要はありませんが、量や頻度を意識して、上手に付き合っていくことが大切です。
自分の食生活を見直し、改善できる点から始めてみましょう。
【根本改善】即効性よりしっかり見直すべき血圧を安定させる生活習慣
応急処置や食事の見直しも大切ですが、血圧を根本から安定させるためには、生活習慣そのものを見直すことが不可欠です。
ここでは、科学的根拠に基づいた7つの生活習慣を紹介します。
減塩
高血圧の改善・予防において、減塩は最も基本的で重要な生活習慣です。
高血圧患者における減塩目標を1日6g未満にすることを強く推奨しており、一般成人の目標値として7g未満が設定されています。
日本人の平均食塩摂取量は約10gといわれており、目標達成には意識的な工夫が必要です。
健達ねっとの「MCSケアモデル」でも、栄養管理の観点から適切な塩分摂取を重視しています。
以下のような工夫で、美味しく減塩を続けましょう。
- 出汁や香味野菜(生姜、ネギなど)の風味を活かす
- 香辛料(こしょう、唐辛子など)や酸味(酢、レモン汁)を利用する
- 加工食品やインスタント食品の利用を控える
- 麺類の汁は飲まない(麺類の汁を全部残すことで2-3gの減塩効果があるとされています)
健達ねっとで紹介している美味しい減塩レシピなども参考に、日々の食事に取り入れてみてください。
適度な有酸素運動
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、血圧を下げる効果が期待できます。
運動によって血管が広がり、血流がよくなるほか、継続することで心肺機能が高まり、血圧が安定しやすくなるのです。
高血圧治療の基本として生活習慣の修正と降圧薬治療が挙げられています。
高血圧症の発症や予防には、習慣的な運動や身体活動の増加が有用であることは多くの研究により証明されているとして、ややきついと感じる中等度の有酸素運動を推奨しています。
さらに、軽い運動(散歩・自分のペースでのジョギング・ラジオ体操・自転車にのる)は、血液の流れをよくし、全身によいだけでなく、肥満防止につながり気分転換にもってこいであると説明されています。
まずはウォーキングの正しい方法と効果を学び、無理のない範囲で週3日以上、1回30分程度を目安に始めてみましょう。
タオルグリップ法
「タオルグリップ法」は、自宅で手軽にできる血圧改善のための運動です。
タオルを握る・緩めるという簡単な動作を繰り返すことで、血管の柔軟性を高める効果が期待できます。
この方法はカナダのマックマスター大学のフィリップ・ミラー博士が開発した「ハンドグリップ法」を基にしており、アメリカの心臓病学会が高血圧の補完療法として、その効果を認めています。
タオルを握ると一時的に前腕の筋肉が縮み血管が圧迫されるため血流が低下しますが、力を緩めた際に血管が拡張し血流が前の状態に戻ります。
その際、血管を拡張させる一酸化窒素(NO)が放出され、NOが全身に循環することで血管が拡張し、持続的に血圧が下がる仕組みと考えられているのです。
【タオルグリップ法のやり方】
- フェイスタオルを正方形に近い形になるよう折り畳み、端からくるくると巻いて筒状にする
- 椅子に座ってリラックスし、全力の30%程度の力で2分間握り続ける
- 1分間休憩する
- これを計3回繰り返し(所要時間8分間)、週3日実施する
注意事項として、最高血圧が180mmHg以上の重度の高血圧の方は禁忌であり、心臓病の人は主治医に事前に相談することが必要とされています。
適正体重(BMI25未満)を維持
肥満は高血圧の大きなリスク要因です。
体重が増加すると、体が必要とする血液量が増え、心臓への負担が大きくなるため血圧が上がります。
逆に、体重を減らすことは効果的な降圧につながるのです。
肥満判定基準でBMI=25以上は肥満とされ、BMIで25未満を目標とすることが推奨されています。
一般的に、体重が1kg減少すると、血圧は1~2mmHg程度下がるといわれています。
健達ねっとの血圧の正常値の記事でも、適正体重の維持が重要であると解説しています。
まずはご自身のBMI(Body Mass Index)を計算し、現状を把握しましょう。
| BMIの計算式と判定基準 |
|---|
| 計算式:体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) 判定基準(日本肥満学会):<18.5(低体重)、18.5~25未満(普通体重)、≥25(肥満) |
もし肥満に該当する場合は、食事療法と運動療法を組み合わせた効果的な体重管理方法で、月1~2kg程度の緩やかな減量を目指しましょう。
急激な減量は体に負担をかけるため、避けるべきです。
節酒・禁煙を心がける
過度なアルコール摂取や喫煙は、血圧を著しく上昇させる要因となるものです。
アルコールは一時的に血圧を下げることもありますが、長期的に飲み続けると交感神経を刺激し、慢性的な高血圧を招きます。
一般にたばこを吸うことで、1分間の脈拍は15~25回、血圧も10mmHg~20mmHg増加するといわれています。
喫煙により血管が収縮し、一時的に血圧が上がるばかりでなく、血液の流れを悪くし、血液が凝固しやすくなり、動脈硬化の原因となるとされています。
具体的な節酒量と完全禁煙が推奨されており、適量とされている飲酒量は以下の通りです。
【推奨される節酒量(1日あたり)】
- 男性:日本酒なら1合=180cc、ビール中びん1本、ウイスキー水割ならシングル2杯まで
- 女性:男性の半分までが適量
禁煙や節酒は簡単ではないかもしれませんが、血圧管理と将来の健康のために、強い意志を持って取り組むことが大切です。
必要であれば、禁煙外来など専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
良質な睡眠の確保
睡眠不足や睡眠の質の低下は、血圧を上昇させる原因のひとつです。
睡眠中は副交感神経が優位になり、心身がリラックスして血圧は低下しますが、睡眠が不十分だと交感神経が活発な状態が続き、血圧が高いまま維持されてしまいます。
毎日規則正しい生活を送り休養を十分にとり疲れを残さないようにすることが重要であり、過重労働・超過勤務・夜更かしは禁物であるとされています。
健達ねっとの書籍「24時間のリズム習慣」でも解説しているように、規則正しい生活リズムを整えることが、質の高い睡眠と血圧の安定につながります。
特に、起床時間と朝食の時間を一定にすることが、体内時計を整える上で重要です。
【睡眠の質を高めるポイント】
- 毎日同じ時間に起き、太陽の光を浴びる
- 日中に適度な運動をする
- 就寝前のスマートフォンやPCの使用を控える
- ぬるめのお湯で入浴し、リラックスする
睡眠の質を改善する方法を実践し、心身をしっかりと休ませる習慣をつけましょう。
ストレスの管理
過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血圧を上昇させる大きな要因です。
ストレスを感じると交感神経が活発になり、血管が収縮して血圧が上がります。
過労や緊張、精神的ストレスをなるべくとり除くことの重要性が説明されています。
日々の生活からストレスを完全になくすことは難しいですが、上手に付き合っていく方法を見つけることが大切です。
健達ねっとの「MCSケアモデル」では、コミュニケーションを通じて安心できる環境を作ることが、ストレス軽減につながると考えています。
また、新潟医療福祉大学の西尾正輝教授が開発した「ノドトレ」は、嚥下機能の向上を目的とした簡単なプログラムですが、深呼吸と同様のリラックス効果が期待でき、血圧の安定にも寄与する可能性があります。
【ストレス管理のヒント】
- 趣味や好きなことに没頭する時間を作る
- 適度な運動で気分転換を図る
- 家族や友人とコミュニケーションをとる
- 深呼吸や瞑想などでリラックスする
自分に合ったストレス解消法を見つけ、心穏やかに過ごす時間を意識的に作ることが、結果として血圧の安定につながります。
まとめ
今回は、「血圧を下げる即効性」という疑問の真相と、根本的な改善策について解説しました。
重要なポイントは、医学的に安全で確実な即効性のある方法は存在しないということです。
医学的根拠に基づき、急激な血圧低下は危険を伴うことが明らかになっています。
血圧管理において最も大切なのは、焦らず、日々の生活習慣をひとつずつ見直し、継続していくことです。
応急処置として深呼吸やツボ押しを試しつつ、食事では減塩を基本に、カリウムやGABA、マグネシウムなどを意識的に摂取しましょう。
さらに、適度な運動、適正体重の維持、節酒・禁煙、良質な睡眠、ストレス管理といった生活習慣の改善に総合的に取り組むことが、根本的な解決への唯一の道です。
健達ねっとでは、GABA配合のサプリメントやマグネシウムを含む骨育注意報など、皆様の健康的な生活をサポートする商品もご用意しています。
この記事で得た知識を元に、今日からできることから始めてみませんか。
その一歩が、未来のあなたの健康を守る大きな力となります。
- 日本高血圧学会|高血圧治療ガイドライン2019
- 厚生労働省e-ヘルスネット|高血圧
- 日本高血圧学会|高血圧治療ガイドライン2019一般向け解説冊子
- 国立循環器病研究センター|高血圧
- 阪急阪神ヘルスケアサポート|WELL TOKK vol.16
- 美味技術研究会誌|ギャバ(GABA)の効能と有効摂取量に関する文献的考察
- ヤクルト本社|γ‐アミノ酪酸(GABA)の血圧降下作用
- 日本栄養士会|GABAの血圧
- 大阪大学微生物病研究所|マグネシウムによる血圧の概日リズム調節機構を解明
- 厚生労働省e-ヘルスネット|高血圧症を改善するための運動
- 致知出版社|フェイスタオルを握って高血圧を改善!? 一度は試したい「タオルグリップ法」
- 日本高血圧学会|高血圧治療ガイドライン